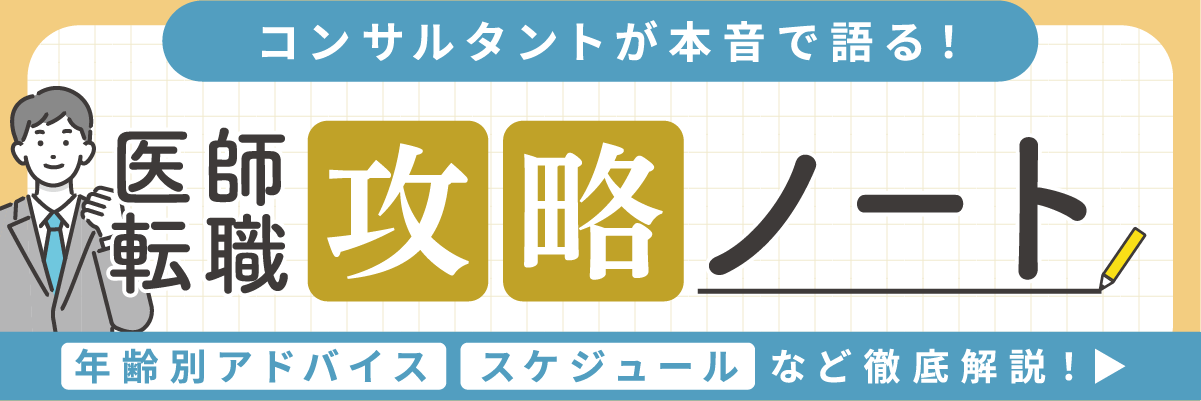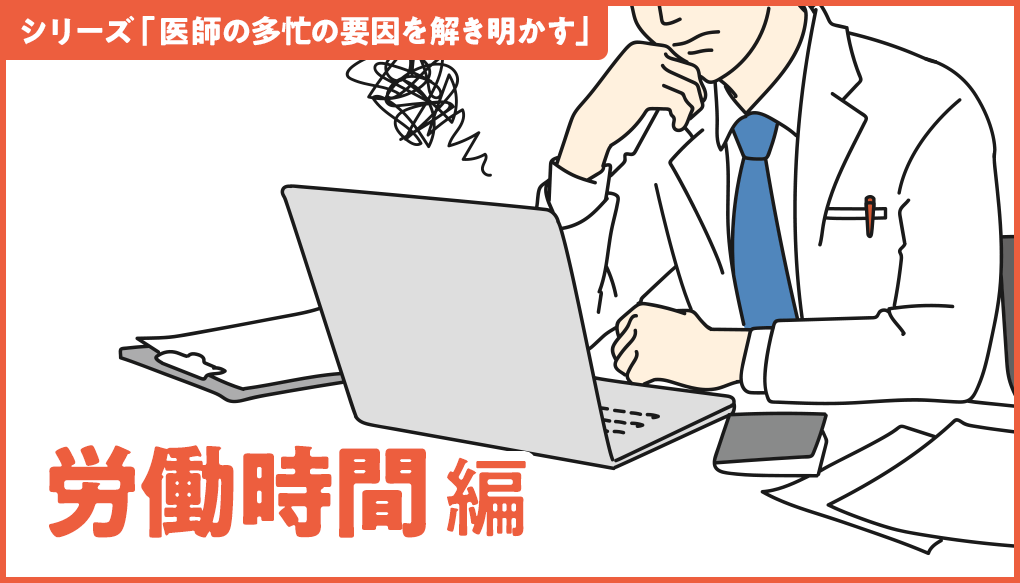2024年4月1日から施行された医師の働き方改革。制度が変わったとは聞くものの、実感がない先生も多いのではないでしょうか。
特に宿日直の扱いや残業の扱いが変わった一方で、実際の業務にどう影響しているのかは見えにくい部分もあります。「制度だけ整って、現場は以前と変わらない」と感じている先生の声もあるかもしれません。
そこで本記事では、「働き方改革が医療現場に与えた影響」について解説します。転職コンサルタントから見た「転職の変化」や「キャリアの変化」も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【2024年施行】医師の働き方改革とは

2024年4月1日に施行された医師の働き方改革では、時間外労働の上限が960時間と定められ、宿日直勤務の扱いも明確化されました。これにより、長時間労働が常態化していた医療現場に制度的な見直しが入りました。
ただし、この改革は一律の改善策ではなく、医療機関の規模や地域性によって対応のばらつきが見られます。Ubi株式会社が2025年に実施した調査によると、医師の60.3%が労働時間の短縮を実感していません。
また、タスク・シフト/シェアによって個々の従業員の業務負担を軽減する取り組みも推進されていますが、隠れ残業をする職員が増える(58.7%)など、未だ課題が多い状況です。
地域間・診療科間の医師偏在の是正も検討されてはいますが、2025年現在において統合的な対策パッケージ案の策定中であり、今後どうなっていくかは未定の状態となっています。
政府としても問題を是正したいとは考えているものの、具体的な改善に関してはまだまだ時間がかかると考えて良さそうです。
働き方改革が医療の現場に与えた変化

働き方改革の制度導入を受け、多くの医療機関で労働時間の見直しや業務の棚卸しが実施されています。中には、これまで当たり前だった日常的な時間外対応を記録・管理する仕組みが整い、負担の可視化が進んだケースもあります。
一方で、スタッフ数が限られる現場では、思うように進んでいないのが実状です。どのような変化があったのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- 宿日直許可が必要になった
- サービス残業が増えた
- アルバイトで生計を立てるのが難しくなった
- 医局のホワイト化が進んだ
宿日直許可が必要になった
宿日直勤務は、時間外労働とは異なる扱いとして「宿日直許可」が必要になりました。これにより深夜勤務が常態化していた職場では、制度に適合させるための体制見直しが求められています。
日本医師会が2024年10月23日に発表した「医師の働き方改革と地域医療への影響に関する日本医師会調査結果」によると、有床診療所・病院ともに制度開始前より宿日直許可を取得している数が増えており、有床診療所で31.0%、病院で93.9%となっています。
一方で、宿日直許可を取得していない医療機関への医師の派遣状況に関しては、有床診療所への派遣を断っているのが1.6%に止まるのに対し、病院へは9.4%もの数が派遣を断っている点が実状です。
特に病院に関しては派遣を断られるケースが増えているため、少なからず働き方改革の影響が出始めていると考えても良さそうです。
サービス残業が増えた
働き方改革の影響で勤務時間外の管理が厳しくなった一方、診療や事務作業の量自体は減っていません。そのため、タイムカード上では退勤済みでも、実際には院内で仕事をしているサービス残業が増えているようです。中には、労働環境がかえって悪化したと感じている医師もいます。
実際、前述のUbi株式会社が実施した調査によると、サービス残業が増えたと感じる医師は、58.7%となっています。研究や教育関連、患者さまの対応などによって、新しい改善策を講じる余裕がないというのが理由のようです。
表面的な労働時間の管理だけではカバーしきれない、医療現場における実質的な労働環境の解決が求められる状況といえます。
アルバイトで生計を立てるのが難しくなった
働き方改革の影響により、アルバイトによる収入確保が以前より難しくなってきたという声も聞かれます。
時間外労働の上限が定められたことで、常勤勤務と掛け持ちできるアルバイトの時間が限られてきたためです。また、宿日直の制限強化によって、これまで高収入が見込めた当直アルバイトも選択肢が狭まる傾向にあります。結果として、収入の柱をアルバイトに頼る働き方が通用しにくくなり、常勤先の給与や待遇の見直しを求める医師が一定数いる状態です。
実際、ドクタービジョンでもアルバイトで生計を立てるのではなく、常勤先を変更して給与面を見直そうとする先生が見受けられるようになっています。
医局のホワイト化が進んだ
医師の働き方改革を受けて、一部の大学病院では医局の労働環境改善が進んできたとの報告もあります。特に時間外勤務の管理や当直回数の制限が導入されたことにより、過重労働を見直す動きが見られるようになっています。
そのため、以前は「激務が当たり前」とされていた医局勤務でも、最近では働きやすさを重視した運営方針を打ち出すケースが増えてきました。医局離れが進む中で、環境を整えて人材を繋ぎとめようとする意識が高まっているのかもしれません。
一方で、「働き方が辛いために医局から転職したい」という理由が通用しなくもなってきています。
【働き方改革後】コンサルタントから見た働き方改革後の変化

毎日多くの先生とやり取りをしているドクタービジョンに所属の転職コンサルタントの視点から見た場合、働き方改革によってどのような変化があったのかを、以下の項目にわけてそれぞれ見ていきましょう。
- 実際に現場で働く医師に聞いた変化
- 転職の相談内容から見えてくる変化
実際に現場で働く医師に聞いた変化
医療機関の体制や規模によって状況は大きく異なり、改善が進んでいる現場もあれば、むしろ働きづらさが増しているケースもあります。
時間の制限がQOL向上につながったケース
人員に余裕がある大規模病院では、残業代の支給が明確になり、タスク・シフトも進んだことで、医師一人ひとりの負担が軽減。結果として、ワーク・ライフ・バランスの改善につながったケースもあります。時間で区切られた働き方により業務が効率化され、以前より診療に集中しやすくなったと感じている医師もいます。
時間制限が負担となっているケース
制度が導入されたことで業務が厳しくなったと感じる医師も少なくありません。勤務時間内に業務を終えなければならないというプレッシャーがかかり、かえって業務効率が下がってしまう場面も見られます。その結果、制度上は残業できないはずが、実態としてはサービス残業が常態化してしまっているケースもあります。
また、勤務時間が制限されたことで常勤先での収入が減り、収入を補うためにアルバイトの回数を増やさざるを得なくなったという声も出ています。
加えて、部下の勤怠を管理する立場にある医師にとっては、勤務状況のチェックや勤怠調整が業務負担となっており、本来の診療業務に集中しづらくなる場面も生じています。
医局のホワイト化で派遣先に人が集まらないケース
医局自体も働き方改革に対応する中でホワイト化が進んでいますが、人員確保が難しくなっている現状もあります。派遣先に十分な人数を送り出せず、現場の医師に一時的な負担が集中することもあります。非常勤医の採用が決まるまでの期間、業務量が増えるケースもあり、急な対応を求められることへの懸念が広がっています。
夜間や休日の体制維持が困難になっている医療機関もあり、外科や小児科など一部の診療科では、特定の時間帯に専門医が不在となる状況も発生しています。こうした事態により、診療体制そのものを見直さざるを得ないケースも出始めています。
転職の相談内容から見えてくる変化
転職の相談内容に関しては、大きな変化はありません。働き方改革が始まった当初は、宿日直許可を確認する先生が多く見られたものの、徐々に当たり前になってきたため、2025年7月現在は確認することも少なくなっています。
一方で、条件面に関してはアルバイトで生計を立てるのではなく、常勤先を変えようとする先生が一定数見受けられます。働き方改革は、転職市場全体にも少なからず影響を与えていると考えて良いでしょう。
コンサルタントが本音で語る医師の転職攻略ノートはこちら
働き方改革を機に医師の転職はどのように変わったのか

働き方改革の施行により、医師の転職理由にも徐々に変化が見られ始めています。これまでの主な理由が「収入の向上」や「診療科の変更」などであったのに対し、現在では「労働環境」や「勤務形態の柔軟性」といった要素も意思決定に影響を与えるようになってきました。
また、働き方改革の影響は、大学病院などの医局にも及んでいます。勤務環境のホワイト化が進み、残業や当直に関するルールが整備されつつあることから、「激務からの脱出」を目的とした転職は通用しづらくなってきた側面もあります。
さらに近年では、医療現場におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が高まりつつあり、ICTツールの導入状況や業務効率の改善度合いが、職場選びの比較基準として意識され始めています。カルテ入力の効率化やシフト管理のデジタル化といった要素は、医師のQOLに直結するため、今後は「ワーク・ライフ・バランスが取れるかどうか」が転職の判断基準として定着していく可能性があります。
このような変化は、すでに都市部や若手医師層を中心に広がっており、今後はより多くの層に波及していくと考えられます。
各医療機関での働き方改革の進捗

一方で、こうした転職理由の変化や" 理想の働き方 "がすべての医療機関で実現されているわけではありません。実際、働き方改革の制度対応には医療機関ごとのばらつきがあり、進捗状況は一様ではありません。
大規模病院では、人的・財政的リソースに余裕があることから、宿日直許可の取得や労務管理システムの導入といった対応が比較的スムーズに進んでいます。しかし、中小規模の診療所や地域医療機関では、制度対応に必要な事務的・人的コストの負担が重く、実務対応が後回しになっているケースも多く見受けられます。
さらに、制度対応が進んでいる大規模病院であっても、ICT活用の面では依然として課題を抱えているのが実情です。例えば、電子カルテの入力業務が煩雑であったり、医師同士の情報共有が非効率だったりと、労働時間の「見える化」はできていても、実際の負担軽減にはつながっていないケースもあります。
このように、制度的には改革が進んでいるものの、現場レベルでの実感や改善効果はまだ十分とは言えず、全体としては" 進捗は半ば "と捉えるのが現実的でしょう。
働き方改革による医師のキャリア形成の変化

2024年4月1日に施行された医師の働き方改革は、時間外労働の上限規制や宿日直の厳格な管理を通じて、医師の労働環境に一定の変化をもたらしました。この流れは今後、医師自身のキャリアプランにも少なからず影響を与えていく可能性があります。
ここでは、中長期的に医師のキャリア観や働き方がどう変化していく可能性があるかに焦点を当てて解説します。
時間制限が自己研鑽とキャリア設計を促す可能性
医師のキャリア形成はこれまで、医局に所属し、臨床経験を積みながら専門医を取得し、昇進していくという" 年功型・直線的ルート "が定番とされてきました。ただし、近年は医局に縛られない働き方や、個人の価値観に基づいたキャリアを選ぶ医師も増えており、すでに多様化が進みつつあります。
このような流れに加え、働き方改革によって時間外勤務の上限が明確に定められたことをきっかけに、今後さらに「ゴールから逆算したキャリア設計」が主流になっていく可能性があります。
例えば、「週4勤務にして自己研鑽の時間を確保する」といった形で、時間の使い方を起点にしたキャリア設計が浸透していくことが予想されます。症例レポートの準備や学会発表、専門医取得のための研修、あるいは英語論文の読み込みなど、日々の業務外で求められるタスクに時間を確保できるかどうかは、将来的なキャリア形成に直結します。
これまで" 隙間時間 "で行っていたこれらの活動に、あえて時間を割ける環境を選ぶことは、より戦略的なキャリア構築につながる選択肢と言えるでしょう。
「第2のキャリア」や「複線的キャリア」への関心が高まる可能性
これまで臨床業務に偏っていたリソースの配分を見直す動きが高まり、「診療だけに依存しないキャリア構造」を意識する医師が徐々に増え、キャリアの多様化に拍車がかかる可能性があります。例えば以下のように、臨床の枠を越えて新たな専門性や役割を築く動きが挙げられます。
- 地方自治体や企業の医療プロジェクトへの参画
- 医療法人の運営や経営に関わるポジションへの転向
- 大学院進学や研究活動による学術キャリアの構築
- 医療×IT、教育、行政など異分野との掛け合わせによる転身
こうした複線的なキャリア形成は、単なる「興味の追求」にとどまらず、制度改正や医療制度の変動といった外的変化に柔軟に対応できるキャリアとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。また、診療と並行してこうした" 第二軸 "を持つことで、将来的に選択肢を狭めずに働き続けられるという点でも、多くの医師にとって現実的かつ戦略的な選択肢となり得ます。
「継続できる働き方」がキャリア選びの主軸になる可能性
制度的に時間外勤務が制限されたことで、「キャリア=がむしゃらに働いて出世する」という価値観ではなく、「キャリア=長く、無理なく続けられる形にする」という方向に軸足を移す医師が増えていく可能性もあります。
これは、燃え尽き症候群や離職リスク、家庭との両立といった観点が、これまで以上にキャリアの持続性を左右する要因になりつつあるからです。NPO法人「EMアライアンス」が2021年に実施した調査によると、全国27の基幹病院に勤務する救急医のうち約10%が、医療過誤や離職リスクを伴う「深刻な燃え尽き症候群」の兆候を示していたと報告されています。
こうした状況を踏まえると、今後のキャリア形成では「がむしゃらな勤務」ではなく、自分自身の健康と生活を守りながら長く働ける設計=キャリアの質が重視されていくと考えられます。
「働き方改革後」のキャリア選びに迷ったら、ドクタービジョンへご相談を
医師の働き方改革によって、キャリアの考え方は確実に変化しつつあります。
「無理なく長く働ける職場を選びたい」
「家庭や研究、自己研鑽と両立できる環境に移りたい」
「将来の開業や副業も見据えた選択がしたい」
「家庭や研究、自己研鑽と両立できる環境に移りたい」
こうした" 多面的 "なキャリア戦略を描く医師が、今後さらに増えていくことが予想されます。
とはいえ、勤務条件や時間の制限が明文化される一方で、医療機関ごとの対応状況や実際の働きやすさにはまだ大きな差があります。自分にとって理想的な職場やキャリアパスを見極めるには、制度や業界動向に精通したサポートが必要です。
ドクタービジョンは、医師の求人・転職・募集に特化した専門サイトとして、働き方改革を踏まえたキャリア設計をサポートしています。 医療業界に精通したコンサルタントが、医師一人ひとりのご経験や志向に寄り添いながら、キャリアプランの構築をお手伝いします。
自己分析を始め、職務経歴書の作成支援などの準備段階のサポートはもちろん、勤務時間や待遇など、先生から採用担当者に伝えづらい要望を、担当コンサルタントが代わりに交渉することも可能です。さらに、全国に拠点を持つドクタービジョンでは、実際にコンサルタントが医療機関を訪問し、求人票では見えないリアルな情報もご提供しています。
変化の時代だからこそ、「これからの働き方」に真剣に向き合いたい。そんな医師の皆さまのご相談を、ドクタービジョンは無料で承っています。以下のリンクより、ぜひお気軽にお問い合わせください。
医師の働き方改革は抜本的な改善には至らず。キャリア形成も加味して転職も検討しよう

2024年4月1日に施行された医師の働き方改革は、医師を含めた医療業界が抱える問題の抜本的な改善に至っていないというのが現状です。設備や制度、人員などの課題から対応しきれていない医療機関も多く、医療機関によって大きな差が生じています。
したがって、キャリア形成においても、従来とほとんど変わらないのが実状です。医療機関が求める医師のニーズに大きな違いも見られないため、引き続きキャリア形成において転職は選択肢のひとつとして考えておいた方が良いでしょう。
ただし、医療機関によってはサービス残業が増えていたり、ICTに課題を抱えていたりと様々なケースがあります。転職活動をする際は、医療機関への豊富な知見を持つコンサルタントを利用し、どのような働き方になるのかイメージできるようにしておきましょう。
1分で登録完了!コンサルタントへの転職相談
「転職について気になることがある」「周りの転職活動の動向を知りたい」など、
まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。