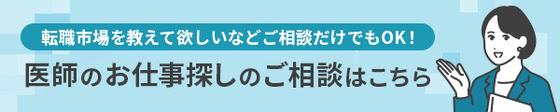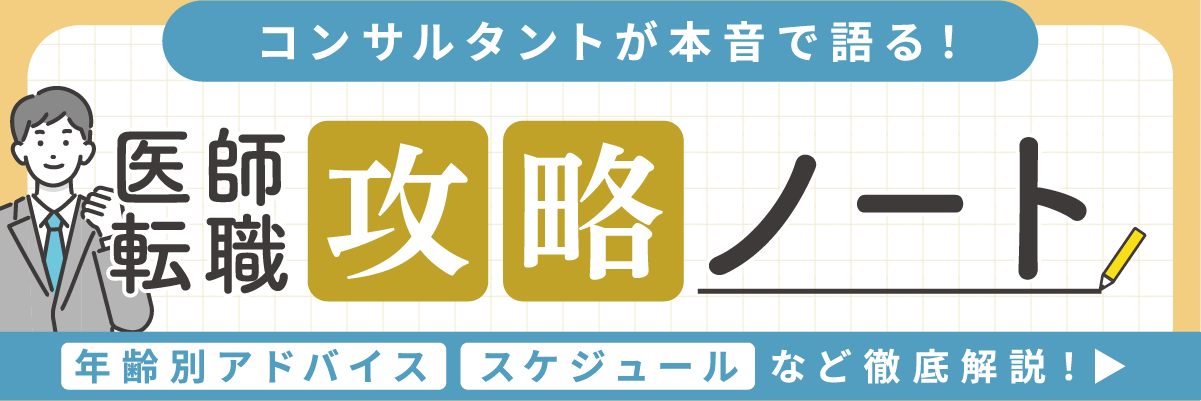日本政府は少子化対策の一つとして、2026年度からの「出産費用の無償化」を検討しています。無償化にする方法としては、今まで自由診療であった出産を保険適用とすることが提案されています。
これから出産を予定している家庭にはメリットがありそうに聞こえますが、出産に携わる医療者や医療機関からは、不安の声も挙がっています。この記事では出産費用の無償化(以下、出産無償化)に関して、本稿執筆時点で考えられるメリットやデメリットを中心に、わかりやすく解説します。

出産無償化が議論されている背景
日本の少子化は年々進行しており、2024年の合計特殊出生率は1.15と、前年の1.20からさらに低下し*1、過去最低となりました。
政府は出産や育児に関する経済的負担を減らすことが少子化対策になると考え、2026年度から「出産無償化」を実現するため、関連学会など各方面と議論を進めています。
出産費用の経済的負担を減らす施策は、これが初めてではありません。健康保険における分娩費・助産費の支給は1927年から始まり、1994年には「出産育児一時金」が創設されました。2023年4月には13年ぶりに金額が見直され、42万円から50万円に増額されています。
しかし昨今の物価高や人件費上昇の影響で、出産育児一時金だけでは出産費用をカバーできず、自己負担でまかなっている人が多いことが、2022年のNPO団体の調査で明らかになっています*2。2022年に48.2万円だった出産費用(全国の正常分娩の平均値)は、2023年には50.7万円、2024年上半期には51.8万円まで上昇しており*3、この傾向はより高まっていると推測できます。
出産費用が原則無料となれば、経済的な理由で出産をためらう家庭を支援でき、出生率の上昇につながるのではないかと期待されています。
令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省(*1)
出産育児一時金等について|厚生労働省
医療保険制度における出産の取扱いの歴史的変遷|厚生労働省 第5回妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(2024年11月)
「妊娠・出産の無償化」と国際水準の「継続ケア」の実現を|厚生労働省 第3回妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(2024年8月)(*2)
議論の整理|厚生労働省 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(2025年5月)(*3)
「こども未来戦略」~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~(令和5年12月22日閣議決定)|こども家庭庁
出産無償化はいつから?―実現する場合の流れ・方法
政府は進行する少子化を懸念し、2023年12月に「子ども未来戦略」をとりまとめ、出産無償化(出産費用の保険適用の導入)を含む、出産に関する支援のさらなる強化について検討を進めてきました。
そして2024年6月の「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」設置をきっかけに議論が盛んになり、世間からも注目されるようになりました。主に以下の4点が論点とされてきました。
- 周産期医療提供体制の確保について
- 出産に係る妊婦の経済的負担の軽減について
- 希望に応じた出産を行うための環境整備について
- 妊産期、産前・産後に関する支援策等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001350033.pdf(2025年10月21日閲覧)
多様な観点で議論ができるよう、検討会には医療関係者や自治体の関係者、有識者等だけでなく、被保険者の立場の人や、妊産婦の当事者など、多くの人が招かれました。
そのとりまとめ資料が2025年5月に公表され、政府は引き続き制度化に必要な議論を深めながら、2026(令和7)年度からの出産無償化の施行を目指すとしています。
出産無償化に向けて政府が検討している方法は、正常分娩に対する費用を保険適用とし、出産育児一時金のさらなる増額をするというものです。しかし出産費用が年々上昇している状況下で、一時金の増額では限界があると考えられるため、3割負担部分を助成するなどの方策を検討すべきという意見も出ています。今後、具体的な制度設計に関する情報が示されると予想されます。
出産無償化のメリット

出産無償化のメリットとして考えられるのは、出産家庭の自己負担額の減少です。出産育児一時金が50万円に増額された2023年4月以降、出産費用が一時金の金額を超過した分娩は全体の45%にのぼることがわかりました。超過額が5万円以下の分娩は全体の20%、5~10万円は全体の12%、10万円以上は全体の13%でした*3。出産無償化になればこれらの自己負担がなくなるため、出産の経済的負担が軽減することは明らかでしょう。
一方で、帝王切開や、東京都以外の地域における出産費用は、現在の出産育児一時金でカバーできている、あるいは下回るケースもあり、出産無償化によってメリットがあるとは言えないという意見もあります。たとえば、東京都における出産費用の平均が62.5万円なのに対し、熊本県は38.9万円です*3。つまり熊本県における出産は、現在の出産育児一時金(50万円)でカバーできていることがわかります。今まで一時金で出産費用をカバーできていた地域の人にとっては、出産無償化による経済的なメリットを感じにくいかもしれません。
ただし、出産をする地域によって金額の差が出ていることで、不公平感を生むという意見もあり、保険で全額カバーされるようになることで、どこで出産しても自己負担額が一律無償になるため、不公平感がなくなるというメリットがあります。
出産無償化のデメリット
まずは、出産する家庭側のデメリットを考えてみましょう。無償化の範囲についてはまだ議論が進められていますが、仮に正常分娩の費用が無償になったとしても、無痛分娩に必要な費用や個室代、お祝い膳などの費用は無償化の対象とならない可能性があります。これらは自己負担となるかもしれません。
助成金でどれくらいカバーできるかによって、先述のとおり自己負担額が減らない、または増える場合もあります。
医療機関側のデメリットはどうでしょうか。とくに小規模な産院は分娩数や患者数が少なく、診療報酬による収益は病院経営に大きく影響します。日本産婦人科医会が分娩を扱う785施設を対象に2024年に実施した調査によると、正常分娩が保険適用となった場合に「分娩の取り扱いを止める」または「制度内容により中止を考える」と回答した医療機関は、あわせて486施設にのぼりました*3。
分娩を扱う病院・診療所は年々減少傾向にあり、1996年は病院が1,720施設、診療所が2,271施設ありましたが、2023年には病院886施設、診療所880施設にまで減少しています*3。
こうした現状をふまえると、出産無償化によって出産を扱う施設がさらに減少するおそれがあると言えるのではないでしょうか。
日本は、周産期死亡率が低いことで有名です。小規模の産院が多数あり、リスクの高い出産や出産後のトラブルなどは、周産期医療センターのような大規模な医療機関が担う体制となっています。2023年の出生は、54.3%を病院が担い、45.1%を診療所、0.5%を助産所が担っています*3。また、2024年の調査では病院と診療所の分娩のうち、47%を産科診療所、25%を一般病院、18%を地域周産期母子医療センター、10%を総合周産期母子医療センターが担っており、医療機関の間で機能分化と連携がとられていることが明らかになりました*3。
もし出産無償化によって地域の小規模な産院が潰れてしまったら、出産のために遠方まで出かけなくてはいけない人が増え、世界一安全と言われている日本のお産の安全が脅かされるという指摘も出ています(後述)。
また、今までは妊産婦本人や家族の希望が反映されるお産も可能でしたが、出産後は早めに退院してもらうような"最低限のお産"を余儀なくされる医療機関が増える可能性もあるでしょう。
出産無償化の財源として、増税や社会保険料の負担増につながる可能性もあるため、現役世代の負担が増すこともデメリットと言えるでしょう。
出産無償化に対する意見

日本産婦人科医会
日本産婦人科医会は、出産費用の自己負担が減ることには賛成の姿勢を示しつつも、正常分娩の保険適用には反対しています。
また、もし正常分娩を保険適用とする場合には、いくつかの解決すべき課題があるとしています。
①保険適用の範囲と運用等によってはかえって妊婦の自己負担が増す可能性があること
②妊娠、出産、産後を通して、自費診療で行われている医療や保険サービスなどの取り扱いが不明で、それらが提供できなくなる可能性があること
③全国一律の分娩費用になることで、地域によっては分娩取扱施設の運営が困難になり、医療提供体制に支障をきたす懸念があること
https://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/2ccf0c03d3a82487d9b083513447366e.pdf(2025年10月21日閲覧)
こうした背景から、日本産婦人科医会は小規模の産院が減り日本の産科医療の体制が脅かされることを懸念し、2024年8月時点で正常分娩の保険適用を「産科医療機関の減少に拍車をかける施策」*4と述べています。
出産費用の保険適用化検討に対する本会の見解について(令和5年4月7日日産婦医会発第283号通知)|日本産婦人科医会
「正常分娩」の保険化に対する日本産婦人科医会の考え方|厚生労働省 第2回妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(2024年8月)(*4)
埼玉県産婦人科医会
埼玉県産婦人科医会も、正常分娩の保険適用に強く反対しています。分娩費用を保険適用とすれば、医療機関の収益が減少し、サービスの質や医療安全への影響、さらには分娩からの撤退が加速すると予想しています。
地域の分娩施設が減ることで、高次医療機関に患者さんが集中することになり、医師や看護師・助産師など医療スタッフの過剰労働や、医療体制の崩壊につながる危険もあるとして、「分娩費用の保険適用ではなく、保険財源以外の新たな公的助成を拡充し、保険財源以外の新たな公的助成を拡充し、妊婦の経済的負担を軽減すること」*5などを提言しています。
ドクタービジョン+は、医師転職支援サービス「ドクタービジョン」の情報発信を担うメディアです。「ドクタービジョン」は、医師だけでなく、薬剤師や看護師など医療従事者の転職を支援する、『地域を支える医療系総合コンサルタント』として皆さまをご支援しています。
「出産費用の無償化」などの医師を取り巻く環境の変化を受けてこれからの働き方を考えたときに、「転職」という選択肢が出てくることも少なくないと思います。そうしたときこそ、求職者の皆さま一人ひとりとしっかり向き合うことを大切にするドクタービジョンにご相談ください。アンケートに留まらず、お電話や対面での面談の場合は、お話を通してご経験やご意向を把握した上で、一緒にキャリアプランを考えていきたいと考えています。
まとめ

少子化対策の一つとして、2026年度からの「出産無償化」が検討されています。しかし、正常分娩が保険適用となることで、患者さんの自己負担額が増えたり、医療機関の負担が増し周産期医療の体制に影響を及ぼしたりする可能性もあるため、政府には慎重な議論と判断が求められています。
臨床の現場で妊産婦を支えている医師や医療者・医療機関の意見をふまえ、安全な出産と自己負担削減のバランスが取れる施策実現が望まれています。今後の動向にも注目しましょう。