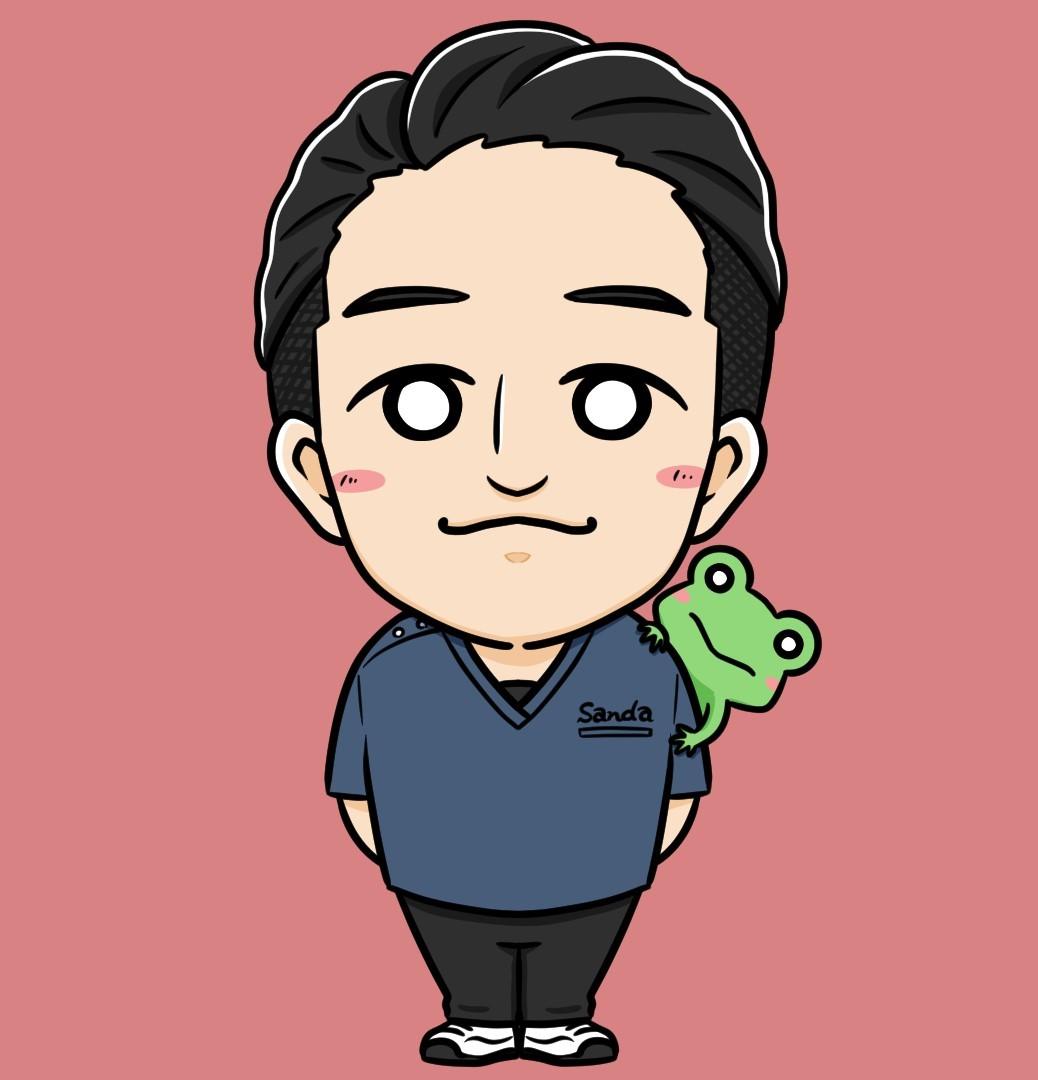日本の多くの地域で高齢化が進む中、住民一人ひとりの健康を支える医療のあり方が問われています。そうした中で注目されているのが、地域に深く根ざし、急性期病院とは異なる役割を担う「コミュニティホスピタル」です。外来・入院から在宅医療まで切れ目のない医療を提供し、地域包括ケアシステムの要として期待される病院です。
この記事では、コミュニティホスピタルとはどんな病院なのか、定義や役割、医師として働く場合のメリットや注意点について、実例を交えながら解説します。
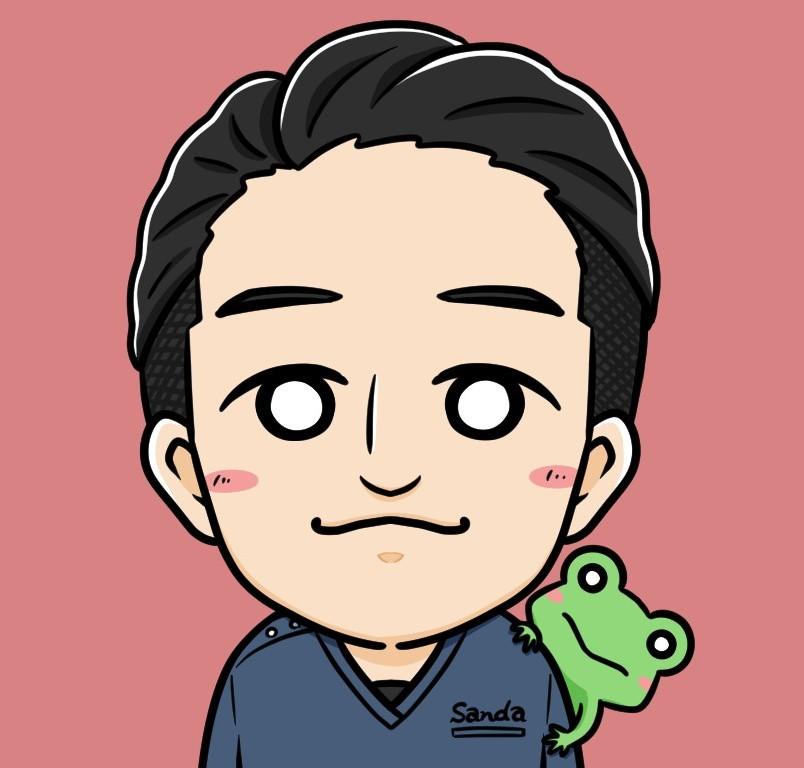
執筆者:三田 大介
コミュニティホスピタルとは
「コミュニティホスピタル」とは、一般的には総合診療を中心に、高度急性期以外の医療(急性期、回復期・慢性期、在宅)を切れ目なく提供することを目指す病院の総称です。決まった定義はありませんが、学術団体「Community Hospital Japan」では「外来、病棟、在宅医療をシームレスに提供する概ね200床未満の病院」*1と定義しています。
また、コミュニティホスピタルの経営支援や人材育成を行う一般社団法人「コミュニティ&コミュニティホスピタル協会」は、「総合診療を軸に超急性期以外のすべての医療、リハビリ、栄養管理、介護などのケアをワンストップで提供する病院」*2と述べています。
これらの定義からわかるように、コミュニティホスピタルは大規模で専門的な病院というよりも、地域住民にとって身近な病院という特徴があると言えるでしょう。
コミュニティホスピタルが注目される背景

コミュニティホスピタルはなぜ今、注目されているのでしょうか。背景には、日本の医療が直面する課題と、それに対応するための国の政策(地域医療構想)があります。
日本は世界でも有数の超高齢社会を迎えています。高齢者の健康には複数の疾患がかかわることが多く、身体的な側面だけでなく精神的・社会的な側面も加味する必要があります。医療においても疾患の治療だけでなく、リハビリテーションや栄養療法、介護サービスの調整などが求められるなど、医療に対する需要は量と質の両面で変化していると言えます。
対して、生産年齢人口の減少により医療の担い手は減少していくために、医療の供給をどう維持するかが課題です。
地域医療構想との関連
人口動態や医療需要の変化は、地域によっても事情が異なります。各地域の実情に合わせて医療体制を整備するため、国が進めている取り組みが「地域医療構想」です。医療を持続的かつ効率的に提供するため、各医療機関の役割を明確にし、地域内で連携を強化することを目指しています。
病床の役割(病床機能区分)は、これまで「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4つに分けられてきました。しかし昨今の日本の抱える問題から、2040年に向けた「新たな地域医療構想」では、「医療機関機能」として以下の3つの側面も考えられています。
- 高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能
- 在宅医療を提供し、地域の生活を支える機能
- 救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001309842.pdf(2025年4月22日閲覧)
在宅医療については、全国の328の二次医療圏のうち「2020年から2040年にかけて需要が50%以上増加する」と予測される医療圏が66もありました。一方で「減少する」と予測される二次医療圏はわずか23しかなく*3、こうした需要に応じた医療体制の整備が求められます。
地域医療構想|厚生労働省
地域医療構想の概要|厚生労働省
新たな地域医療構想について|厚生労働省 第9回新たな地域医療構想等に関する検討会(2024年9月)
新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について|厚生労働省 第7回新たな地域医療構想等に関する検討会(2024年8月)(*3)
「新たな地域医療構想等に関する検討会」のとりまとめを公表します|厚生労働省
▼関連記事はこちら
「地域医療構想」とは?概要や策定経緯、2040年に向けた新たな取り組みを解説
コミュニティホスピタルの役割
こうした背景をふまえ、これからの地域医療においてコミュニティホスピタルには、具体的にどのような役割が期待されているのでしょうか。
主な役割として、「シームレスな医療の提供」と「多職種連携・地域連携の推進」が挙げられます。
シームレスな医療の提供
コミュニティホスピタルは、先述の「地域ごとに求められる医療提供機能」のうち、以下2つの機能を担う病院であると言えます。
- 高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能
- 在宅医療を提供し、地域の生活を支える機能
これは、一つの施設で急性期の加療を行うことができるほか、リハビリテーションによる在宅復帰の支援、退院後の訪問診療や看取りまで、途切れのない医療を提供することを意味します。
多職種連携・地域連携の推進
多領域にまたがる複数の疾患を持ち、ときに社会的な背景も複雑にかかわる高齢者診療では、多職種の介入は必須と言えます。
また、コミュニティホスピタルでは総合診療という側面から患者さんの診療を行いますが、ときには専門的な加療が必要になることもあるでしょう。つまり地域の高度医療機関との連携も必須となります。
さらに、退院後の患者さんの生活を支えるためには、訪問看護ステーションや歯科医療機関、通所・訪問リハビリテーションなど、院外の多様な施設との連携も欠かせません。コミュニティホスピタルは、その連携の起点となることが求められます。
病診連携とは?地域連携との関連、取り組みの実例や今後の展望【現役医師解説】
チーム医療で医師が大切にすべきこととは。各職種の役割や多職種連携のメリットを解説
タスク・シフト/シェアとは?医師の働き方改革に向けた医療現場の変化【現役医師解説】
コミュニティホスピタルの業務・活動
ここからは、コミュニティホスピタルで行われていることについて、「総合診療」「リハビリテーション」「教育」「地域活動」の4つの側面から、具体的に見ていきましょう。
1.総合診療―外来・入院・在宅
総合診療と聞くと「診断に難渋する症例に対して、診断をつけて専門家につなぐ」という役割を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし総合診療はそれ以外にも、複数の疾患や課題を持つ症例、心理的要因や社会的要因を含む症例の診療も得意とする分野です。
外来ではプライマリ・ケア医として地域住民の窓口に、入院では主治医として多職種連携の要になります。訪問診療では患者さんの「生活」を支え、ときに看取りを担うこともあります。
医師のための「患者の看取りの在り方」【令和版】
2.リハビリテーション機能の強化
高齢の患者さんにおいては、日常生活に介助が必要なケースが少なくありません。コミュニティホスピタルでは、途切れのないリハビリテーションを集中的に提供することが可能です。退院後も地域連携を通して、訪問・通所リハビリテーションを提供することができます。
3.教育
地域で持続的に医療を提供するには、人材の育成が必須です。医師については、2018年に新専門医制度の基本領域に加わった「総合診療専門医」の資格が重視されています。全国の総合診療科などを基幹施設として日本専門医機構のプログラムが整備されており、コミュニティ&コミュニティホスピタル協会も総合診療専門医の育成プログラムを所持しています。
シームレスな医療を提供するには、コメディカルの育成も重要です。コメディカル自身にとっても、一つの病院内で幅広いステージを経験できるメリットがあり、地域医療への貢献度が高まるでしょう。自治体と連携している病院の中には、医療系専門学校との連携や、一定の経験を持つコメディカルがさらにスキルアップを目指せるプログラムを展開しているところもあります。
一般のみなさまへ 総合診療について|日本病院総合診療医学会
総合診療領域 専門研修プログラム一覧|日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会
コミュニティホスピタル総合診療プログラム|コミュニティ&コミュニティホスピタル協会
4.地域活動
地域での生活を支えるコミュニティホスピタルでは、疾患の知識を提供する講演会や勉強会、地域住民の健康相談など、医療に関する活動だけでなく、医療以外の交流も大切にしています。中には地元の飲食店と協力したり、病院長が交流の場に足を運んだりする病院もあるなど、さまざまな取り組みが見られます。
こうした活動や場の提供により、地域住民からの信頼を得るだけでなく、医療需要の発掘や健康意識の向上も期待できます。
コミュニティホスピタルで勤務するということ

ここからは、医師がコミュニティホスピタルで勤務する場合の働き方、キャリアについて考えていきましょう。
コミュニティホスピタルの魅力
コミュニティホスピタルでの勤務には、大規模病院とは異なる魅力があります。
急性期病院では近年、在院日数の短縮化が進み、一般病床の平均在院日数は、2007年には19.0日だったのが、2023年には15.7日になっています*4,5。「もっと患者さんを自分で診たかった」と感じる機会が増えている人もいるのではないでしょうか。
コミュニティホスピタルでは、急性期から回復期、さらには退院後の訪問診療まで、より長い期間で患者さんを診療できます。
また、総合診療という臓器横断的な診療ができるようになるということは、今後ますます高齢者診療の重要性が増していく中で、医師として大きな強みになるでしょう。多職種連携によるチーム医療、医療機関の枠を超えた活動など、地域の需要に応じた医療を提供できることは、大きなやりがいになり得ます。
平成19(2007)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況|厚生労働省(*4)
└Ⅱ-3 平均在院日数
令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況|厚生労働省(*5)└p.26 平均在院日数
コミュニティホスピタル勤務の注意点
一方で、いくつか考慮すべき点もあります。まず、コミュニティホスピタルを掲げている病院が、専門医養成をしているとは限らない点です。
たとえばコミュニティ&コミュニティホスピタル協会の総合診療専門医育成プログラムは一部地域での展開であり、地域によってはアクセスが限られます。専門医資格の取得を目指したい場合は、勤務したい地域で総合診療専門研修プログラム(専門医制度)を受講できるのか、確認する必要があります。
総合診療専門医に限らず、日本病院会や日本病院総合診療医学会が認定する「病院総合医」のプログラムもコミュニティホスピタルでの業務と親和性が高いため、有力な選択肢になるでしょう。
また、コミュニティホスピタルの役割を考えると、専門に特化した高度医療や超急性期医療の修練は難しいと言わざるを得ません。比較的小規模な病院が多いため、大規模病院を志向する医師には適さない可能性があるでしょう。
地域に根差した医療を提供する病院が、必ずしも「コミュニティホスピタル」という名称を掲げているとは限りません。急性期病院とは違った形で、地域を支えるさまざまな病院に目を向けることで、より広い視野で診療に臨むことができるでしょう。
総合診療医のキャリアは?メリット・デメリットも解説
新専門医制度、総合診療医を希望する場合にはサブスペシャルティの取得は必須?
総合診療医の年収は?専門医取得後のキャリアパスについても解説
「病院総合医」(ホスピタリスト)とは?役割や専門医資格などを解説
まとめ
高齢化し続ける日本の医療を維持していくために、コミュニティホスピタルにはシームレスな医療、多職種連携、地域住民との交流活動など、重要な役割が期待されています。総合診療や地域医療に興味のある方、専門特化の医療とは違う道に興味を持った方は、ぜひコミュニティホスピタルにも注目してみてはいかがでしょうか。