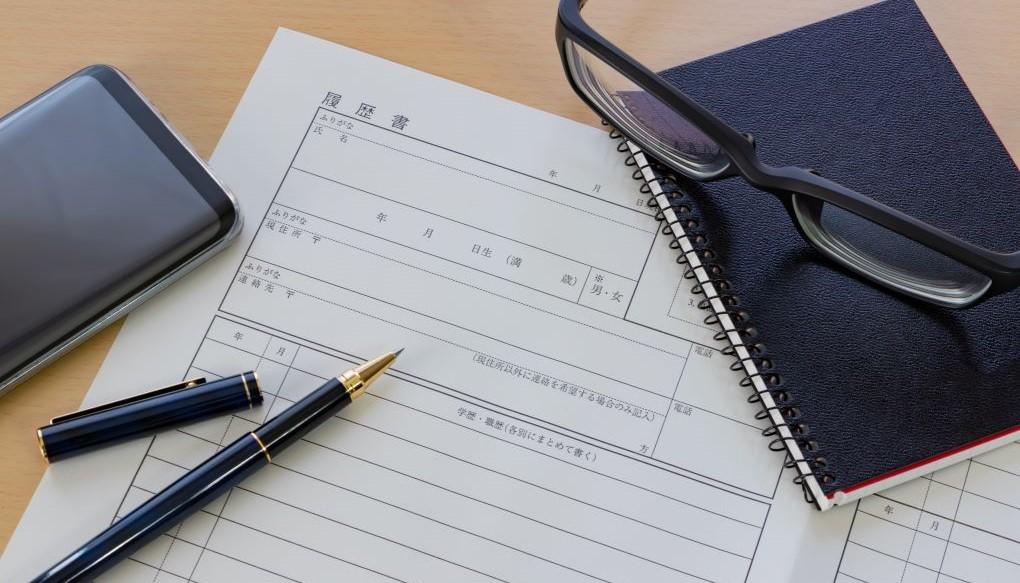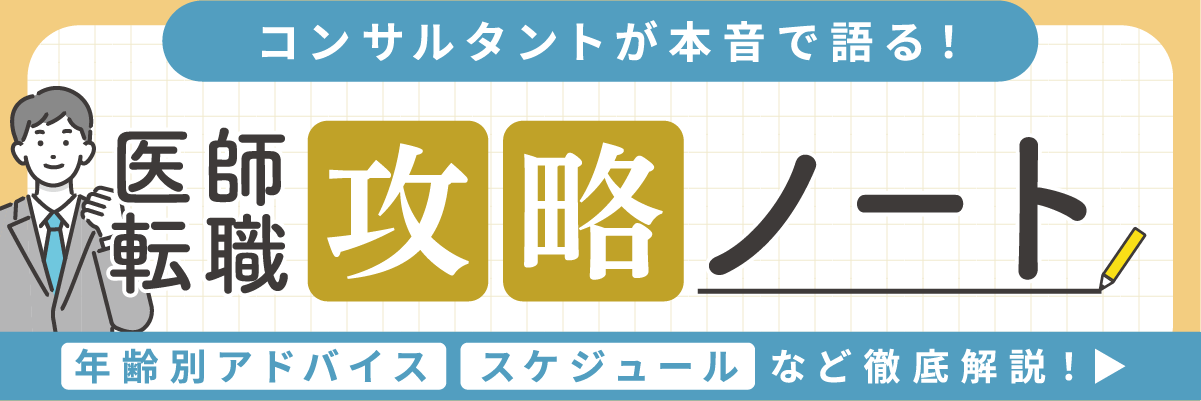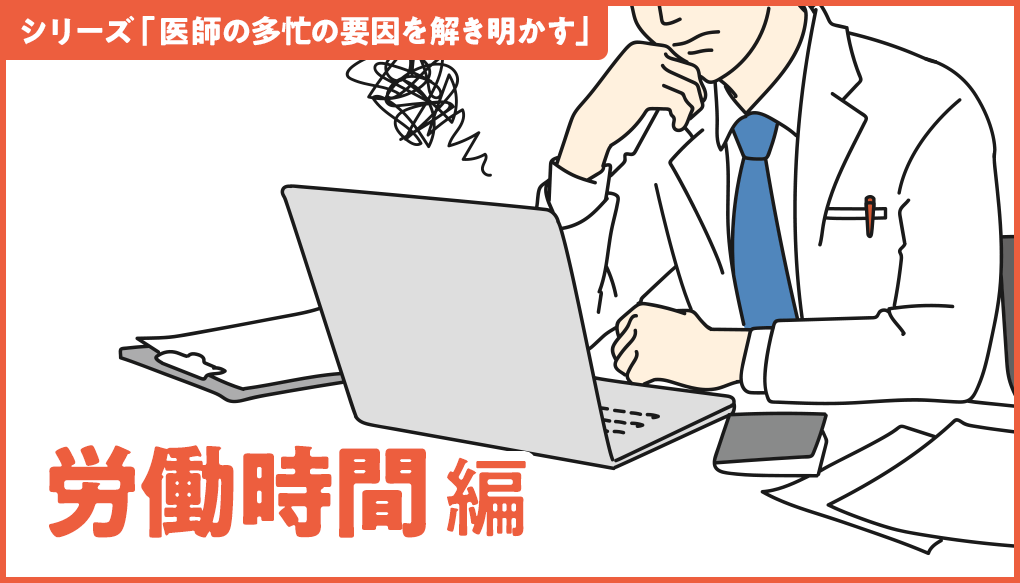医師の転職では職務経歴書の他、自己PRも合否を左右する要素の1つです。どんなに経歴が素晴らしくてもそれを上手くアピールできなければ意味がありません。だからこそ採用担当者の心に響く内容が書けているか、応募する前に確認しておくことが重要です。
とはいえ、患者さまの対応や診療スキルなど、日常の業務で当たり前にこなしていることをどのようにアピールすべきか迷ってしまう先生もいるのではないでしょうか。「自分の強みが特別なものではない気がする」と不安になる先生もいるかもしれません。
そこで本記事では、例文つきで「医師が採用担当者に印象を残すための自己PRの作り方」を解説します。「良い例文と悪い例文」や「採用担当者が重視しているポイント」も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
自己PRは医師が自分自身を医療機関にアピールするための重要な項目

自己PRは単なる自己紹介ではなく、採用担当者に「この先生に来てほしい」と感じさせる重要なアピール要素です。職歴やスキルはもちろん、そこにどんな姿勢や強みがあるのかを伝えることで、医療機関との相性を判断してもらう材料になります。
経歴が似ている候補者が複数いた場合、自己PRの中身で評価がわかれる場合もあるため、丁寧に準備しておきたい項目です。
そんな自己PRについて、まずは以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- 自己PRは構成が大切
- 職歴からはわからない内容である
- 転職後に活かせる能力である
自己PRは構成が大切
自己PRを書くときは、構成を意識するだけで伝わりやすさが大きく変わります。以下のような構成を意識してみましょう。
- 結論→根拠→成果
- 課題→工夫→結果
上記のように筋道の通った構成で書かれていると、読み手の理解も深まります。漠然と結論だけ伝えるよりも、どんな場面でどのように取り組んだのかを順序立てて説明する方が、説得力のある内容になります。
中でも使いやすいのが、PREP法です。PREP法とは説明の構成を表したモデルであり、「Point(結論・主張)」「Reason(結論にいたった理由、主張の理由)」「Example(理由に説得力を持たせるための事例やデータ)」「Point(結論・主張)」の流れで書いていきます。例えば、以下のような文になります。
Point(結論):
私は患者さまの最善の治療を実現するため、多職種連携を重視したチーム医療の実践を最も大切にしています。
Reason(理由):
医療の高度化・複雑化により、一人の医師だけでは患者さまのすべてのニーズに対応することは困難になっているためです。看護師、薬剤師、理学療法士など各専門職の知識と経験を結集することで、より質の高い医療を提供できると確信しています。
Example(具体例):
前職の総合病院では、糖尿病患者さまの治療において、医師・看護師・栄養士・薬剤師からなるチームを立ち上げました。定期的なカンファレンスを通じて情報共有を徹底し、患者さま一人ひとりに最適化された治療プランを作成しました。その結果、HbA1c平均値を6か月で1.2%改善させることができ、患者さまの満足度も向上しました。
Point(結論の再確認):
貴院でもチーム医療を通じて、患者さまにより良い医療の提供に貢献したいと考えています。
上記のような形で自己PRを書くことで、採用担当者に自分の魅力をわかりやすく伝えられます。
職歴からはわからない内容をPRする
転職において医師の職歴は非常に重要ですが、単に所属施設や診療科目を並べただけでは、具体的な人物像は伝わりにくいものです。そのため、自己PRでは以下のような内容を盛り込みましょう。
- 勤務場所や部署、業務の中でどのような役割を担っていたか
- 日々の業務の中で何を工夫していたか
こうした情報は、書類からは見えません。補足する意識で記載しておくことで、採用側が知りたい履歴書に書かれていない部分を伝えられるでしょう。例えば、以下の文の具体例に当たる部分が参考になります。
Point(結論):
私は患者さまとの信頼関係構築を最優先とし、丁寧なコミュニケーションを通じて患者さま中心の医療を実践することを強みとしています。
Reason(理由):
医療は患者さまの協力なしには成り立たちません。治療効果を最大化するためには患者さまが治療内容を十分理解し、納得して取り組むことが重要だからです。また、患者さまの不安や疑問を解消することで、より良い治療環境を作ることができると考えています。
Example(具体例):
内科外来で勤務していた際、糖尿病を抱える高齢の患者さまに対して、専門用語を避けて食事や運動療法の必要性を説明し、生活習慣の改善を図るサポートを行いました。食事制限の理由や血糖コントロールの仕組みを図にまとめて提示し、日常生活の中で実践できる工夫を一緒に考えることで、患者さまから「生活に取り入れやすい」「安心して治療に取り組める」と評価いただき、実際に数カ月後にはHbA1cの改善も見られました。
Point(結論の再確認):
今後も患者さまとの対話を大切にし、信頼関係に基づいた質の高い医療を提供していきたいと考えています。
例文を読むとわかるように、職歴からはわからない内容を盛り込んでいます。自分が取り組んだ工夫と併せて患者さまからの評価を記載することで、説得力のある自己PRとなっています。
このように、具体的な内容が伝わるかどうかを意識して書いていきましょう。
転職後に活かせる能力であること
自己PRで評価されるのは、過去の実績だけではありません。転職後にどう活かせるのか、どんな貢献ができそうかを見据えた内容が好印象につながります。
例えば「チーム医療に慣れている」「多職種連携の経験がある」といった点を、これからの職場でも活かせる形で伝えると、即戦力としての印象を持ってもらいやすくなります。自己PRを単なる経験にするのではなく、この能力があれば転職先の課題を解決できると伝わる内容にしましょう。
特に意識しておきたいのが、働きたい医療機関に合わせているかどうかです。どれだけ魅力的な人材であっても、その医療機関が求めていない人材では、採用される確率は大きく下がります。求める人材に合致していると判断してもらえるように、自己PRは働きたい医療機関に合わせて考えるようにしましょう。
【例文つき】自己PRを書く際に意識したいポイント

自己PRを書く際は、意識したいポイントがあります。どのようなポイントを意識すれば良いのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- アピールには根拠をセットにして説得力を持たせる
- 具体的な表現方法を使う
- 医療機関が求めている医師像を意識する
- 経歴を羅列しない
アピールには根拠をセットにして説得力を持たせる
自己PRを書く際は、強みをただ並べるのではなく、なぜそう言えるのかという根拠を示せるかが重要です。「患者さまへの対応を大切にしている」と書く場合は、実際に患者さまから感謝されたエピソードを添えると具体性が増します。例えば、以下のような形です。
悪い例:根拠がなく分かりにくい
私は患者さまのことを第一に考えます。医師として大切なことは、患者さまに寄り添うことだと思います。私はいつも患者さまの立場に立って考えるようにしています。患者さまが安心できるような医療を提供したいです。そのために日々努力しています。医師という仕事は責任が重いですが、やりがいがあります。今後も患者さまのために頑張りたいと思います。
良い例:根拠に具体性があり説得力がある
患者さまとの信頼関係を大切にし、医療チームの一員としてスタッフと連携しながら診療に取り組むことを意識してきました。患者さまが安心して治療に向き合うためには、症状だけでなく生活背景に配慮した支援や、チームで一貫した対応を行うことが不可欠だと考えています。
実際に、定期的に通院されている糖尿病の患者さまに対し、管理栄養士や看護師と協力しながら食事や運動、服薬管理の生活指導を継続したところ、血糖コントロールが改善し、主治医からの評価や患者さまからの感謝の言葉をいただくことができました。こうした経験を通じて、丁寧な対応とスタッフ連携が診療の質向上や大きなやりがいにつながることを強く実感しています。
具体的な表現方法を使う
自己PRでは、抽象的な表現だけでは相手にあなたの強みが伝わりにくく、印象にも残りません。数字やエピソードを交えて「どのような環境で、どのような行動を取り、どんな成果があったのか」を示すことで、採用担当者が具体的にイメージしやすくなります。
以下の例を比較してみましょう。
悪い例:抽象的で説得力に欠けている
私は多くの患者さまと接する中で、丁寧な対応を心がけてきました。患者さまの気持ちに寄り添い、親身になって診療を行うよう努めています。その結果、患者さまからは良い評価をいただいており、信頼していただけているのではないかと思います。今後も可能な限り患者さまに満足していただけるような医療を提供していきたいと考えています。
良い例:具体性がありイメージしやすい
1日50人以上の外来対応がある中でも、限られた時間の中で患者さま一人ひとりに丁寧に向き合うことを大切にしてきました。患者さまが安心して診療を受けられるためには、不安や症状をしっかり受け止めるだけでなく、看護師や受付スタッフと連携し、スムーズな診療体制を整えることが欠かせないと考えています。
実際に、スタッフと協力して診療の流れを調整した結果、「親身に話を聞いてくれる」といった評価を多くいただき、患者さまからの信頼や満足度が高まりました。こうした取り組みにより、継続受診や新たな患者さまのご紹介にもつながり、チーム全体として業務効率と患者満足度の両立を実現できたと実感しています。
応募先の医療機関が求めている医師像を意識する
どの医療機関にも、求める人物像があります。そのため、自己PRの内容は使い回すのではなく、応募する医療機関に合わせて変えていかなければいけません。例えば、地域密着型のクリニックへ応募する場合、以下のような乖離が生じないようにしましょう。
悪い例:目線が一方的で、現場ニーズとズレている
私は○○専門医として、この地域でも自分の専門知識を活かした医療を提供したいと考えています。大学病院で培った最新の知識や技術を地域の患者さまにもお届けすることで、より良い医療を受けていただけるのではないでしょうか。地域の皆様にはまだ馴染みのない治療法もあるかもしれませんが、丁寧に説明して理解していただき、最適な医療を提供していきたいと思います。私の専門分野については、大学病院レベルの診療が可能ですので、患者さまにとってメリットは大きいと考えています。
良い例:現場の視点を理解したうえで、貢献姿勢をアピールできている
患者さまとの信頼関係を築くことを何よりも大切にしています。患者さまが安心して治療に取り組むためには、症状や検査データだけでなく、生活背景やお気持ちにも丁寧に耳を傾けることが不可欠だと考えているからです。
実際に、看護師やコメディカルスタッフと情報を共有し、診療方針や生活指導の一貫性を保つよう努めることで、チーム全体で患者さまを支える体制を整えてきました。その結果、患者さまの信頼が深まり、継続的な受診や前向きな治療意欲にもつながり、診療全体の質向上にも寄与できていると実感しています。
経歴は具体的な取り組みや成果とセットで伝える
自己PRでは、経歴の羅列も注意したいポイントです。ただ単に経歴が並んでいるだけでは、印象に残りません。具体的な取り組みを加えて、実際の貢献度や姿勢が伝わる内容にしましょう。例えば、以下のような形です。
悪い例:経歴の羅列だけで、人物像や強みが伝わらない
○○大学医学部を卒業後、△△病院で初期研修を行いました。その後、××大学病院内科に入局し、3年間勤務しました。□□病院では2年間、消化器内科医として働きました。◇◇クリニックでは1年半、外来診療を担当しました。現在は▽▽病院の内科で勤務しています。これまで合計8年間の臨床経験があります。○○学会の認定医資格も取得しています。学会発表は5回、論文発表は3本あります。
良い例:具体的な経験と成果が示され、人物像や貢献度が伝わる
○○病院での5年間の勤務を通じて、内科外来や病棟業務を幅広く経験し、慢性疾患管理や退院支援のスキルを磨いてきました。特に、患者さまが安心して自宅療養に移行できるためには、多職種で連携した退院計画の立案が重要だと考えています。
実際に、看護師や薬剤師、理学療法士、ソーシャルワーカーと定期的にカンファレンスを行い、患者さま一人ひとりに合わせた退院支援を実践した結果、退院後30日以内の再入院率を従来の15%から8%まで減少させることができました。これにより、患者さまやご家族から「安心して自宅で過ごせる」との評価をいただき、チーム医療がもたらす成果とやりがいを強く実感しました。
自己PRを書く際のポイントまとめ
自己PRでは、抽象的な表現や経歴の羅列だけでは、採用担当者にあなたの人物像や強みが伝わりにくくなります。良い印象を与えるためには、「根拠となる具体的なエピソード」や「成果につながった行動」をセットで示すことが重要です。
また、応募先の医療機関が求める人物像や診療方針を意識し、内容を適切にカスタマイズすることも欠かせません。 「どんな環境で何をしてきたのか」「どう貢献できるのか」がイメージできるように書くことで、採用担当者に「一緒に働く姿」が鮮明に浮かび、評価される可能性が高まります。
これらを踏まえて、経験や強みを整理し、採用担当者に伝わる形に仕上げていきましょう。
面接で自己PRをする時に意識したいポイント

書類での自己PRと、面接での自己PRは伝え方のニュアンスが異なります。面接では、原稿を読み上げるように言うのではなく、自分の言葉で話すように意識しましょう。背伸びをせず実体験を交えて話すと、誠実さや人柄が伝わりやすくなります。身振り手振りや表情を変えるのも良いでしょう。
特に医師の場合、患者さまとのコミュニケーション力や多職種との連携力を口頭でどう表現するかが、評価につながるポイントの1つです。面接前に鏡を使って練習し、相手がどのように感じるかを客観的に確認する方法もあります。
また、転職コンサルタントを利用している場合は、同席してもらうのも1つの手です。適切にフォローしてくれるため、安心して自己PRができます。
診療科よりも医療機関によって中身を変えよう
自己PRは、外科や内科といった診療科よりも、医療機関によって変えるようにしましょう。医療機関ごとに求める人材は異なるためです。例えば以下のような部分でも、話す内容は大きく異なります。
- 一般外来:初診・再診に応じた問診の工夫、待ち時間の短縮など
- 訪問診療:患者さまのご家族や看護師、ケアマネージャーとの関係構築
それぞれが魅力的に感じるポイントを意識し、医療機関ごとに自己PRを変更していくようにしましょう。事前に医療機関を調べ、どのような方針なのかを知っておくと自己PRを書きやすくなります。
【医師必見】採用担当者が自己PRで重視するポイント

自己PRにおいて採用担当者が重視しているのは「この先生はうちのチームでうまくやっていけるかどうか」です。履歴書に書かれている専門スキルだけでなく、協調性や柔軟性、問題解決力といった面も自己PRから評価されています。
事実、ドクタービジョンのコンサルタントが採用担当者にヒアリングしたところ、以下のポイントが重視されていました。
- 医師としてどのような想いで診察をしているか
- 内部のスタッフに対して、どう対応しているか
- 受けようとしている医療機関に対してどのような想いを持っているか
志望動機はもちろん、人柄も評価の対象なのが見て取れるヒアリング内容です。一定の専門スキルを有していることを前提条件として、その先の人間性や協調性、価値観の一致が重要な判断基準となっていることがわかります。
特に医療現場はチームで動きます。どれだけ優秀な医師でも1人では限界があります。看護師や薬剤師、理学療法士に事務スタッフなど、多くの人との連携なしに質の高い医療は提供できません。そのため、履歴書に書かれている経歴や専門スキルだけでなく、先述した協調性や価値観、コミュニケーション能力といったヒューマンスキルが評価されています。
こうした点から見ても、応募先の特性やニーズを理解し、合致している人柄かどうかは重要な判断材料になるといえます。
【要注意】自己PRでありがちな失敗例:相手に合わないアピールは逆効果
自己PRは自分の強みを伝える重要な場面ですが、その内容が医療機関の求める人材像と合致していなければ、かえってマイナス評価につながる恐れがあります。特に多いのが、「どこでも同じ内容を話してしまう」「相手のニーズを理解せずに一方的にPRをする」といった失敗です。
たとえば、以下のような自己PRは、内容自体に問題はなくても、相手の医療機関の特性によっては響かないケースがあります。
以下の例文を見てみましょう。
私の強みは継続的な学習への取り組みです。循環器内科医として、常に最新の医学知識を患者さまに還元したいと考え、年間20以上の学会・研修会に参加し、英語論文を月10本読む習慣を続けています。この取り組みにより、従来の治療では改善困難だった患者さまに新しいアプローチを提案でき、治療成績向上につながりました。
この内容は学び続ける姿勢としては非常に評価されるものの、もし応募先がチーム医療を重視している病院だった場合、「協調性」や「連携における工夫」といった観点が欠けていると見なされ、アピールとして不十分に映る可能性があります。
また、急性期病院、慢性期病院、クリニック、介護医療院など、医療機関によって求めるスキルや役割は大きく異なります。急性期では専門性や即戦力が重視される一方、クリニックでは患者対応力や柔軟性が重視されることもあります。事前に情報収集を行わず、すべての面接で同じ自己PRをしてしまうと、相手のニーズに合わない" 的外れな印象 "を与えてしまうリスクがあります。
自己PRを成功させるには、応募先がどんな人物を求めているか、どんな価値観を大事にしているかをしっかり理解したうえで、自分の強みと重なる部分を的確に伝えることが重要です。
対面面接とWeb面接における自己PRの伝え方の違い

近年、対面面接だけではなくWeb面接をする医療機関も増えてきました。両者は話す内容そのものは変わらないものの、以下のような点で異なります。
| 面接 形式 |
メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 対面 面接 |
表情や声の抑揚を伝えやすい | 自然な話し方や目線、姿勢にも気を配る必要がある |
| Web 面接 |
場所を選ばず面接ができる | カメラ写りや音声の聞き取りやすさに気を配る必要がある |
対面面接は表情や声の抑揚を伝えやすく、自然な話し方や目線、姿勢にも気を配ると好印象になります。
一方のWeb面接は、場所を選ばずに面接できるメリットはあるものの、カメラ写りや音声の聞き取りやすさには注意が必要です。事前にテストをして、問題ないかを確認した方が良いでしょう。
また、採用担当者が話している最中に被せる形で話してしまうと、傾聴できないと判断される可能性もあります。間をしっかり取るように意識してみてください。
対面とWeb面接については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ確認してください。
自己PRで困ったら「ドクタービジョン」へご相談を
「自分の強みをどう伝えるべきかわからない」
「医療機関ごとに何をアピールすればよいか迷う」
自己PRの作成は、転職活動の中でも特に悩ましいステップのひとつです。
「ドクタービジョン」は、日本調剤グループのメディカルリソースが提供する、医師の求人・転職・募集に特化した専門サイトです。 医療業界に精通したコンサルタントが、これまでのご経験やご希望を丁寧にヒアリングし、応募先に合った自己PRの作成を含めた書類対策や面接準備まで、トータルでサポートいたします。
給与・勤務時間などの聞きにくい条件交渉も代行するため、転職が初めての方も安心です。また、全国に拠点を構えるドクタービジョンでは、コンサルタントが医療機関の実情を自ら確認し、求人票ではわからないリアルな情報もお伝えします。
自己PRの方法にお悩みの方も、キャリアの方向性を整理したい方も、まずは以下のリンクからお気軽にご相談ください。
医師の転職にとって自己PRは大切。相手が魅力的に感じる伝え方を意識しよう

医師の転職において、自己PRは単なる履歴書の項目ではなく、自分自身の価値を伝える大切な部分です。採用側にとっても「どんな先生なのか」「どのような働き方ができるのか」を判断する材料になります。
希望の医療機関に転職を成功させるためにも、自分の強みを整理し、それをどう活かせるかまで伝えられているかは重要です。今回紹介したポイントを参考に、魅力的な自己PRになるよう、根拠や具体性を持たせるようにしてみましょう。
もし自己PRの自信が持てないときは、ドクタービジョンのコンサルタントをご活用ください。経験豊富なコンサルタントが、添削・アドバイスをいたします。無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
1分で登録完了!コンサルタントへの転職相談
「転職について気になることがある」「周りの転職活動の動向を知りたい」など、
まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。