政府が2025年の「骨太の方針」に盛り込んだことで広く話題になったのが、「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し」です。国政の場で議論が進められており、2026年度から医療保険の適用除外となる可能性が、現実味を帯びています。
保険適用から除外となれば、医療費の適正化やセルフメディケーション推進といった政策的意義がある一方、風邪薬や抗アレルギー薬、湿布、保湿剤など、日常診療で処方頻度の高い薬剤が対象となることで、患者さんの受診行動や治療継続に大きな影響を与えかねません。
この記事ではOTC類似薬をめぐる昨今の現状・課題を整理し、医療現場への影響を考察します。
※本稿執筆時点での情報に基づきます。最新の情報・動向もあわせてご確認ください。

執筆者:Dr.SoS
OTC類似薬とは
まずは、「OTC類似薬」とは何かを確認していきましょう。類義語が多いので、混同しないよう注意が必要です。
OTC類似薬の定義と、OTC医薬品との違い

「OTC類似薬」について明文化された定義はありませんが、既存の市販薬(OTC医薬品)と同様の有効成分や効能を持つ医療用医薬品を指す場合が多いです。
ここで「OTC医薬品」とは、いわゆる市販薬(大衆薬)のことを指します。OTCは Over The Counter の略で、薬をカウンター越しに販売することに由来しています。
OTC医薬品には処方箋が不要で、そのうち多くはインターネットなどの非対面でも購入可能です。医師の診察が不要な点から、たとえば抗がん剤のような重大な副作用リスクがある薬品、重篤な症状に対して使用する薬品は、OTC医薬品には向きません。
つまりOTC医薬品は、病態が軽度な疾患の症状緩和・セルフメディケーションを目的とする薬剤と言えるでしょう(セルフメディケーションについては後述)。
OTC類似薬とOTC医薬品の違いを表にまとめました。医師の診察および処方箋の要否、医療保険の適用の有無が、両者の大きな違いであることがわかります。
【OTC類似薬とOTC医薬品の違い】
| OTC類似薬 | OTC医薬品 | |
|---|---|---|
| 効果・副作用 | 作用は穏やかで、重篤な副作用が少ない | |
| 有効成分 | 同一 ※含有量には違いあり |
|
| 医師の診察・診断 | 必要 | 不要 |
| 処方箋 | 原則必要 | 不要 |
| 医療保険 | 適用 | 適用外(自費) |
| 関連する税制 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
| 患者負担 | 低い(〜3割) | 高い(10割) |
OTC医薬品とは?|日本OTC医薬品協会
医薬品のネット販売を安心して利用するために|政府広報オンライン
医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省
OTC類似薬の代表例
OTC類似薬は、以下のようなジャンルが代表的です。
- 風邪薬
- 抗アレルギー薬
- 湿布薬
- 外用薬 など
一日最大容量がOTC医薬品と同程度とされるOTC類似薬もあり、以下がその一例です(2025年4月、社会保障改革に関する3党協議および参議院厚生労働委員会資料より)。
| 有効成分 | OTC類似薬(販売名の例) | OTC医薬品(販売名の例) |
|---|---|---|
| エピナスチン | アレジオン®錠20(日本ベーリンガーインゲルハイム) | アレジオン®20(エスエス製薬) |
| ロキソプロフェン | ロキソニン®錠60 mg(第一三共) | ロキソニン®S(第一三共) |
| カルボシステイン | ムコダイン®錠500 mg(杏林製薬) | ムコダイン®去たん錠Pro500(シオノギヘルスケア) |
| ヘパリン類似物質 | ヒルドイド®クリーム0.3%(マルホ) | ビーソフテン®クリーム(テイコクファルマケア) |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ベトネベート軟膏0.12%(グラクソ・スミスクライン) | リンデロン®Vs軟膏(シオノギヘルスケア) |
OTC類似薬の「保険適用除外」の可能性
なぜOTC類似薬の保険適用除外が話題になるのか?
近年、OTC類似薬は政策上の議題としてたびたび取り上げられてきました。
先述のとおり、OTC類似薬は通常の医療用医薬品と異なる特徴を持っています。また、OTC類似薬とOTC医薬品では医療保険の適用有無が異なるため、医療費や自己負担額もかなり違ってきます。
しかし、OTC類似薬とOTC医薬品は有効成分が同じであり、薬品によっては一日最大容量も同程度です。ほぼ同様の効能・副作用が期待できるにもかかわらず、一方には医療保険が適用され、もう一方は保険適用外で全額自費負担になる状況は、OTC類似薬の問題点の一つとされてきました。
医療保険の適用範囲は、社会全体の医療費増大にも寄与します。日本の医療費は高齢化に伴って増え続けており、削減に向けた取り組みがいっそう重要視されていることは皆さんもご存知のとおりかと思います。
医療費適正化計画とは?―第四期【2024~2029年度】の内容を中心に解説
OTC類似薬の保険適用除外はいつから?
こうした問題点が指摘される中、2025年6月11日、自由民主党・公明党・日本維新の会が、OTC類似薬の保険給付の在り方を見直す方針で合意しました。早ければ2026年度から実施するという内容で、社会保険料の負担低減を主張している日本維新の会からの要望に、ほかの2党が歩み寄った形です。
その2日後(6月13日)、政府が発表した「骨太の方針2025」(経済財政運営と改革の基本方針2025)に、同様の内容が記載されていることが判明したことで、大きな話題となりました。以下のように記載されています。
持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するため、OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し※や、地域フォーミュラリの全国展開、新たな地域医療構想に向けた病床削減、医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現、現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底、がんを含む生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進などの改革について、引き続き行われる社会保障改革に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、2026年度から実行する。
※医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、個別品目に関する対応について適正使用の取組の検討や、セルフメディケーション推進の観点からのさらなる医薬品・検査薬のスイッチOTC化に向けた実効的な方策の検討を含む。
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf(2025年9月4日閲覧)
経済財政運営と改革の基本方針2025|内閣府
OTC類似薬の保険適用除外に伴うメリット
OTC類似薬の保険適用除外には、メリットと懸念点が双方存在します。
まずはメリットについて考えていきましょう。大きく下記の3つが挙げられます。
【OTC類似薬の保険適用除外により想定される主なメリット】
- 国民医療費の削減が期待できる
- 医療資源を有効に活用できる
- 国民のセルフメディケーション意識が高まる
国民医療費の削減が期待できる

国民医療費の削減は、OTC類似薬の保険適用除外でもたらされる最大のメリットと考えられています。先述した2025年4月の社会保障改革に関する3党協議および参議院厚生労働委員会では、保険適用除外に賛成する議員から、OTC類似薬の市場が1兆円に及ぶと説明されています*1。
OTC類似薬は定義が曖昧なため、市場規模の推計が難しく、必ずしも想定どおりに医療費が削減されるわけではないという意見もありますが、相当程度の医療費削減効果が期待できることは間違いないでしょう。
医療資源を有効に活用できる
医療資源の有効活用も、OTC類似薬の保険適用除外に期待されるメリットと言えます。
OTC類似薬のみで治療できる軽症の患者さんが医療機関の受診を控えることで、より重症な疾患を抱える患者さんや、専門性の高い医療に対し、限られた医療資源を投じることができると期待されるためです。
折しも2024年からは「医師の働き方改革」が本格的に始まり、医療DXの推進も加速が目指されているなど、効率的に医療を提供する仕組みづくりが求められている状況ですから、このメリットも見過ごせないでしょう。
国民のセルフメディケーション意識が高まる
OTC類似薬が保険適用除外となることで、患者さんが処方薬をなんとなく使うという"受け身の姿勢"でなく、自身で薬局を受診して必要な薬を選ぶという"主体的な姿勢"が、国民に求められるようになると考えられます。
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)*2は「セルフメディケーション」と呼ばれ、国民の健康管理や疾病予防、医療費適正化の観点から厚生労働省も推進しています。
国民のセルフメディケーション意識が高まれば、食生活に注意したり、適度な運動を実施したりすることで、疾病の一次予防効果も期待できます。ひいては医療費削減にも寄与する可能性があるでしょう。
ニュース&インフォメーション セルフメディケーション税制を知っていますか!?~平成29年1月から特定の医薬品購入に対する新しい税制が始まります~|厚生労働省(*2)
▼関連記事はこちら
医師が知っておくべき「未病」の概念とは?評価方法や病気への移行を防ぐための対策を解説
OTC類似薬の保険適用除外に対する懸念点
続いて、OTC類似薬の保険適用除外の懸念点についても考えていきましょう。大きく以下の3つが挙げられます。
【OTC類似薬の保険適用除外により想定される主な懸念点】
- 患者さんの自己負担が増える
- 受診控えで診療の遅れや健康被害を招くおそれがある
- 医師の処方行動が変わり、医療費の増加につながり得る
患者さんの自己負担が増える
患者負担の増加は、メリットとして挙げた「医療費削減」の裏返しと言えます。
OTC類似薬が保険適用除外になることで、これまで医療保険で賄われていたOTC類似薬の薬価の一部(通常7割)を、患者さん自身が負担するようになるわけです。単純に考えて、3割負担が10割負担になるわけですから、患者さんの負担は3倍以上増えることになります。
OTC類似薬よりもOTC医薬品の方が薬価が高く設定されている傾向にあることから、患者負担はさらに多くなる場合もあるでしょう。皮膚疾患に対してよく用いられる保湿剤(ヘパリン類似物質油性クリーム)やステロイド外用薬など、患者負担が10倍以上になる薬剤もあります。
患者さんの負担が増加すれば、薬剤の塗布量や内服量を"節約"してしまい、症状を十分コントロールできないおそれもあります。一度悪化した症状を治療するには、早期に適切な治療を開始した場合と比べて、よりコストがかかるケースも多いです。OTC類似薬の保険適用除外で期待どおりの医療費削減効果が得られるかは、慎重に検討する必要があるでしょう。
受診控えで診療の遅れや健康被害を招くおそれがある
OTC類似薬の保険適用除外により、医療機関を受診する機会が減ると想定されます。
たとえば「この程度の発熱なら大した病気ではないだろう。病院に行っても治療薬に保険が適用されないのだから、市販薬で様子を見た方が良い」と考え、市販の解熱鎮痛薬で対症療法をしている人が、実は膠原病や血液疾患などの重大な疾患にかかっていることもあり得ます。過度な受診控えは適切な診断や治療の遅れ、疾患の重症化などにつながるおそれがあるのです。
市販薬の過剰な服用や不適切使用により、健康被害を招くおそれがあることも懸念点です。たとえば、頭痛に対して市販の鎮痛薬で対処し続けていると、ロキソプロフェンの過剰摂取による腎障害や、薬剤の使用過多による頭痛をきたす可能性があります。
後になって、かえって高い診療費がかかってしまうことがあるほか、最悪のケースでは「救命できたはずの人が助からなくなってしまう」おそれも考えられます。
医師の処方行動が変わり、医療費の増加につながり得る
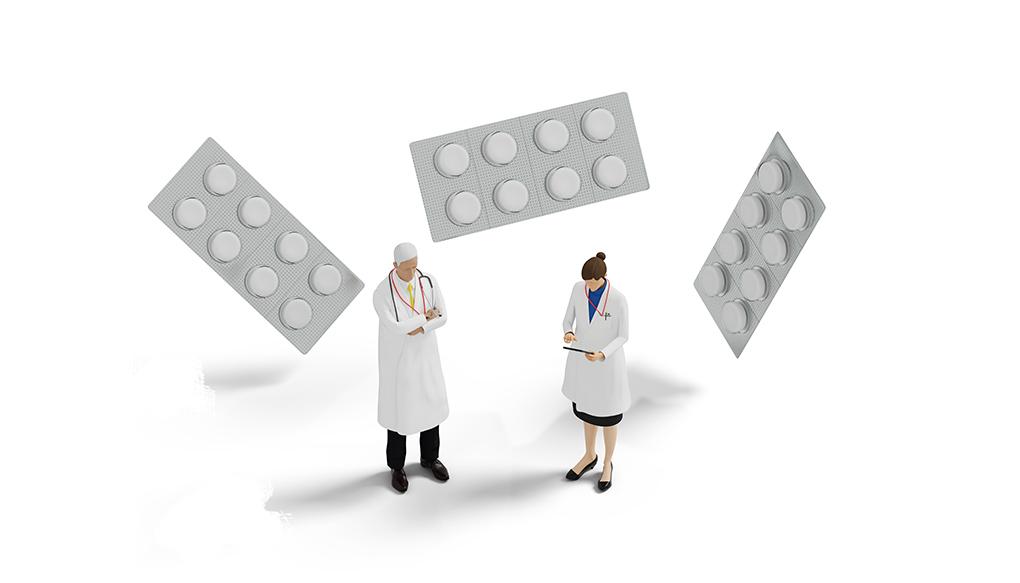
OTC類似薬が保険適用除外となることで、医師の処方にも変化が生じる可能性があります。
たとえば、花粉症の治療で用いられる第2世代抗ヒスタミン薬(抗アレルギー薬)は、エピナスチン・フェキソフェナジン・ベポタスチンベシル酸塩のようにOTC類似薬に分類される(=OTC医薬品が存在する)ものと、ビラスチン・オロパタジンのようにOTC医薬品が存在しないものが混在しています(本稿執筆現在)。
このケースに対して医師は、患者さんの負担が大きい薬、たとえばエピナスチンではなく、負担を軽減できる薬であるオロパタジンの処方を考えるのではないでしょうか。患者さんのためを思ってそのような処方を選択する医師もいるでしょうし、負担が大きくなれば医師個人や病院への不満や苦情につながる可能性もあります。
便秘薬や解熱鎮痛薬などでも、同様のケースが生じやすいでしょう。
医師の処方行動がこのように変化すれば、想定ほど社会全体の医療費削減につながらない、むしろ高くなってしまう可能性もあります。
ほかにもさまざまな懸念点があることから、日本医師会や患者会などからは、OTC類似薬の保険適用除外に反対する意見が多く出されています。
「日医君」だより プレスリリース「OTC類似薬に係る最近の状況について」|日本医師会 日医on-line
社会保険料の削減を目的としたOTC類似薬の保険適用除外やOTC医薬品化に強い懸念を表明|日本医師会 日医on-line
「OTC類似薬の保険除外やめて」難病患者家族が8万5千筆の署名提出|全国保険医団体連合会
【OTC類似薬保険除外】アトピー・難病患者の治療継続が困難に|全国保険医団体連合会
まとめ

この記事ではOTC類似薬をめぐる昨今の議論について見てきました。OTC類似薬は市販薬と同様の有効成分・効能を持つ処方薬で、現時点ではOTC医薬品と比べて、患者さんの自己負担額はかなり少なく設定されています。これが医療費増加の原因の一つと考えられており、保険適用から除外することで医療費を削減するほか、国民のセルフメディケーションを促進する狙いがあります。
一方で、患者さんの負担増や健康被害のリスクを生む懸念などを背景に慎重論も強いのが現状です。経済的な事情で健康格差や医療格差につながれば、国民皆保険制度の趣旨からも望ましいとは言えないでしょう。
2026年度からの段階的導入が現実味を帯びる中、今後の動向が注目されます。








