近年さまざまな「ハラスメント」が問題視される中、医師や医療従事者に特有なのが「ペイシェントハラスメント」(ペイハラ)です。医療現場における「カスタマーハラスメント」に該当する言葉であり、悩みを抱えている先生もいるのではないでしょうか。
医療の世界では昨今「患者中心の医療」の概念が重視されるようになりました。医師をはじめとする医療従事者は、患者さんの思いやニーズに寄り添い、信頼関係を築く努力を日々重ねています。一方で、"患者ファースト"の理念だけが一人歩きしてしまうケースも多いかもしれません。こうした時流も背景に、医療従事者に対して不適切な言動や過剰な要求をする患者さんが、ときに存在します。
この記事ではペイシェントハラスメントの実態や背景、現場の医師・医療機関が疲弊しないために取るべき対策を考えます。

執筆者:Dr.SoS
ペイシェントハラスメントとは
ペイシェントハラスメント(以下、ペイハラ)とは、患者さんやその家族などから医療従事者に対する、暴言・暴力・性的な嫌がらせ(セクシャルハラスメント)、クレームの乱用といったハラスメント行為を指します。
たとえば外来診療では、予約時間外に長時間の診察を求める、診断に納得できないと声を荒げる、「ほかの医者ならもっとちゃんと説明してくれる」といった侮辱的な言葉をぶつける、などの場面が想定されます。救急外来では、緊急性の低い受診にもかかわらず診察の順番や内容について過度な要求やクレームをつける、医師の判断を否定する発言を繰り返す、などが考えられます。
近年はインターネットやSNSの普及によって、新たな形のペイハラも問題になっています。医師の発言や態度を一方的な視点で切り取ってSNSに投稿する、個人や病院の実名を挙げて中傷的なコメントをレビューサイトに投稿する、などです。こうした「晒し行為」は医師個人の名誉やメンタル、医療機関の信用に深刻な影響を及ぼします。
ペイハラは医療現場で日常的に起きているにもかかわらず、「患者さんの言うことだから仕方がない」として見過ごされるケースも少なくありません。「こんなことを言われるのは自分に落ち度があったからではないか」「この程度で文句を言うのは医療者として未熟なのではないか」と、自分を責める医師もいますが、逆恨みから身体的被害が生じるおそれもあるほか、個人の健康やパフォーマンスへの影響にとどまらず、転科や離職といったキャリアや人生の選択、さらには医療全体の質の低下にも波及する深刻な問題となっています。
こうした行為を行う患者さんや家族は「モンスターペイシェント」とも呼ばれます。病気に対する不安や、医療制度や過去の体験からの不信感など、さまざまな背景が存在することでしょう。しかしどのような理由があるにせよ、医療従事者を過剰に傷つける行為が正当化されるわけではありません。
カスタマーハラスメントとペイシェントハラスメントの違い
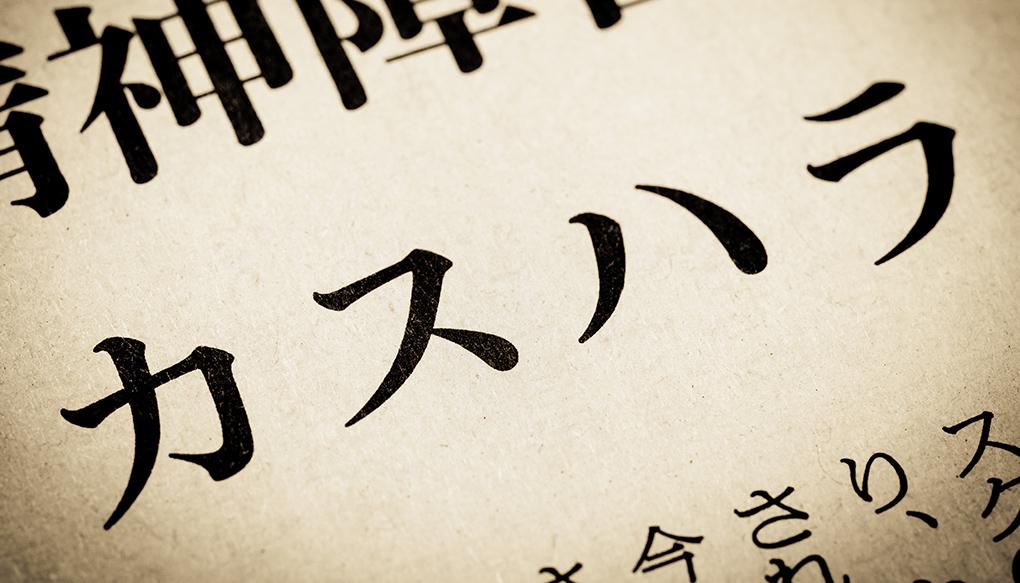
結論から述べると、ペイシェントハラスメントはカスタマーハラスメントの一部と言って良いでしょう。
ペイハラはその言葉(ペイシェント=患者)が意味するとおり、医療業界における用語ですが、社会一般でも顧客(カスタマー)からの不当な要求を意味する「カスタマーハラスメント」(カスハラ)が大きな問題となっています。
2022年に厚生労働省が作成した『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、カスハラは下記のように説明されています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf(2025年7月10日閲覧)
たとえば、飲食店で注文間違いがあったときに店長に土下座をさせる、役所の窓口で自分の要求が通らないと威圧的な言動や暴力行為を行う、などはカスハラの事例として想像しやすいでしょう。2025年4月には、東京都などでカスハラを未然に防ぐための条例が施行されました。
医療は、患者さんと医療機関とが「医療契約」(診療契約)を結んだ上で成り立つものです。患者さんは顧客、つまりペイハラは「医療現場で生じるカスハラ」と解釈できます。
しかし、カスハラに対する見解や指針がそのまま医療現場に当てはまるかというと、必ずしもそうではありません。たとえば、医師には医師法第19条で「応召義務」が定められており、正当な事由がなければ診察治療を拒むことはできないとされています。患者さんとの信頼関係が喪失している場合は"応召義務の例外"となり、新たな診察を行わないことが正当化されますが、通常の顧客-消費者関係と比べると、その判断のハードルは高いでしょう。
また、患者-医師間では「情報の非対称性」が大きく、医師が提供する医療が適切でも、患者さんが理解できず「もっと良い治療を受けられたはずだ」と指摘・要求するケースも起こり得ます。一般的なカスハラであれば、提供する商品やサービスに過失がなければ「不当な要求」とみなされるものでも、患者さん側の要求が「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く」と解釈されないおそれもあるのです。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル|厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例|東京都例規集データベース
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)|e-Gov 法令検索
医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について|厚生労働省
▼応召義務に関する詳しい記事はこちら
医師が応召義務を負わない『正当な理由』とは【現役医師解説】
ペイシェントハラスメントが生じる背景

どうして、このようなペイハラが生じてしまうのでしょうか。
医療業界では昨今、患者さんの権利を尊重し、満足度の高い医療を提供するための"患者ファースト"の理念が浸透しています。そのため、インフォームド・コンセントの徹底、ともに治療方針を考える姿勢、説明責任の重視といった方針・風土が根付いてきました。とくに近年は、治療方針の決定に患者さんの意思を介在させる「SDM」(shared decision making、共同意思決定)の概念が重視され、実践されています。
一方で、こうした"患者ファースト"の理念だけが一人歩きし、その目的・意味の解釈や実践手法を誤ると、「患者さんの意見はすべて叶えるべきだ」「患者さんの不満は、医療従事者側に落ち度がある」などと、医師に対して我慢や自己犠牲を強いる場面も生じ得ます。
とくに若手医師や女性医師、非正規雇用の医師は立場が弱く、患者さんとのトラブルを自己責任として受け止めやすいと言えます。若手の場合は経験・自信の不足から、患者さんの攻撃的な態度を受け止めてしまいやすいでしょう。女性医師の場合は一般に男性よりも体力面で劣ることで暴言・暴力行為の対象となりやすく、性別に基づくセクシャルハラスメントが混在する危険もあります。医師がトラブルを自責して終わることがないよう、指導医や管理職が、ペイハラという問題に適切に対処する必要があるでしょう。
また、医療機関にペイハラの相談窓口が整っていない、あるいは存在はしても実質機能していないケースも少なくないと思われます。こうした組織では、ペイハラは表面化しづらいでしょう。
このように、患者さんの希望をできる限り優先しようとする医療現場の風土や、トラブルを拾い上げ適切に対処するシステムが未成熟なことが、ペイハラの背景・要因にあると考えられます。
SDM(共同意思決定)とは?患者と医師が協力する医療の在り方
NBM(narrative based medicine)とは?ナラティブ(物語)の意味やEBMとの違いを解説
ペイシェントハラスメントが生じる頻度
ペイハラやそれによる被害は、どれくらい起こり得るものなのでしょうか。
さまざまな地方医師会や民間企業のアンケート調査からは、ペイハラは決してまれな出来事ではなく、多くの医師が経験していることが覗えます。
医師以外の医療従事者でも、ペイハラの被害は数多く発生しています。少し古いデータですが、2017年度の看護師の労災支給決定(認定)の要因として最も多かったのは「患者からの暴言・暴力の体験」で、44.2%を占めていました*1,2。ペイハラはまれな事象ではなく、医療現場に深刻な影響を与えていると言えるでしょう。医療従事者の働き方改革が進む中、ペイハラの実態にも光を当て、勤務環境を改善していく必要があります。
労災疾病臨床研究事業費補助金 過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究 平成29年度総括・分担研究報告書 |国立保健医療科学院 健康危機管理支援ライブラリー(H-CRISIS)(*1)
平成30年版 過労死等防止対策白書 概要|厚生労働省(*2)
ペイシェントハラスメントが医師に与える影響
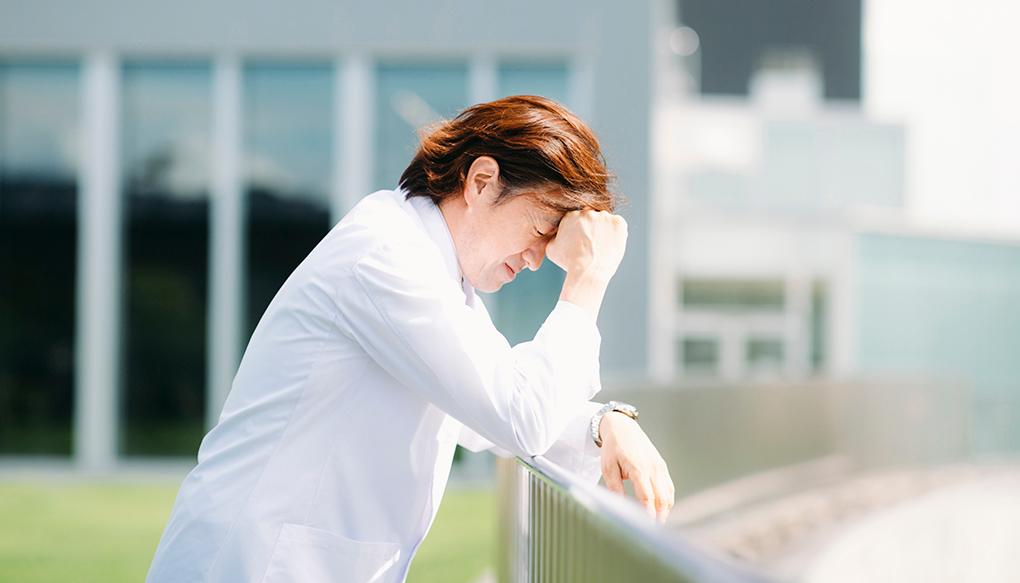
ここからは、ペイハラが医師に与える影響について見ていきましょう。
ペイハラは医師にとって、単なる"嫌な出来事"では済みません。医師のメンタルヘルスに深刻な影響を与え、ときにはキャリアを揺るがす事態へ発展する場合もあります。
医師という仕事はプロフェッショナルとして、感情を抑えて冷静に対応することが求められる、いわゆる「感情労働」(emotional labor;Hochschildが提唱)に該当します。心ない言葉や理不尽な要求を浴び続ければ、精神的な負担は蓄積していき、やがては「燃え尽き症候群」(バーンアウト)へとつながりかねません。
医療は不確実なものであり、必ずしも望ましい結果が得られるわけでないことを医師の皆さんはご理解されていると思いますが、世間一般では十分に理解されているとは言えません。このため「自分が望んだ通りの治療結果が得られなかった」という逆恨みから身体的な被害、最悪の場合は事件に至る例もあります。
たとえば2022年に発生した「ふじみ野市散弾銃男立てこもり事件」は、被告人が在宅医療クリニックの診療内容に不信感を抱いたことが犯行の動機でした。また、2025年6月にも、千葉県の病院で男性患者が医師を刺傷させる事件がありました。日本に限らず中国でも、患者や患者家族による傷害・殺害事件が近年頻発していると報道されています。
ペイハラは、長期的には医師のキャリアの選択肢を狭める要因にもなり得ます。地域医療や在宅医療など、患者さんとより身近な環境で働くことを希望していた医師が、度重なるペイハラやトラブルで臨床現場を離れる事態も起きかねません。
ペイシェントハラスメントへの対策(対応・予防)
ペイハラを防ぐためには、個人の努力だけでは限界があります。医療業界全体で、組織的かつ多角的な対策が必要です。ここでは医療機関、さらに医師個人でも取り得る具体的な対策をいくつか紹介します。
医療機関での対策
医療機関としては、ペイハラへの対策マニュアルを策定したり、医療従事者やスタッフに対する研修を実施したりして、ペイハラ発生時の対応フローや院内のルールを決めておくことが必要でしょう。
たとえば、患者さんから不適切な言動があった際は別のスタッフも同席する、さらには記録を残したり、担当者を変更したりするなど、組織として対応する仕組みを事前に定めておくことで、現場の医師が孤立せずに済みます。院内に相談窓口や報告体制を整備し、「声を上げても大丈夫」という安心感を持てる環境をあらかじめ作っておくことも大切です。
予防策としては、「ペイハラは許されない行為である」という方針を、明確に示すことも有効です。効果が期待されるのは、受付や待合室・診察室に「暴言・暴力はハラスメントに該当する」ことを明記したポスターなどを掲示することです。視覚的に注意喚起をすることで、患者さん側の意識改革につながります。
ペイシェントハラスメントの対応マニュアル

ペイハラに特化した公的な対策マニュアルはまだ存在しませんが(本稿執筆時点)、先述した厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』は、ペイハラ対策にも活用できます。
また、看護領域では日本看護協会が『看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン』を、介護領域では厚生労働省が『介護現場におけるハラスメント対策マニュアル』を作成しており、これらも参考になるでしょう。
ほかにも厚生労働省のサイトには、研修用の動画コンテンツや、病院の取り組み事例も紹介されています。まだ自分の勤務先にマニュアルや研修教材がない、あるいはこれから作る立場にあるという方は、参考にしてみてください。
病院における患者・家族の暴力に対する医療安全力を高める体制の醸成|日本医師会 医療安全推進者ネットワーク
トップの意識の高さからマニュアル策定やHPへの対応方針を公開|厚生労働省 あかるい職場応援団
医療従事者の勤務環境の改善について「その他 医療現場における暴力・ハラスメント対策」|厚生労働省
看護現場におけるハラスメント対策|日本看護協会
介護現場におけるハラスメント対策|厚生労働省
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(令和4(2022)年3月改訂)|厚生労働省・三菱総合研究所
医師個人での対策
医師個人レベルで重要なのは、「線引き」と「記録」です。
ペイハラが疑われる言動に対しては、毅然とした態度で境界線を示すことが重要です。「それ以上の発言はお控えください」「そのご要望にはお応えできません」などと明確に伝えることで、患者さん側の言動にブレーキをかけることができます。
また、患者さんの不適切な言動を感情的に処理せず、客観的な事実として記録しておくことで、のちのトラブル対応や報告に役立ちます。できれば電子カルテや院内報告書など、証拠として残る形が望ましいです。
問題にぶつかった際は一人で抱え込まず、早めに上司や同僚に相談することも忘れてはなりません。話すことによる心理的効果も期待できるほか、アウトプットすることで状況を整理でき、相談相手から同様の経験や対処法を聞けたり、助言を受けたりすることもできるでしょう。
法的手段や第三者機関の活用
悪質なハラスメント行為に対しては、法的な対応も視野に入れましょう。暴言や暴力は、刑法や民法上の名誉毀損・侮辱・傷害などに該当する可能性があります。院内に法務部門がない場合は、弁護士への相談や医師会を通じた支援を得られると良いでしょう。
厚生労働省や日本医師会でも、医療者の相談窓口の整備が進んでいます。こうした第三者機関を活用することで、法的・心理的なサポートを受けることができるでしょう。
医療現場における暴言・暴力等のハラスメント対策について(情報提供)(医政総発0228第1号平成31年2月28日付通知)|厚生労働省
日本医師会ペイシェントハラスメント・ネット上の悪質な書込み相談窓口(日医ペイハラ・ネット相談窓口)|日本医師会
「日本医師会ペイシェントハラスメント・ネット上の悪質な書込み相談窓口(日医ペイハラ・ネット相談窓口)」を運用中!!|日本医師会 日医on-line
まとめ
この記事ではペイシェントハラスメントについて見てきました。医療機関を受診する患者さんやその家族はさまざまな疾病を抱え、不安な感情を抱いています。患者さんに寄り添う"患者ファースト"の考え方で医療が進められること自体は、素晴らしいことでしょう。しかし、一部の患者さんによる過度な要請・要求につながってしまうおそれもあります。
ペイハラは医師が一人で解決することは難しいものです。個人で抱え込まず、複数のスタッフで対応にあたることが望ましいでしょう。大手の医療機関では近年、院内マニュアルなどの整備が進んでいるため、ご自身の組織でどのような対策が取られているか、一度確認してみるのも良いでしょう。
この記事がペイハラの理解や、対策を考える上での一助となれば幸いです。








