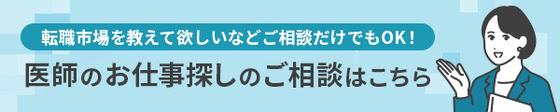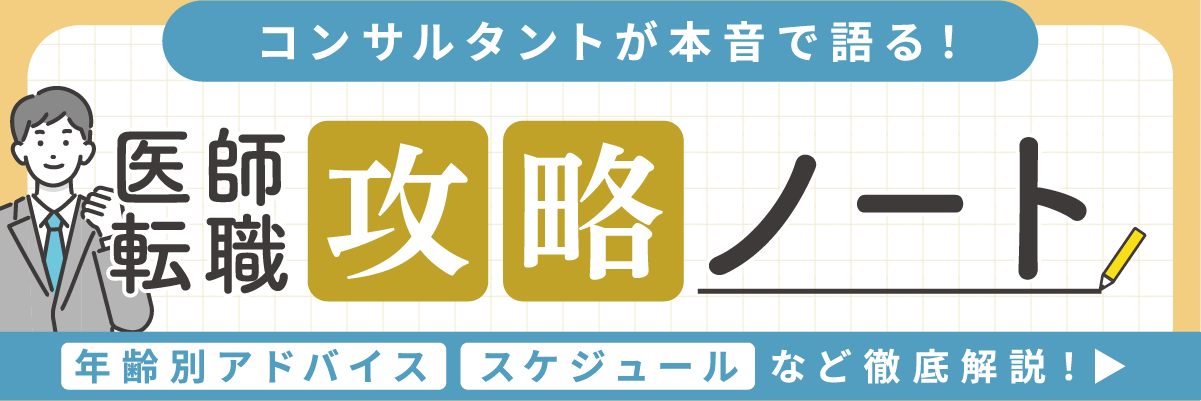大学病院で働く医師の世界は序列社会だと思われがちです。若手の頃は長時間労働を強いられ、経験を重ねることで発言力が増して処遇も改善していくようなイメージを持たれる方も多いでしょう。
そこで今回は、大学病院の医局内での医師の序列について詳しく解説します。働き方改革や転職時の注意点もあわせて解説いたしますので、ご参考ください。
執筆者:成田 亜希子
医局の「序列」とは?

医局にはトップから病院長、教授、准教授、講師、助教、助手、医員、研修医などの肩書をもつ医師がいます。それぞれの役割と働き方について詳しく見てみましょう。
研修医
一般的に「研修医」は、医学部卒業後に厚生労働省が定める初期臨床研修に取り組んでいる医師を指します。以前は卒後3年目以降の医師を後期研修医と呼ぶこともありましたが、2018年からの新専門医制度では3年目から専門医の研修が始まるため、研修医には含みません。
なお、研修医は医局の中で一番下の立場であり、研鑽中の身でもあるため、長時間労働となるケースも多いようです。
助教、助手、医員、専攻医など
大学病院によって名称が異なることもありますが、一般的に2年間の初期臨床研修を終えた医師は、日本専門医機構が定める所定のプログラムをこなしながら専門医を目指します。プログラムは診療科によって異なりますが、3~5年ほどで、処遇は研修医のときとあまり変わらないケースが多いでしょう。
専門医を取得したあとは、医員や助手として勤務し、博士号を取得することで助教への昇格が可能です。助教になると、少しずつ長時間労働などは改善されるようです。
講師
40歳前後になると、助教から講師に昇格する人が増えます。大学病院では診療のほかに医学生の講義や実習に関わる機会も増え、仕事の幅が広がります。頻回な日当直などの業務からは解放されていくことが多くなるでしょう。
准教授
40代後半で就任するケースが多いですが、医局員の年齢構成によってはもう少し前後します。准教授になると長時間労働などが少なくなる一方で、教授へのランクアップを視野に入れ、教授選に向けての準備が必要なため、論文執筆などに多くの時間を割くことになります。
教授
教授は医局でトップの立場となり、50歳前後の医師が選ばれることが多いです。教授になると診療に携わる時間は減り、講演会や論文執筆などで多忙になることが多いでしょう。
病院長
教授よりさらに上の立場になるには、病院長を目指しましょう。病院長はその名の通り、大学病院のすべての診療科の医師のトップです。したがって、責任も当然重くなり、病院運営などに時間を割くことも増えるでしょう。
医師が医局で出世する方法

大学病院には数多くの医師がいるため、准教授以上へランクアップできるのはほんの一握りです。医師の世界は未だに卒業年度や出身校による序列がありますが、40代からは卒業年度や出身校とは直接関連のない格差が生まれていきます。
大学病院の医局で出世するには、医師としての診療スキルが優れていることも大切ですが、研究を遂行する能力や論文を執筆する能力も必要となります。どんなに手術のスキルが高くても、論文のIF(インパクトファクター/影響度)が低いと、准教授や教授にランクアップすることは困難です。また、教授選を取り仕切る教授会で認められる必要もあるため、人格が優れていることや政治力も求められるでしょう。
医師の働き方改革で医局に変化?

2024年4月から、医師の「働き方改革」が本格化します。
具体的には、医師の長時間労働を制限して原則的に時間外労働を月100時間未満に制限するというものです。その上限を超える場合は、労働時間の短縮などについて面接指導を受ける必要があるとされています。
現在、医師は長時間労働や休日出勤など過酷な労働環境に置かれているケースが多く、とくに若手医師は帰宅できない環境に置かれることも少なくありません。働き方改革によって、医師の労働環境の改善が期待されます。
一方で、働き方改革が行われると大学病院の医局制度や遠隔地の医療体制が崩壊するのではないかという懸念があるのも事実です。一般的に大学病院では高度な治療を行うため、長時間の手術や救急の患者さまの時間外手術なども多く行います。
そのため、医師の労働時間は長くなる傾向にありますが、勤務時間に制限がかかることで高度な医療を遂行するためには現状より多くの人手が必要となります。
また、大学病院の任務の一つでもある研究を行う時間も限られてくるでしょう。そのため、大学病院から派遣されている遠隔地の医療機関の医師が引き上げられる可能性も指摘されているのです。
前述の新専門医制度が開始された際にも、専攻医の大学病院離れが進みました。今回の医師の働き方改革においても、給料が低い傾向にある大学病院からの離脱が加速して、医局制度が崩壊していく可能性があるとの声があがっています。
医局での転職・退局で気をつけるポイント

新専門医制度や医師の働き方改革などによって、医局は今後もあり方や体制が大きく変わっていくことが予想されます。そうした医局からの転職や退局を検討するときは、どのようなことに注意するべきでしょうか。
今後のキャリアをしっかり検討して決断する
医師には様々な方向性のキャリア形成があります。どのようなキャリアを最終的な目標にするのか熟考したうえで、働き方を決めていきましょう。
若手医師の場合は、学位や専門医取得を目指すかどうかを踏まえ、どのような進路を選ぶべきか決断するのが大切です。また、診療と研究活動のどちらに重きを置くかによっても働き方は大きく変わるでしょう。
医師としての人生をしっかり検討して、それぞれの道に合った選択をしていくことが大切です。
退局の意向は真摯に伝える
医局は肩書による序列が強いため、退局の意思を伝えにくいと悩む医師も多いでしょう。しかし、医局は終身雇用ではありません。医局のなかでは自身が思い描くキャリアを形成するのが難しい場合もあります。
また、激務な労働環境に置かれプライベートとの両立が難しいなどの事情もあるでしょう。退局を決意した場合は、できるだけ早めに伝えるようにしましょう。
自分に合った医局の選び方
新たに医局を選ぶときは、医師の働き方や診療と研究の内容、待遇などから総合的に判断して決めるのが大切です。研究内容に興味があったとしても、医師数が少なく、且つ過酷な労働環境では、研究に集中できないケースも少なくありません。
事前に医局の見学をするのもおすすめです。実際に働く医師の様子や医局全体の雰囲気などを知り、自分に合っているかを念入りに確認しましょう。
ドクタービジョン+は、医師転職支援サービス「ドクタービジョン」の情報発信を担うメディアです。「ドクタービジョン」は、医師だけでなく、薬剤師や看護師など医療従事者の転職を支援する、『地域を支える医療系総合コンサルタント』として皆さまをご支援しています。
"医局以外でのこれからの働き方"を考えたときに、「転職」という選択肢が出てくることも少なくないと思います。そうしたときこそ、求職者の皆さま一人ひとりとしっかり向き合うことを大切にするドクタービジョンにご相談ください。アンケートに留まらず、お電話や対面での面談の場合は、お話を通してご経験やご意向を把握した上で、一緒にキャリアプランを考えていきたいと考えています。
医局の仕組みを知って自分に合った働き方の検討を
大学病院の医局は、教授をトップとした序列社会です。研修医や専攻医のときは長時間労働や日当直などへの対応が避けられないケースも少なくありません。しかしながら、講師や准教授、教授に昇格すると、働きやすくなることが多くなります。
しかし、医局で出世できるのは一握りの医師です。さらに新専門医制度や医師の働き方改革の影響を受けて医局制度が大きく変わることも予想されます。
医師としてどのようなキャリアを築きたいかをよく考えて、医局に所属しない選択肢も視野に入れて働き方を決めていきましょう。また、新たな医局への入局を検討する場合は、その特徴を理解して慎重に決めることが大切です。
1分で登録完了!コンサルタントへの転職相談
「転職について気になることがある」「周りの転職活動の動向を知りたい」など、
まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。