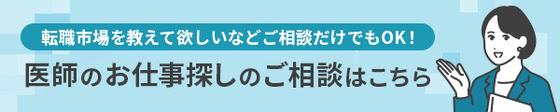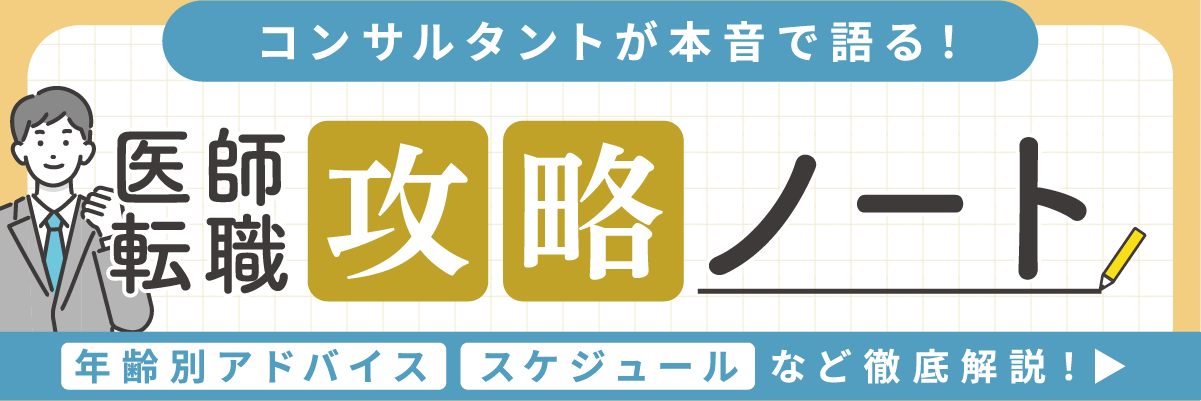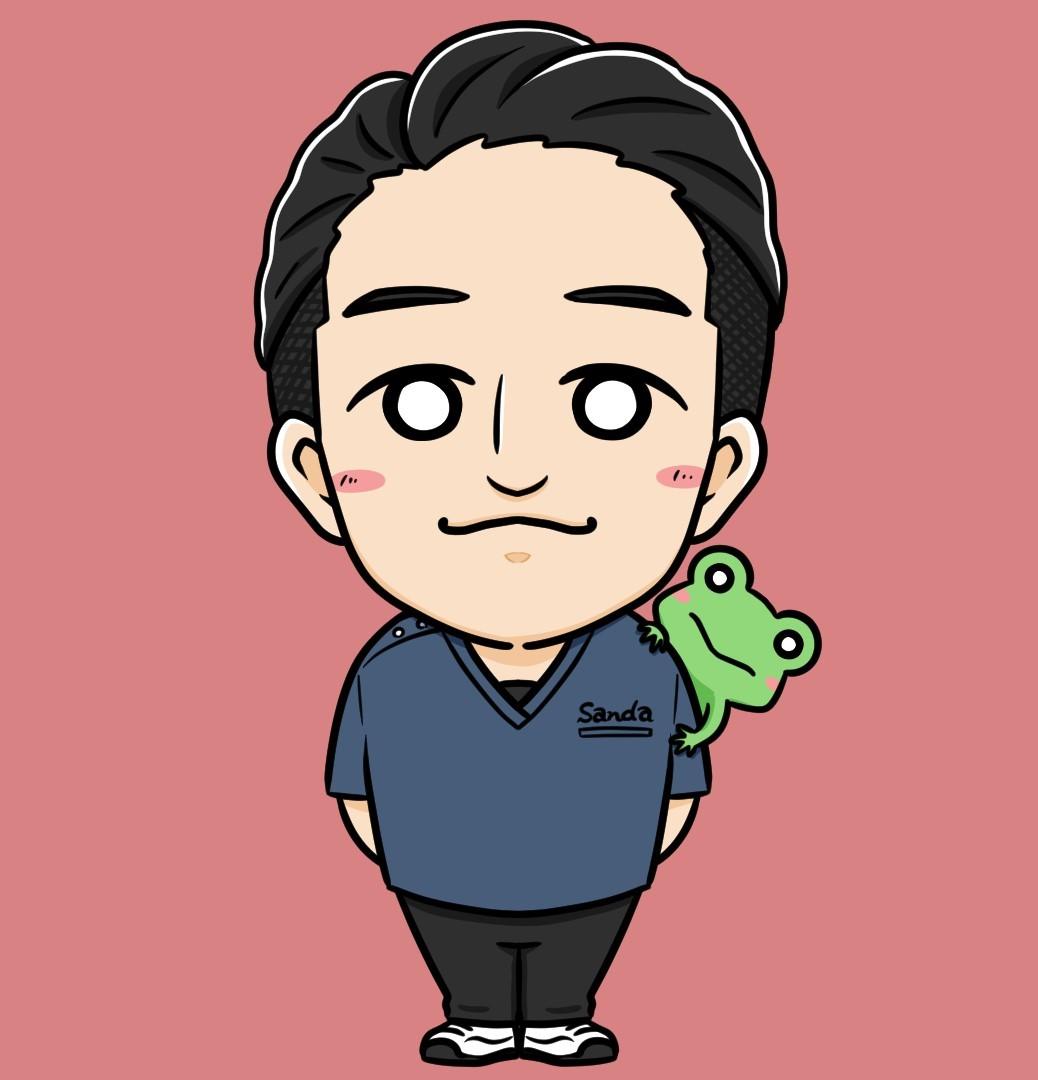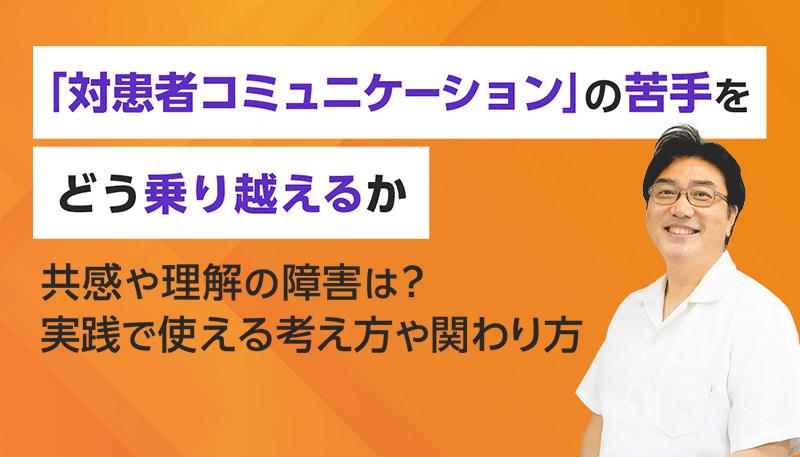超高齢社会を迎えた日本において、原疾患の治療を行うだけでは"足りない"ことを経験する先生も多いのではないでしょうか。リハビリテーション医療は、活動を維持して在宅復帰をしやすくするだけでなく、原疾患による予後を改善することもあり、現代の医療ではどの診療科にも重要な存在となっています。ほかの医療と同じように患者さん一人ひとりに合わせて計画することが大切で、「リハビリテーション総合計画評価料」という診療報酬もあります。
この記事では、「リハビリテーション総合計画評価料」の概要、関連する「リハビリテーション総合実施計画書」の作成のポイントなどを解説します。
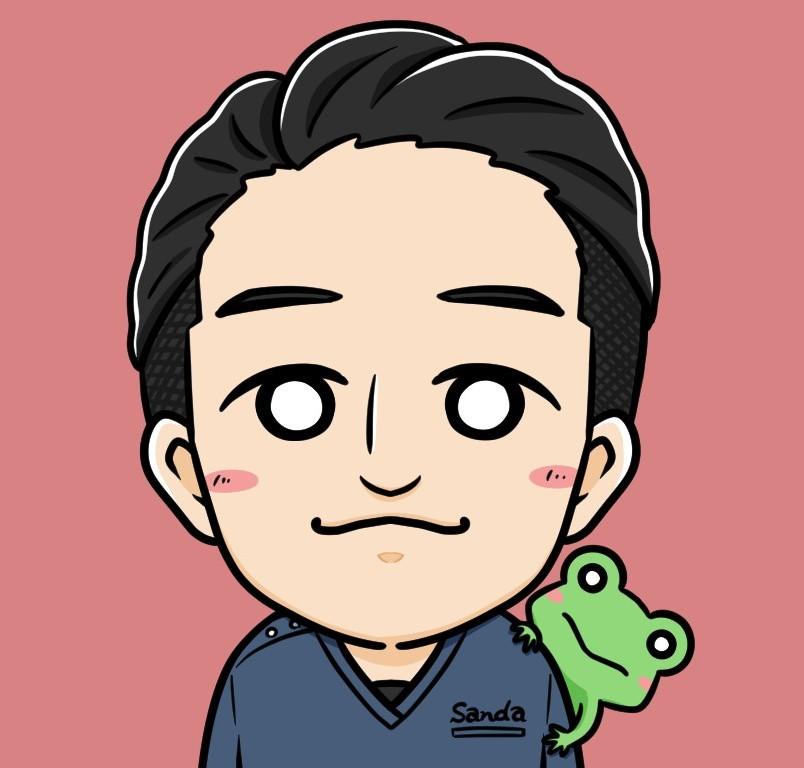
リハビリテーション総合計画評価料とは
「リハビリテーション総合計画評価料」とは、リハビリテーションを行う患者さんに対して算定できる診療報酬です。厚生労働省は以下のように述べています。
【リハビリテーション総合計画評価料の概要】
定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000548708.pdf(2025年7月17日閲覧)
この文章から、リハビリテーション医療では多職種で計画を立てて実施し、効果を確認するという一連の流れが重視されていることがわかります。
リハビリテーション総合計画評価料の算定対象・回数
リハビリテーション総合計画評価料は、「疾患別リハビリテーション料」を請求しようとするすべての患者さんについて、算定が可能です。
患者さん1人につき月1回、算定することができます。
リハビリテーション総合計画評価料1と2の違い
リハビリテーション総合計画評価料は2種類あり、以下のように定められています(本稿執筆現在)。
| リハビリテーション総合計画評価料1 | 300点 |
|---|---|
| リハビリテーション総合計画評価料2 | 240点 |
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603758.pdf(2025年7月17日閲覧)
1と2の違いは「介護リハビリテーションを予定しているかどうか」です。「介護リハビリテーションを予定している」と判定されるのは、患者さんが要介護被保険者(要介護の介護認定を受けた人)であり、かつ各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過してリハビリテーションを実施している場合です。
個別事項(その1)(リハビリテーション、医薬品の効率的かつ有効・安全な使用)|厚生労働省 第423回中央社会保険医療協議会総会(2019年9月)
診療報酬改定 通則 第7部 リハビリテーション|厚生労働省
リハビリテーション総合実施計画書とは

「リハビリテーション総合実施計画書」は、リハビリテーション総合計画評価料を算定するために必要な書類です。
リハビリテーション総合実施計画書と似た名称として「リハビリテーション実施計画書」がありますが、両者は異なる書類です。いずれもリハビリテーションのプランを記載するものですが、リハビリテーション実施計画書には詳細な記載や多職種での作成義務はなく、リハビリテーション総合計画評価料を算定する資料とはなりません。一方でリハビリテーション総合実施計画書は、リハビリテーション実施計画書の代わりとすることができます。
リハビリテーション総合実施計画書に記載する内容
リハビリテーション総合実施計画書にはいくつか書式がありますが、どれも多くの項目を記載する必要があります。
具体的には以下のような項目で構成されており、主に国際生活機能分類(ICF:International Classification of Functioning, Disability and Health)による健康の構成要素に基づいています。
【リハビリテーション総合実施計画書に記載する主な内容】
| 算定病名、合併疾患 | リハビリテーションが必要になった原因の疾患、管理が必要な合併症・併存疾患 |
|---|---|
| 心身機能・構造 | 意識障害や麻痺、筋力低下などの機能 |
| 活動 | 主に日常生活動作(ADL:activities of daily living)が自立か、介助が必要か ※FIM(functional independence measure:機能的自立度評価法)による記載が望ましい。 |
| 栄養 | 現在の栄養の摂取状況、必要栄養量など |
| 参加 | 職業や経済状況など、社会とのつながり |
| 心理 | 障害の受容などの心理的側面 |
| 環境 | 家族や家屋環境 |
| リハビリテーションの基本方針、リスク管理 | 個々に応じたリハビリテーションを進める上での方針、リスク |
| 本人・家族の希望 | 本人・家族がどのように考えているか、何を希望するか |
| 目標 | リハビリテーションの目標 |
※様式によっては機能・活動・参加などの記載も必要。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293312.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220533.pdf
(2025年7月17日閲覧)
令和6年度診療報酬改定【省令・告示】(2)2 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305第4号)
└別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
└別紙(医科点数表)様式23 リハビリテーション実施計画書
▼関連記事はこちら
高齢者総合機能評価(CGA)とは?21年ぶり新ガイドラインの概要・評価項目や診療報酬加算を解説
リハビリテーション総合実施計画書を作成する流れ
まずは患者さんに対してリハビリテーションの適応を検討し、適応があると判断した場合にはリハビリテーションの処方を行います。処方を受けて、各療法士がリハビリテーションを実施します。
このリハビリテーション開始後7日以内(遅くとも14日以内)に、リハビリテーション総合実施計画書を作成しなければなりません。計画書は多職種が協働(共同)して作成する必要があります。
作成した内容は患者さんまたは家族に説明し、写しを診療録に添付します。説明は医師が実施することが求められています。
リハビリテーション総合計画で意識したいこと
ここからは、効率的なリハビリテーションによる患者支援と、不適切な算定防止のために、リハビリテーション総合計画について意識したい留意点をご紹介します。
- 多職種による定期的な作成・評価
- 地域連携
- 説明と同意
1.多職種による定期的な作成・評価

リハビリテーション総合実施計画料の算定に関して、地方厚生局が保健医療機関に以下のような指導をした事例があります。
- 医師が単独で作成し、多職種で共同して作成していない。
- リハビリテーション総合実施計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行っていない。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000374509.pdf(2025年7月17日閲覧)
リハビリテーション総合実施計画書では多くの項目を網羅する必要があるため、多職種が協働(共同)して作成することが求められています。また、総合実施計画書は「これからどのようなリハビリテーションを提供していくか」という"計画"だけでなく、「これまでのリハビリテーションはどうだったのか」という"効果判定"の側面も持つため、定期的な作成・評価・見直しが課されていることにも留意が必要です。
チーム医療で医師が大切にすべきこととは。各職種の役割や多職種連携のメリットを解説
2.地域連携
近年では医療と介護の連携、医療機関同士の地域連携が重要視されています。リハビリテーションにおいても地域連携のための情報提供は必須です。
かつては「リハビリテーション計画提供料」という加算がありましたが、2024(令和6)年度の診療報酬改定により廃止されました。一方で、各疾患リハビリテーション料を算定するための施設基準として、ほかの介護事業所や医療機関でリハビリテーションを実施・継続する予定がある場合にリハビリテーション総合実施計画書等の文書で提供できる体制が求められるようになりました。
リハビリテーション総合実施計画書は単なる計画だけではなく、情報提供の役割も持つこととなります。
病診連携とは?地域連携との関連、取り組みの実例や今後の展望【現役医師解説】
「地域医療構想」とは?概要や策定経緯、2040年に向けた新たな取り組みを解説
地域包括ケアシステムとは?医師に求められる役割
3.説明と同意
リハビリテーションは各療法士が行うイメージが強いかもしれませんが、医師の処方と指示に基づいて実施されるものです。ほかの治療と同様に、医師と患者さんとの間で「説明と同意」が求められます。
とくにリハビリテーション総合実施計画書については、説明者(医師)と患者さん側双方の署名が必要であり、診療録への添付も求められます。計画書には「患者・家族の希望」という欄もあり、十分なヒアリングと同意が求められます。
補足:不適切算定の判定事例
リハビリテーション総合計画の作成や運用が不十分と判定されると、不適切な算定とみなされ、診療報酬の返還を求められることもあります。過去には、以下のような原因で、診療報酬の返還に至った事例があります。
- リハビリテーション総合実施計画書を作成していない
- 説明した内容を診療録に記載していない
- リハビリテーション計画において医師の指摘がない
リハビリテーション総合実施計画書は項目が多く、多職種で記載する必要もあるため、負担は少なくありません。しかし返還額が大きいと億単位になるケースもあり、経営への影響は大きいでしょう。
なにより不適切な実施計画は患者さんへの負の影響も考えられます。適切な作成と運用を意識したいものです。
あまり知られていない、リハビリテーションに関する"お金の話"

ここまでリハビリテーション総合計画評価料について解説してきましたが、ここではそのほかのお金の側面からも、リハビリテーションについて理解を深めていきましょう。
DPCにおけるリハビリテーションの位置付け
急性期病院では、多くの施設でDPC制度(診断群分類別包括評価)を導入しています。DPC制度とは、疾患や手術・処置等ごとに入院基本料、一部の検査や画像診断、投薬などが包括される診療報酬制度のことです。
リハビリテーションはこの包括範囲外であるため、実施した分だけ上限の範囲内でリハビリテーション料を算定できます(後述)。つまり、リハビリテーションは実施すればするほど、病院の収益につながるのです(※注)。
実際にどれだけのリハビリテーションを提供できるかは、リハビリテーション部門の体制・人員によりますが、患者さんだけでなく病院の経営のためにもなることを思うと、必要に応じてリハビリテーション処方を検討する閾値を下げても良いかもしれません。
※注:リハビリテーションにおける薬剤料は、包括評価の対象となります。
疾患別リハビリテーション料
リハビリテーション料を算定できること自体は、多くの先生方がご存知かと思います。しかし、疾患によって診療報酬が違うことはご存知でしょうか。
同じ疾患群に対するリハビリテーション料でも、人数や設備などの施設基準を満たすかどうかで、診療報酬は異なります。
医療行為のほとんどは「行為の回数」で報酬が設定されていますが、リハビリテーション料は1単位(20分以上)という「時間」で規定されているのも特徴です。
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ:205点、Ⅱ:125点)
...急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患、慢性心不全(左室駆出率40%以下)など - 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ:245点、Ⅱ:200点、Ⅲ:100点)
...脳梗塞、脳腫瘍、脊髄損傷、パーキンソン病、高次脳機能障害 など - 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ:180点、Ⅱ:146点、Ⅲ:77点)
...急性疾患等に伴う安静による廃用症候群 - 運動器リハビリテーション料(Ⅰ:185点、Ⅱ:170点、Ⅲ:85点)
...上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、運動器の悪性腫瘍 など - 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ:175点、Ⅱ:85点)
...肺炎・無気肺、肺腫瘍、肺塞栓、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者 など
(対象疾患の例は厚生労働省 第423回中央社会保険医療協議会総会資料「個別事項(その1)(リハビリテーション、医薬品の効率的かつ有効・安全な使用)」(2019年9月)p.5より引用(一部編集))
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000548708.pdf
(2025年7月17日閲覧)
リハビリはいつまでできるのか?
リハビリテーション料には、それぞれ「標準的算定日数」が設定されています。起算日より1日6単位が上限(回復期リハビリテーション病棟など別に定められる場合には9単位が上限)ですが、標準的算定日数を超えて状態を維持することを目的とする場合には、1ヵ月に13単位まで算定ができます。
ただし、標準的算定日数を超えた後でも状態の改善が期待できる場合、一部疾患には日数制限が適応されないため、必要なリハビリテーションが制限されるわけではありません。
ドクタービジョン+は、医師転職支援サービス「ドクタービジョン」の情報発信を担うメディアです。「ドクタービジョン」は、医師だけでなく、薬剤師や看護師など医療従事者の転職を支援する、『地域を支える医療系総合コンサルタント』として皆さまをご支援しています。
診療報酬改定などの医師を取り巻く環境の変化を受けてこれからの働き方を考えたときに、「転職」という選択肢が出てくることも少なくないと思います。そうしたときこそ、求職者の皆さま一人ひとりとしっかり向き合うことを大切にするドクタービジョンにご相談ください。アンケートに留まらず、お電話や対面での面談の場合は、お話を通してご経験やご意向を把握した上で、一緒にキャリアプランを考えていきたいと考えています。
まとめ

現在の医療においては早期からのリハビリテーション介入、多職種連携によるチームアプローチ、患者さんとその家族への十分な説明と同意が、患者さんの機能回復とQOL向上、さらには原疾患の予後改善にも不可欠と言えます。リハビリテーション総合計画評価料は単なる加算ではなく、患者さん一人ひとりに合わせた最適なリハビリテーションを提供するための重要なツールと言えるでしょう。
普段の診療で、何気なくリハビリテーションをオーダーする先生も多いかもしれません。若手の先生であれば「上司に言われたから」というケースも多いのではないでしょうか。しかし多くの疾患でリハビリテーションの有用性が示されている今だからこそ、総合実施計画書などを通じてリハビリテーションへの理解を深めていくことが、患者さんのためだけでなく自身の診療の質を上げることにもつながるでしょう。