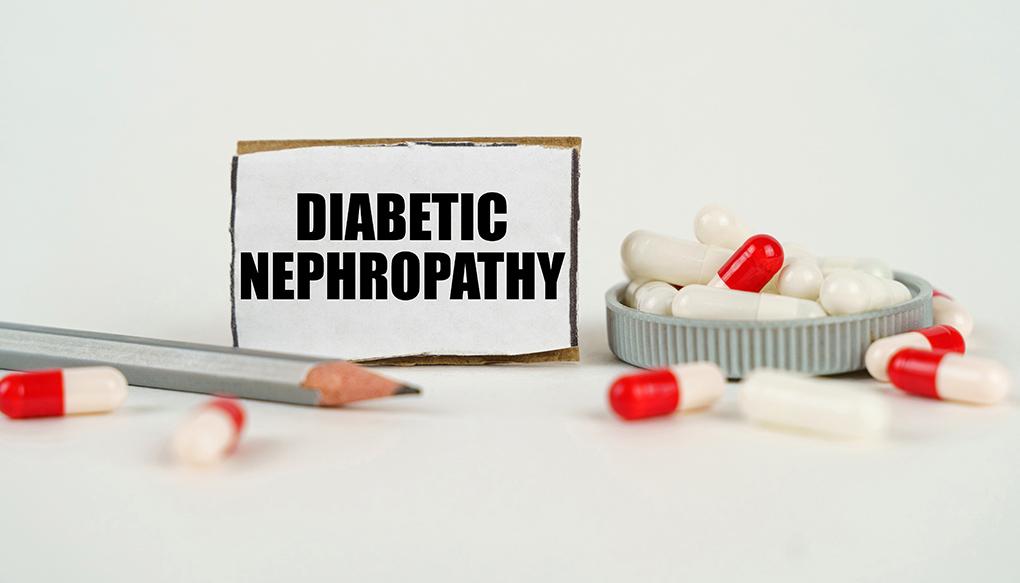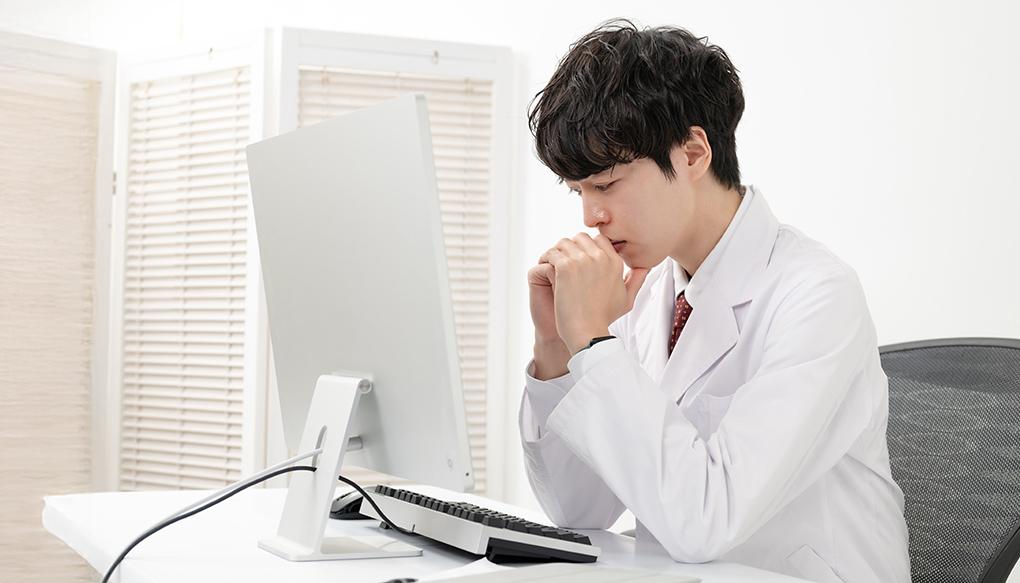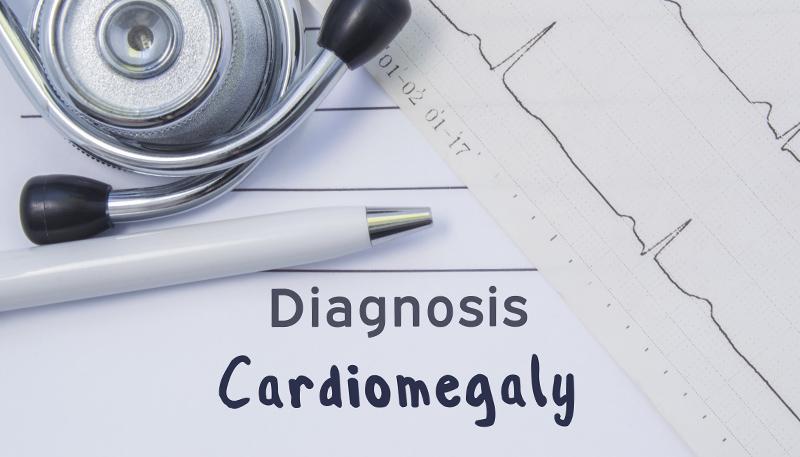慢性腎臓病の原因の一つとして知られる「糖尿病性腎症」は、社会の高齢化や生活習慣の欧米化などの影響で増加傾向にあります。また、透析治療を必要とする慢性腎臓病の原因の約40%を、糖尿病による腎臓病が占めることがわかっています*1。
慢性腎臓病や糖尿病性腎症を診察する機会は多いものの、定義や診断基準などを改めて確認したい先生方もいるのではないでしょうか。この記事では慢性腎臓病と糖尿病性腎症の関係、慢性腎臓病を診療する上でのポイントについて、腎臓専門医である筆者が経験を交えてお話しします。
※筆者個人の見解を含みます。診療にあたっては最新のガイドラインや治療指針、各種薬剤の添付文書などをご確認ください。

慢性腎臓病と糖尿病性腎症の違い
慢性腎臓病と糖尿病性腎症はどちらも腎機能の低下をきたすため、違いがわかりづらいかもしれません。結論から言うと、糖尿病性腎症は慢性腎臓病の一部に含まれます。
慢性腎臓病(CKD:chronic kidney disease)は、何らかの原因によって腎臓の機能低下が3カ月継続して起こっている"状態"を指します。そのため糖尿病性腎症だけでなく、高血圧による腎硬化症や高尿酸血症による腎機能障害など、多くの疾患が慢性腎臓病に含まれます。
一方の糖尿病性腎症(diabetic nephropathy)の定義は、「慢性的な高血糖状態に起因した腎臓構成細胞・組織障害と腎血行動態異常の結果生じる細小血管症」*2です。慢性腎臓病の原因疾患であることが多く、心血管疾患の発症リスクも上昇させることが明らかになっています*3。
慢性腎臓病が進行すると、患者さん自身の腎機能で余分な水分や老廃物を排出できなくなる「末期腎不全」の状態に陥るため、透析や腎移植などの腎代替療法が必要になります。糖尿病による腎機能障害は、透析を必要とする原因の第1位です(2023年)*1。
糖尿病性腎症の典型的な経過では、微量アルブミン尿から始まり、大量のアルブミン尿や蛋白尿を認めるようになった後に、腎機能低下が進むとされています。しかし、最近では治療薬の発展や高齢化などの影響で、糖尿病のある患者さんでもアルブミン尿や蛋白尿が軽度で、腎機能障害が進行するような非典型的な経過を辿る症例が増えてきていると言われています*4。
このような"非典型的な経過"を辿る症例は近年、「糖尿病関連腎臓病」(DKD:diabetic kidney disease)と定義するようになりました。日本においては当初、DKDの訳語は「糖尿病性腎臓病」とされていましたが、糖尿病性腎症との違いがわかりづらいという考えのもと、2023年に「糖尿病関連腎臓病」とすることが日本腎臓学会と日本糖尿病学会によって決められました。
つまり、糖尿病性腎症も糖尿病関連腎臓病も、慢性腎臓病に含まれます。
慢性腎臓病という概念が提唱された理由
一方の慢性腎臓病に関しては、疾患概念が定義される以前は「慢性腎不全」という言葉が使われていました。慢性腎不全は何らかの原因で腎機能が低下している状態を意味していましたが、腎機能低下の程度や専門医への紹介基準などは明確に定義されていませんでした。
医学研究が進み、腎機能障害は中等度であっても心血管疾患の発症リスクは上昇すると明らかになったことで、「慢性腎臓病」(CKD)という疾患概念が定義されました。腎機能障害を早期に発見し介入すれば、腎機能が悪化するスピードを抑えられる可能性があることから、診断基準や専門医への紹介基準も整理されました。
腎機能障害の悪化を抑えられれば、末期腎不全になって腎代替療法を必要とすることも少なくなり、患者さんの負担軽減だけでなく、医療費の削減にも貢献します。
2024年の報告によると、日本人の成人のおよそ5人に1人が慢性腎臓病と推計されています*5,6。疾患概念や診断基準、専門医への紹介基準などが明らかになったことで、専門医以外の先生にとっても慢性腎臓病の病態が身近になり、わかりやすくなったのではないかと思います。
慢性腎臓病の原因
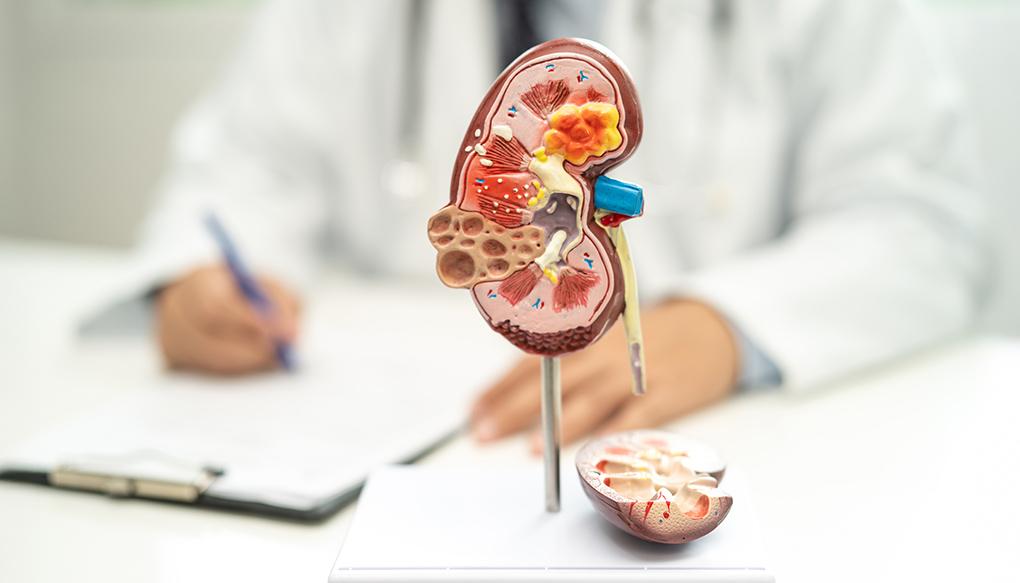
慢性腎臓病の原因を特定あるいは推定することは、治療方針を立てたり予後を推測したりする上で重要になります。病態の進行を遅らせるため、原疾患の治療が大切だからです。
慢性腎臓病の原因としては、糖尿病のほかに高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣病、IgA腎症や膜性腎症などの原発性糸球体疾患、多発性嚢胞腎のような遺伝性疾患、膠原病などが挙げられます。
原因疾患の特定には腎生検が必要です。しかし出血のリスクもあるため、実臨床では有益性と危険性を考慮し、個々の症例ごとに腎生検の適応があるか慎重に判断します。腎生検を施行せずに、臨床経過や既往歴などから原因疾患を推定することもあります。
慢性腎臓病の診断方法
慢性腎臓病は、「健康に影響を与える腎臓の構造や機能の異常が3カ月を超えて持続」する場合に診断します*6,7。具体的には、蛋白尿・アルブミン尿などの尿異常所見や画像・血液・病理診断で腎障害の存在が明らかな場合、GFR(糸球体濾過量)が60 mL/分/1.73m2未満の場合に、慢性腎臓病と考えます。
通常臨床では、DKDは30 mg/gCr以上のアルブミン尿とGFRの値から、DKD以外の慢性腎臓病では0.15 g/gCr以上の蛋白尿とGFRの値から、それぞれ診断します*6。
GFRは、18歳以上の場合は血清クレアチニン(Cr)値と年齢・性別から、日本人のGFR推算式(JSN eGFR)を使用し、推算GFR(eGFR:estimated GFR)を評価します(日本腎臓学会のwebサイトでeGFRが計算できるようになっています)。eGFRの数値によって、G1~G5の6段階の「GFR区分」(G3はaとbの2段階)に分けられ、eGFRの数値が低いほど腎機能が低いことを示します*6。
アルブミン尿・蛋白尿に関しては、それぞれA1~A3の3段階の区分に分けられます(A1は正常)。
最新のガイドラインに基づいて慢性腎臓病の重症度判定をした際には、原因検索の結果も併記することが推奨されています。具体的には以下のような記載をします。
【重症度判定の記載例】
- CKD G3aA2(DKD)
- CKD G3aA2(多発性嚢胞腎)
- CKD G3bA3(IgA腎症)
- CKD G4A3(巣状分節性糸球体硬化症)
慢性腎臓病を見つけるためのポイント

ここからは、慢性腎臓病を鑑別するためのポイントをいくつかご紹介します。
- eGFRを把握する
- アルブミン尿・蛋白尿を測定する
- 合併症や既往歴を確認する
- 内服薬を確認する
1.eGFRを把握する
たとえば、血液検査で「Cr 1.3 mg/dL」という数値を見たら、どのように考えると良いでしょうか。
先述した日本腎臓学会の「腎機能測定ツール」で、eGFRを計算してみましょう。
たとえば、30歳の男性であれば eGFR=54.9 mL/分/1.73m2となります。40歳の女性であれば37.3 mL/分/1.73m2、65歳男性では43.9 mL/分/1.73m2となります。3例はいずれもeGFR<60 mL/分/1.73m2未満のため、慢性腎臓病と診断されます。
血清Crの数値としてそれほど高くないように感じても、実際にeGFRを計算してみると、慢性腎臓病と診断される場合があります。
eGFRの数値に違いが生じるのは、血清Crが筋肉量を反映するためです。筋肉量が多いほど血清Cr値は高くなるため、一般に女性より男性、高齢者より若年者の方が、血清Cr値は少し高めになります。
そのため、寝たきりで筋肉量が低下している人、筋疾患・四肢欠損などがある人ではeGFRの過大評価を、逆にアスリートや運動習慣のある高齢者ではeGFRを過小評価してしまう可能性があり、注意が必要です。
2.アルブミン尿・蛋白尿を測定する
慢性腎臓病を診断するための重要な要素として「アルブミン尿」や「蛋白尿」があります。先述のとおり、DKDであればアルブミン尿、DKD以外の慢性腎臓病であれば蛋白尿の持続が診断基準に含まれています。
初期の腎機能障害に気付くために、アルブミン尿・蛋白尿の測定は有用とされています。血清Crが上昇する前に検出される場合も多いからです。
アルブミン尿・蛋白尿を検査する方法は3つあります。
- 1日分の尿を溜め(24時間蓄尿)、尿中のアルブミン量・蛋白量を測定する方法
- スポット尿中のアルブミン量・蛋白量を測定する方法(外来でもすぐに検査が可能)
- 試験紙法(健診でスクリーニングのために使用されることが多い)
蛋白尿が多いほど腎機能障害が進行すること、心血管疾患による死亡リスクが上がることが明らかになっており、定期的な測定が重要です。
3.合併症や既往歴を確認する
先述のとおり、高血圧や糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、肥満などの生活習慣病は、腎機能障害を引き起こしやすい疾患として知られています。また、膠原病や感染症、がん、先天性疾患なども腎機能障害の原因となることがあります。
合併症や既往歴を確認し、慢性腎臓病の原因になるものがないか検討してみてください。
4.内服薬を確認する
薬によって腎機能障害が引き起こされることを薬剤性腎障害と言います。腎機能障害の原因を考察する上で、内服薬の確認をすることが大切です。
原因薬剤としてよく知られているものに、解熱鎮痛薬(NSAIDs)、抗菌薬、造影剤、抗がん剤などがあります。また、サプリメントの中にも腎機能障害を引き起こすものがあります。
まとめ
慢性腎臓病や糖尿病性腎症は、どの科でも診る機会のあるコモンディジーズです。しかし、診断の仕方や原因疾患の推定など難しく感じることがあるかもしれません。今回解説したようなポイントが、先生方の診療の一助になれば幸いです。
わが国の慢性透析療法の現況 2023年末の慢性透析患者に関する集計|日本透析医学会
└第3章 図17 導入患者 原疾患割合の推移,1983-2023(*1)
糖尿病診療ガイドライン2024|日本糖尿病学会(*2)和田隆志:糖尿病性腎症:最近の進歩.日本内科学会雑誌 105(9):1870-1876,2016(*3)
岡田浩一:DKDの疾患概念と腎臓専門医への紹介基準.日本内科学会雑誌 108(5):901-906,2019(*4)
令和5年度 JSN公的研究班研究成果合同発表会|日本腎臓学会(*5)
日本腎臓学会 編:CKD診療ガイド2024.東京医学社,2024(日本腎臓学会誌 67(1):1-178,2025)(*6)
日本腎臓学会 編:エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023.東京医学社,2023(*7)
腎臓の病気について調べる 4.急性腎障害と慢性腎臓病|日本腎臓学会
腎臓の病気について調べる 6.全身性疾患に伴う腎障害|日本腎臓学会
松井勝・斎藤能彦:心腎連関の新展開.日本内科学会雑誌 106(5)911-918,2017
乳原善文:腎生検の適応と実際.日本内科学会雑誌 109(5):881-885,2020