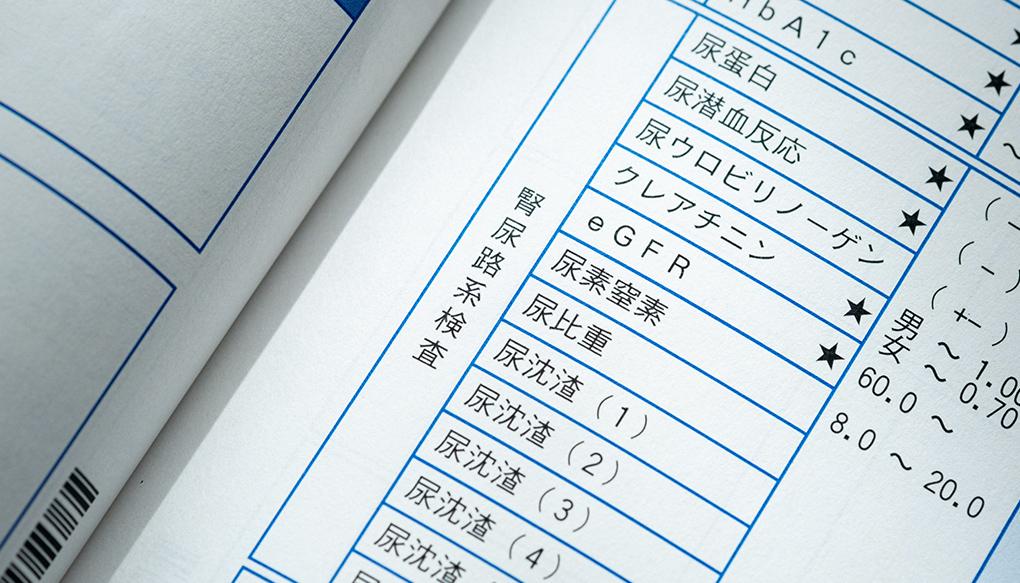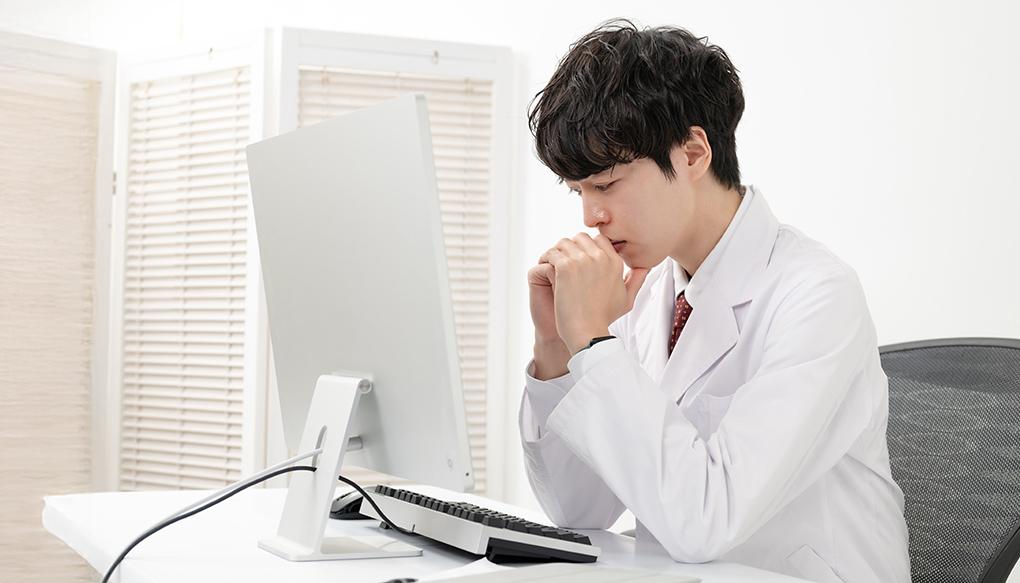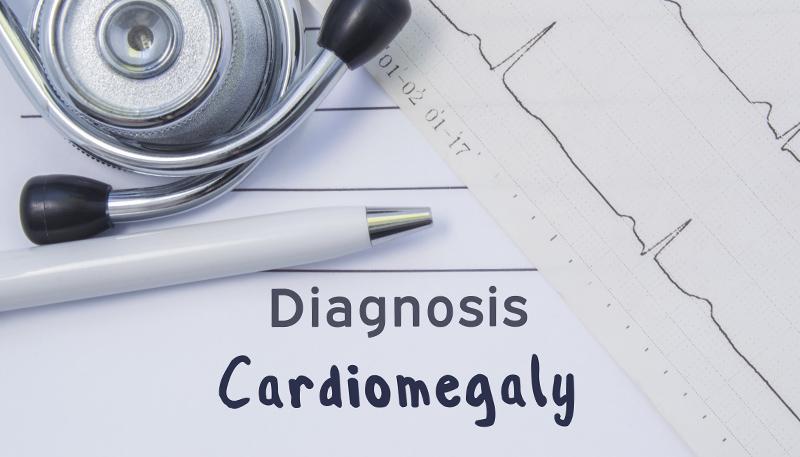社会の高齢化や生活習慣の欧米化、医療技術の進歩といった影響で、糖尿病による腎機能障害を有する患者数は増加傾向にあります。近年、典型的な経過をたどらないものを「糖尿病関連腎臓病」(DKD)と呼ぶようになったことで、従来の「糖尿病性腎症」との違いがわかりづらいと感じている先生方もいるかもしれません。
この記事では糖尿病関連腎臓病の定義や糖尿病性腎症との違いについて、腎臓内科医である筆者が経験を交えてお話しします。
※筆者個人の見解を含みます。診療にあたっては最新のガイドラインや治療指針、各種薬剤の添付文書などをご確認ください。

糖尿病関連腎臓病(DKD)とは
糖尿病による腎機能障害である「糖尿病性腎症」(DN:diabetic nephropathy)は、尿所見が微量アルブミン尿から蛋白尿へと進行し、腎機能が徐々に低下するのが典型的な臨床像でした。
しかし、最近は社会の高齢化や医療技術の発展により、蛋白尿が軽度でも急激に腎機能が低下する、あるいは蛋白尿を認めても腎機能がさほど低下しないなど、病態の多様化が指摘されています。
糖尿病性腎症の典型的な臨床経過を辿らないものの、糖尿病による腎機能障害を認めるものが「糖尿病関連腎臓病」(DKD:diabetic kidney disease)です。欧米では日本に先駆けてDKDの疾患概念が浸透しており、近年は日本腎臓学会と日本糖尿病学会がDKDの普及に向けて尽力してきました。
両学会は2017年に「STOP-DKD宣言」を採択し、DKDに関する調査や治療法の開発に取り組んでいます。
DKDの和訳は当初、「糖尿病関連腎臓病」ではなく「糖尿病性腎臓病」と表現されることもありました。しかし糖尿病性腎症との違いがわかりづらいため、2023年に「糖尿病関連腎臓病」という名称に統一されています。
岡田浩一:DKDの疾患概念と腎臓専門医への紹介基準.日本内科学会雑誌 108(5):901-906,2019
糖尿病性腎臓病への挑戦 糖尿病性腎臓病克服宣言:STOP-DKD|日本腎臓学会
DKD(Diabetic Kidney disease)の訳語について|日本糖尿病学会
糖尿病関連腎臓病(DKD)と糖尿病性腎症(DN)の違い
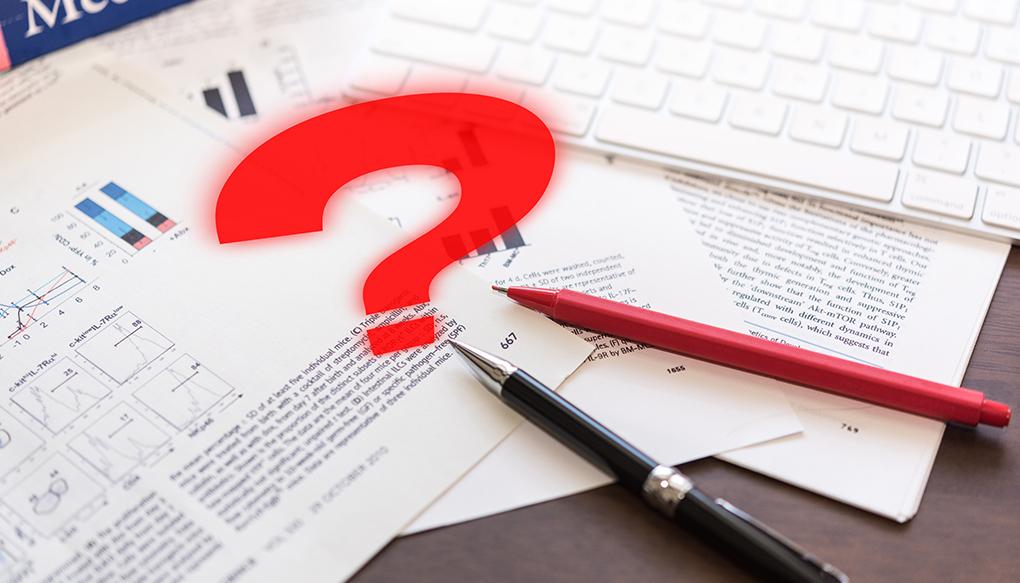
糖尿病性腎症の典型的な経過では、糖尿病を発症してから約5~10年で微量アルブミン尿を、その後顕性タンパク尿・持続的タンパク尿を認めるようになり、最終的には腎機能障害が進んで末期腎不全に至ります。
末期腎不全になると、血液透析・腹膜透析・腎移植などの腎代替療法が必要です(糖尿病性腎症は、日本における透析導入疾患の第1位として知られています(2023年)*1)。
しかし先述のとおり、近年は典型的な臨床経過を呈する糖尿病性腎症だけでなく、社会の高齢化や、レニン-アンジオテンシン系阻害薬などの治療薬の発展の影響で、蛋白尿が軽度でも腎機能障害が進行するような、非典型的な経過を辿る症例が増えていると言われています。
そのような非典型的な経過を辿る症例も加味して、DKDの和訳にあたる「糖尿病関連腎臓病」が日本腎臓学会と日本糖尿病学会において定義されました。
糖尿病に伴う腎機能障害の経過の多様性をふまえて、従来の糖尿病性腎症の病期分類も2023年に改訂されています。たとえば、第4期(腎不全期)ではアルブミン尿や蛋白尿の有無は問わず、GFRが30未満の場合に診断されるようになりました。「糖尿病性腎症は必ずしも第1期から順次第5期まで進行するものではない」という注釈も付けられています*2。
まとめると、糖尿病関連腎臓病は多様な臨床経過を含む広い概念であり、糖尿病性腎症に限らず、糖尿病に関連するさまざまな腎疾患を含みます。「古典的(典型的)な糖尿病性腎症を内包する概念」と考えるとわかりやすいでしょう。
糖尿病関連腎臓病(DKD)の専門医への紹介基準
ここまで見てきたような背景から、近年はどの診療科でも、糖尿病関連腎臓病の患者さんを診る機会が増えています。
専門医が近くにいなかったり、紹介のハードルが高かったりする地域もあるとは思いますが、どの程度の病態で専門医へ紹介したら良いかをおさえておくと安心です。
慢性腎臓病の腎臓専門医・専門医療機関への紹介については、日本腎臓学会が基準を提示しています。ガイドラインの内容をふまえ、要点を文章化してみました。
- まず、アルブミン尿・蛋白尿が正常であっても、40歳未満であれば「GFR 60 mL/分/1.73m2未満」で専門医に紹介
- 微量アルブミン尿(30~299 mg/gCr)、軽度蛋白尿(0.15~0.49 g/gCr)の場合は、GFR 60 mL/分/1.73m2未満であれば紹介、血尿がある場合はGFR値にかかわらず紹介
- 顕性アルブミン尿(300 mg/gCr以上)、高度蛋白尿(0.5 g/gCr以上)の場合は、GFR値にかかわらず紹介
糖尿病関連腎臓病についても、上記を紹介の基準としましょう。
ただしガイドラインでは、この基準が「全国統一的なものではない」*3こと、かかりつけ医の判断で「これらの紹介基準にとらわれずに腎臓専門医・専門医療機関に紹介することは極めて重要」*3とも述べています。
糖尿病関連腎臓病(DKD)の治療・管理

糖尿病専門医や腎臓専門医でなくても、生活習慣の改善や血圧の管理などによって腎機能障害の進行を抑えることができます。ポイントを4つ、見ていきましょう。
1.生活習慣を改善する
生活習慣の改善は、腎臓への負担の軽減につながります。肥満がある場合はBMI<25になるように減量し、過剰なアルコールの摂取を避けると良いと言われています*4。禁煙や適度な運動、バランスの良い食事もあわせて推奨しましょう。
適正な飲酒量は、アルコール量で男性20~30 mL/日以下、日本酒だと1合です。女性は男性に比べて少なく、アルコール量で10~20 mL/日以下とされています*4。
糖尿病の合併症として増殖性網膜症がある場合や、虚血性心疾患の急性期などでは、激しい運動は病状を悪化させる可能性があるため推奨されません。しかし病状が安定しているときには、1週間に150分程度の運動が推奨されています*4,5。
ただし、運動習慣がなかった人が急に運動をすると足腰を痛めたり、長く続かなかったりするため、個人に合った運動方法や運動量を提案できると良いでしょう。1駅分歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、少しずつでも身体を動かすように提案すると良いかもしれません。
2.血糖値を適正に保つ
高血糖の持続は糖尿病関連腎臓病だけでなく、合併症の発症・進行にも関与するため、血糖値を適切に保つことが大切です。日本糖尿病学会は、合併症予防のためのHbA1cの目標値を7.0%未満としていますが、年齢や罹病期間、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮した個別設定が推奨されています(たとえば、血糖コントロールが難しい場合や高齢の場合、HbA1cは8.0%未満とすることもあります)*6。
SGLT2阻害薬は、腎予後の改善と心血管イベント発症抑制効果があることが認められています。ただし、投与開始後に一時的なGFRの低下を認めるため、開始2週間~数カ月程度はGFRの評価が必要です*3。
3.血圧を適正に保つ
高血圧は糖尿病関連腎臓病を進行させる大きな要因として知られており、血圧を適正に保つことが大切です。アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬またはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)は、早期腎臓病の発症や腎機能障害の進行を有意に抑制すると言われています。
降圧目標は130/80 mmHg未満(診察室血圧)となっており*7、レニン-アンジオテンシン系阻害薬を第一選択とし、カルシウム拮抗薬や利尿薬を適宜併用します*3。
4.脂質代謝異常を管理する
脂質代謝異常は糖尿病関連腎臓病の進行や心血管疾患発症のリスクになるため、血中のLDLコレステロールや中性脂肪などの値を適切に保つことも大切です。
心血管疾患の既往がない場合には、以下を目標にします。
- LDLコレステロール値<120 mg/dL
- 中性脂肪(空腹時)<150 mg/dL
- HDLコレステロール値≧40 mg/dL
https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/03_230210.pdf(2025年9月24日閲覧)
心血管疾患などの既往がある場合は、中性脂肪とHDLコレステロールの値は上記と同様ですが、LDLコレステロール値を100 mg/dL未満に保つようにします*8。
まとめ
糖尿病関連腎臓病は、どの科でも診る機会のあるコモンディジーズの一つと言えます。進行を阻止するためには医師・看護師・管理栄養士などの各職種が連携し、治療にかかわることが大切です。最新の疾患概念をおさえ、日々の診療や管理に加えて適切に専門医に紹介できるよう、今回解説したポイントが先生方の診療の一助になれば幸いです。
わが国の慢性透析療法の現況 2023年末の慢性透析患者に関する集計|日本透析医学会
└第3章 図17 導入患者 原疾患割合の推移,1983-2023(*1)
糖尿病性腎症合同委員会・糖尿病性腎症病期分類改訂ワーキンググループ:糖尿病性腎症病期分類 2023 の策定.糖尿病 66(11):797-805,2023(*2)日本腎臓学会 編:CKD診療ガイド2024.東京医学社,2024(日本腎臓学会誌 67(1):1-178,2025)(*3)
古家大祐:糖尿病性腎臓病の診断と治療のアップデート.日本内科学会雑誌 112(3):432-437,2022(*4)
山内敏正ほか(日本糖尿病学会コンセンサスステートメント策定に関する委員会):糖尿病患者の栄養食事指導―エネルギー・炭水化物・タンパク質摂取量と栄養食事指導―.糖尿病 63(3):91-109,2020
日本糖尿病学会:糖尿病診療ガイドライン2024.南江堂,2024 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について|日本糖尿病学会(*6)
日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会 編:高血圧管理・治療ガイドライン2025.ライフサイエンス出版,2025(*7)
日本動脈硬化学会:動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版.西村書店,2022