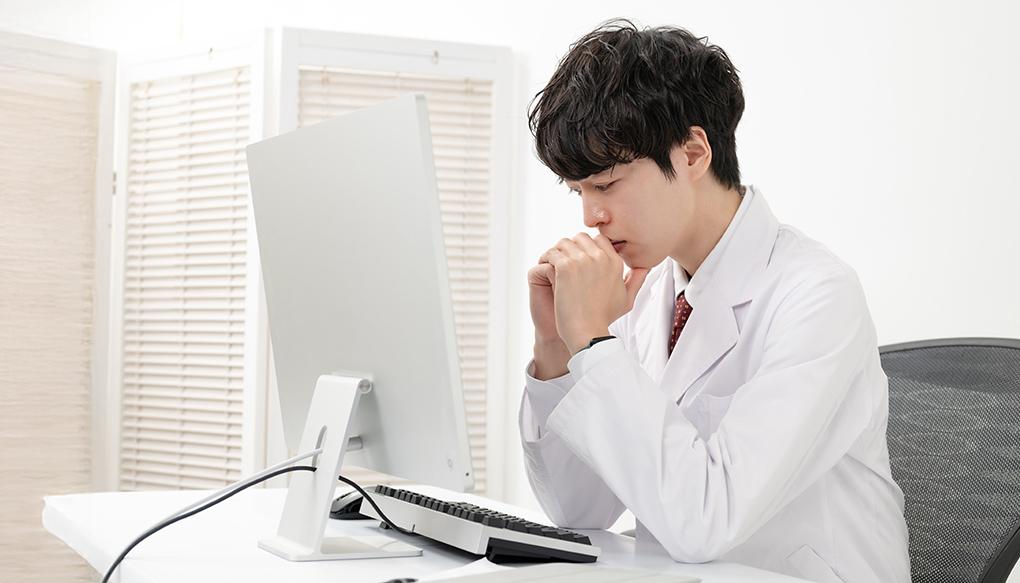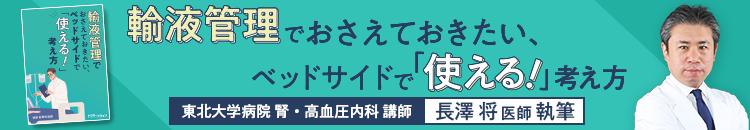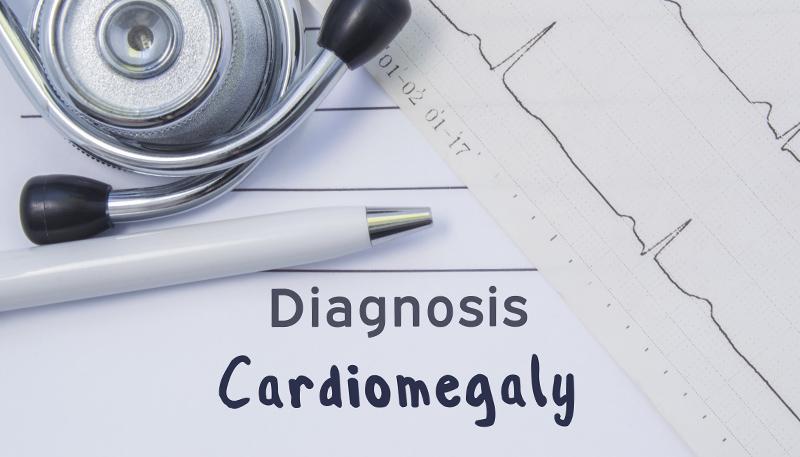「教科書どおりの知識は頭にあるけれど、いざ患者さんを目の前にすると、輸液をどのようにオーダーすべきか迷ってしまう」
「脱水や浮腫など、患者さんの体液バランス評価にいまひとつ自信が持てないことがある」
「低Na血症、高K血症といった電解質異常への具体的な対応に迷ってしまう」
「心機能や腎機能が低下した患者さんに適切に対応できているか不安になる」
日々の診療や病棟管理にあたっていると、"知っている"ことと"実践できる"ことの挟間で、このようなもどかしさを感じる場面もあるのではないでしょうか。
今回は、腎臓専門医である長澤将先生に、ベッドサイドで"使える"輸液管理の考え方を患者さんの病態変化に即した視点で解説いただきました。先生方がより自信を持って診療にあたるための一助となるよう、無料の音声解説とPDF資料をご用意しております。
このページでは急性腎障害(AKI)と低Na血症に対する輸液戦略について、長澤先生の音声解説をお届けします。知識と実践のギャップを埋める、具体的な思考プロセスの学習にお役立てください。

急性腎障害(AKI)
「Crの上昇や、尿量の低下が気になると思うのですが、それ自体はあまり臨床上の問題は起こしませんよね。
臨床上問題を起こすのは、Naの貯留による溢水、Kの貯留による不整脈、この2つが問題になることが多いわけです。」
<続きは音声でご確認ください>
低Na血症
「低Na血症、これはポイントは、あくまでNaと水の比なんです。これを分かっていただければと良いと。
そこで体液量の問題が入ってくると。要するに、体液量減少の時は、ちょっとラーメンのスープ少な目だし、体液量増加の時にはラーメンちょっと多いですよという話になってくると。」
<続きは音声でご確認ください>
◆◆◆ この音声とあわせて、長澤先生が執筆されたPDF資料『輸液管理でおさえておきたい、ベッドサイドで"使える!"考え方』も無料でご提供中です。以下のフォームよりお申し込みいただくことで、ダウンロード用URLをお受け取りいただけます。 【無料PDF】『輸液管理でおさえておきたい、ベッドサイドで"使える!"考え方』お申し込みフォーム ※ご応募いただいた方には、人材紹介サービスにおける各種情報をはじめ、仕事や生活に役立つ医師コラムなどをご提供するため、メールマガジンをお送りさせていただきます。 【注意事項】
●当コンテンツは医師向けの内容となっているため、医師ではない方のお申し込みはご遠慮ください。
●当コンテンツの二次利用やSNSでの拡散、他の方への提供は固く禁止いたします。発覚した場合は厳正に対処させていただきます。
●予告なく音声コンテンツを削除する可能性がございます。