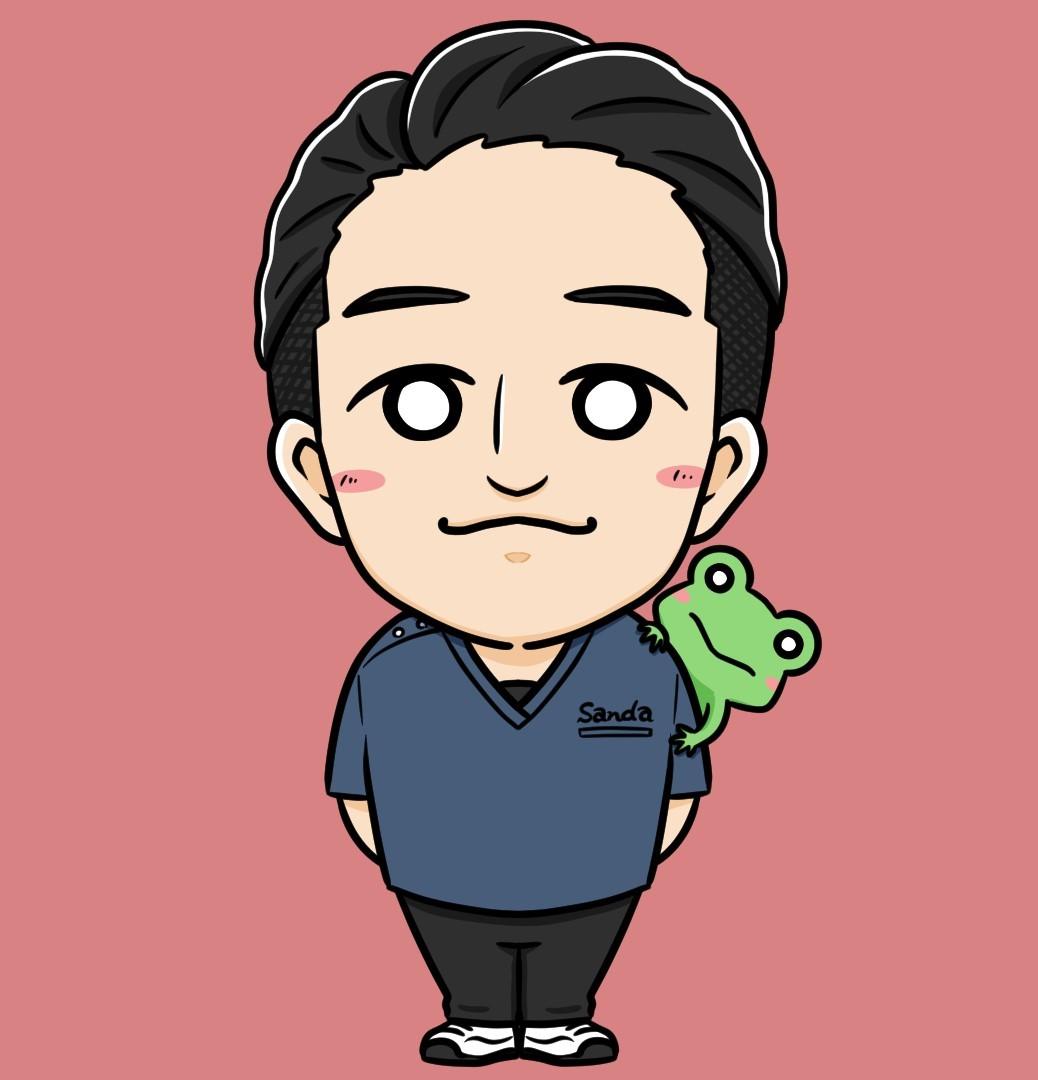医師として働いていると、臨床・研究・教育などで多忙な日常を送ることが多いと思います。その中で「今とは違う形で活動できないか」「もっと社会のためにできることはないか」と考えたことがある先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような医師にとって、ボランティア活動は一つの選択肢になるかもしれません。この記事では、医師が行うボランティア活動の例や、仕事との境界、参加する上で考慮したいことなど、ともに考えていきたいと思います。
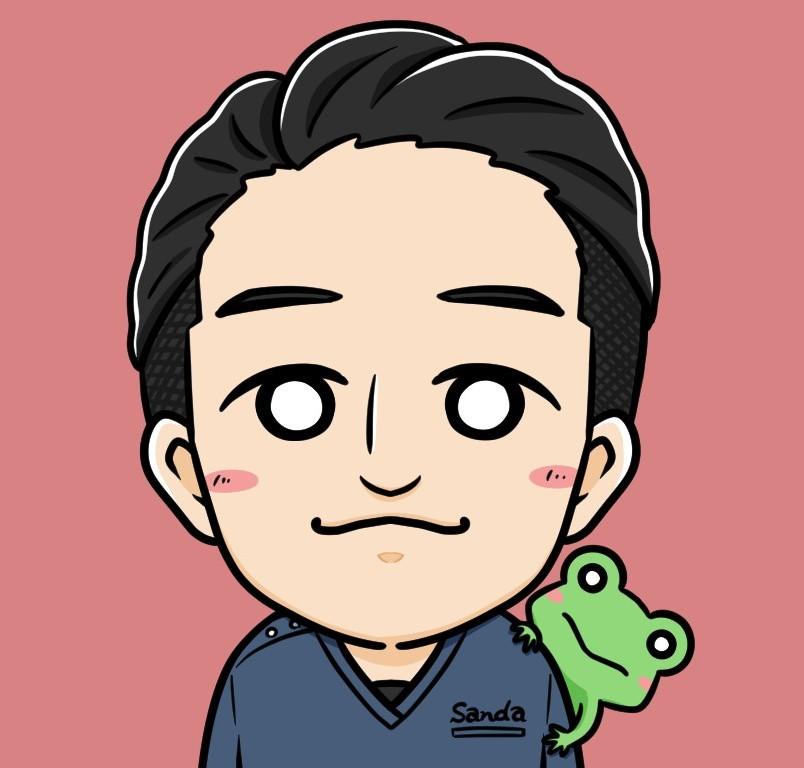
執筆者:三田 大介
医師のボランティア活動とは
医師がボランティア活動ををすると一口に言っても、その内容や実態はさまざまです。医師として専門性を発揮できるものもあれば、医業とはあまり関連のない分野で活動している方々もいます。
そもそも「ボランティア」とは何か、基本的な考え方から見ていきましょう。
そもそも「ボランティア」とは?

「ボランティア」(volunteer)という言葉は、一般的には英語の「志願兵」が語源とされていますが、ラテン語で「自由意志」を意味する「ボランタール」(voluntaries)に由来するという説もあります。
ボランティアという言葉に明確な定義はありませんが、たとえばボランティア活動推進国際協議会(IAVE)による『世界ボランティア宣言』(The Universal Declaration on Volunteering)では、以下のように示されています。
【世界ボランティア宣言(1990年、ボランティア活動推進国際競技会総会)】
ボランティアとは「個人が自発的に決意・選択するものであり、人間の持っている潜在的能力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動である。」
https://www.nier.go.jp/jissen/book/r04/pdf/r04volunteer_base_all.pdf(2025年7月15日閲覧)
ボランティアの中には「プロボノ」(pro bono)という言葉もあり、職業専門性やスキルを活かして取り組む活動を指します。ラテン語の"pro bono publico"の略で、「公衆の善のために」「公共の利益のために」(for the public good)といった意味を持っています。つまり、医師という職業を活かしてボランティア活動をする場合はプロボノと言う方が近いかもしれません。
活動に対する報酬を気にする人もいるのではないでしょうか。ボランティアの語源から考えると無償が基本ではありますが、交通費などの実費や、専門的な協力に対する謝金が支払われることもあります。このような活動は「有償ボランティア」と呼ばれています。
令和4年度 ボランティアに関する基礎資料|文部科学省 国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター
平成23年版 情報通信白書 第2部 特集 共生型ネット社会の実現に向けて|総務省
「世界ボランティア宣言」日本語訳(The Universal Declaration on Volunteering)|NPO法人JAVE(ボランティア活動推進国際協議会 日本)
医師のボランティア活動の例

医師のボランティア活動には、さまざまな形があります。特定の団体(NPOなど)に所属するのか、個人やチームで活動するのか、定期的なのか非常時なのか、といった具合です。
国内に限らず海外で活動するものもありますので、自身の生活・専門性・想いに沿った活動を考えられると良いのではないでしょうか。
ここでは、いくつかの事例を紹介していきます。
災害時の医療支援
地震や台風などの大規模災害時には、医療活動が止まったり、人や資源が適切に分配できなくなったりすることで、平時以上に人手が必要になります。そのようなときに活躍するのが、被災地でボランティア活動を展開する医療チームです。DMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日本医師会災害医療チーム)、DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)などがあります。
災害大国・日本の医師が知っておきたい災害医療の基本
医師が「DMAT」になるには?活動内容や登録要件
JMAT(日本医師会災害医療チーム)とは?どんな活動をしている?
DPATとは?DMATとの違いや活動実績について解説
DICT(災害時感染制御支援チーム)とは?活動内容や医師としての参加条件を紹介
DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)とは?活動内容や参加条件【医師向け】
JRAT(日本災害リハビリテーション支援協会)とは?活動内容や登録条件を紹介
医療アクセスが悪い人への支援
災害時に限らず、平時より医療アクセスが悪い人々もいます。たとえば「無医地域」「へき地」では、巡回診療や医師派遣といった形で医療サービスを届けることが求められます。社会的意義が大きな活動であり、多くは有償です。
医療アクセスが良好な地域でも、経済的な事情で医療を安全に受けることができない人々もいます。そのような人への健康相談・生活支援も、医師がボランティアとして参加できる活動の一つです。
地域の健康教育・啓発活動への参加
より身近に参加できるボランティア活動もあります。たとえば、地域住民向けの公開講座・講演、健康相談は、医師として専門性を発揮できるボランティア活動です。特定の疾患を持つ患者さんや家族が集うコミュニティ(患者会・患者サロンなど)への参加も、医師としてニーズに応えることができる活動と言えます。
ほかに、スポーツ業界にも医師のニーズがあります。チームドクターに近い立場で部活動や地域チームのサポート、大会での救護・運営補助などに参加できるケースもあります。
その他
ここまでは医師という職業専門性を活かせる活動を挙げてきましたが、そうではない活動ももちろん可能です。たとえば、街づくりや地域安全の活動、自然保護や環境保全、医療と異なる分野での国際協力などがあります。
医師という立場から離れた活動だからこそ、より具体的な目的・目標が求められるでしょうし、実際に活動する際には想いや能力が試されます。ボランティア活動を完遂できた際には普段の臨床とは異なる充実感が得られるでしょう。
仕事とボランティア活動の境界は?
医師という職業を活かすボランティア活動は、その専門性の高さから、仕事との区別が難しい場面もあります。先述したDMATやDHEATのように、所属している病院・自治体から派遣される活動や、病院が企画する市民公開講座・講演会などは、業務の内容や指示系統から、本業の一環とみなされることが多いでしょう。
一方で、個人として、もしくは外部の団体を通じて活動する場合は、仕事との区別はより明確になるでしょう。ここで確認しておきたいのは、ボランティア活動は無償が原則であるということです。
しかし先述のとおり、社会的なニーズや人材確保の点から、有償ボランティアとして謝金が払われることもあります。有償ボランティアの場合、所属先の就業規則に違反していないか、確認しなければなりません。活動する前に、内容や期間、謝金の有無など、活動条件を必ず確認しましょう。
謝金を受け取れば、確定申告が必要となることもあります。万が一ボランティア活動中に事故や医療過誤が起きた場合、加入している保険がカバーしてくれるのか、といった確認・備えも重要です。
医師の副業について現役医師が解説。自分らしく働く上でおすすめの仕事や注意点とは 研修医はアルバイトできる?専攻医で始めるおすすめの仕事や注意点とは 【改定版】確定申告が必要な医師とは?令和7年税制改正の影響もFPが解説
医師に関連するボランティア団体
ここでは、医師が活躍しているボランティア団体の例を、いくつか紹介します。ごく一部の団体ですので、ボランティアに興味を持った方は、ほかの団体についてもぜひ調査してみてください。
国境なき医師団
「国境なき医師団」は、紛争や自然災害、貧困などにより危機に直面する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届ける、民間の国際団体です*1。活動をより効果的にするため、参加者には給与や日当、各種保険や住居など、さまざまなサポートが用意されます。
医師は、通年で募集されています。専門科によって多少異なりますが、3~6ヵ月からの派遣が多いようです。専門医資格や教育経験、英語またはフランス語などの語学力やスキルが求められます。
公式サイトには医師による活動記録が多数掲載されており、現地の状況や活動の実際について深く知ることができます。
ジャパンハート
「ジャパンハート」は、「すべての人が、生まれてきて良かったと思える世界を実現する。」*2というビジョンのもと、医療支援を中心に活動する「日本発祥の国際医療NGO」です*3。国内外の医師不足地域や被災地での支援、貧困や難病に苦しむ小児医療などに取り組んでいます。
医師の募集は、国内外で行われています。「海外メディカルチーム」では、臨床研修を修了していることと(専門は不問)、事前に短期プログラムに参加することが必要条件です。
短期プログラムは2種類あり、現場の見学を含む2泊3日の「体験コース」と、数日~1週間ほど診療活動に参加する「短期ボランティアコース」があります。国内では、小児がんの子どもたちを支援するプロジェクトや災害医療支援において、医師ボランティアを募集しています(2025年7月現在)。
Vision / Mission / Value|ジャパンハート(Japan Heart)(*2)
団体概要|ジャパンハート(Japan Heart)(*3)
医師として参加する|ジャパンハート(Japan Heart)
災害人道医療支援会(HuMA)
災害人道医療支援会(HuMA:Humanitarian Medical Assistance)は、災害医療を中心に活動している特定非営利活動法人です。被災地で医療支援を行う点ではほかの団体と共通しますが、復興支援・地域開発も視野に入れた活動を展開しています。
特徴的なのは、災害医療に関する人材育成・研修を積極的に行っていることでしょう。行政機関や企業からの依頼で実施する研修もあります。医療従事者だけでなく、災害ボランティアに携わる幅広い市民に対して学びの機会を提供しています。
医師がボランティア活動をしたいと思ったら

医師がボランティア活動をしたいと思ったときには、どのようなことを意識すると良いでしょうか。
まずは、「なぜボランティア活動をしたいのか」「ボランティア活動を通して何を得たいのか」を、深く考えてみることが大切です。ボランティア活動は、誰かに喜ばれたり、社会的なやりがいを感じたりすることのできる機会です。通常診療では得られない多様な視点やスキルを獲得することもできるかもしれません。
しかし仕事に加えてさらなる時間・体力的な負担がかかる可能性もあり、やり抜くためには強い意思が必要と言えます。
目標や目的を確認できたら、次は「情報収集と計画」です。活動内容や活動場所から、自分の目的や想いに沿う活動をしている団体はないか、調査してみるのが良いでしょう。先述のとおり、活動条件が本業の就業規則に抵触しないか確認することも忘れないようにしましょう。
自身の現在の働き方や生活において、現実的にどのような活動がどの程度できるのか確認しつつ、準備していくことが重要です。疑問や迷いがあれば、ボランティア団体や、実際に活動している人に話を聞く機会を探れると良いでしょう。
まとめ
医師によるボランティア活動は専門性が高く、社会的意義も大きいと言えます。自身にとっても、新たなスキルや視点が得られるという点で、人生を豊かなものにすることでしょう。
一方で、仕事との両立を実現できるかどうかや、活動条件・契約面など、気持ちだけではどうにもならないこともあるかもしれません。医師としてどう働きたいか、ボランティア活動をする場合はそれを通して何を得たいのかを自問し、取り組んでいきましょう。