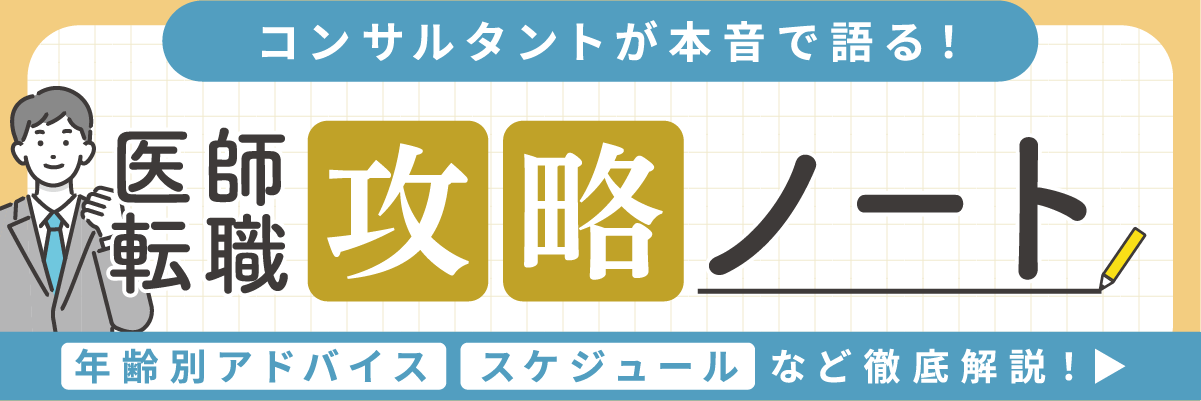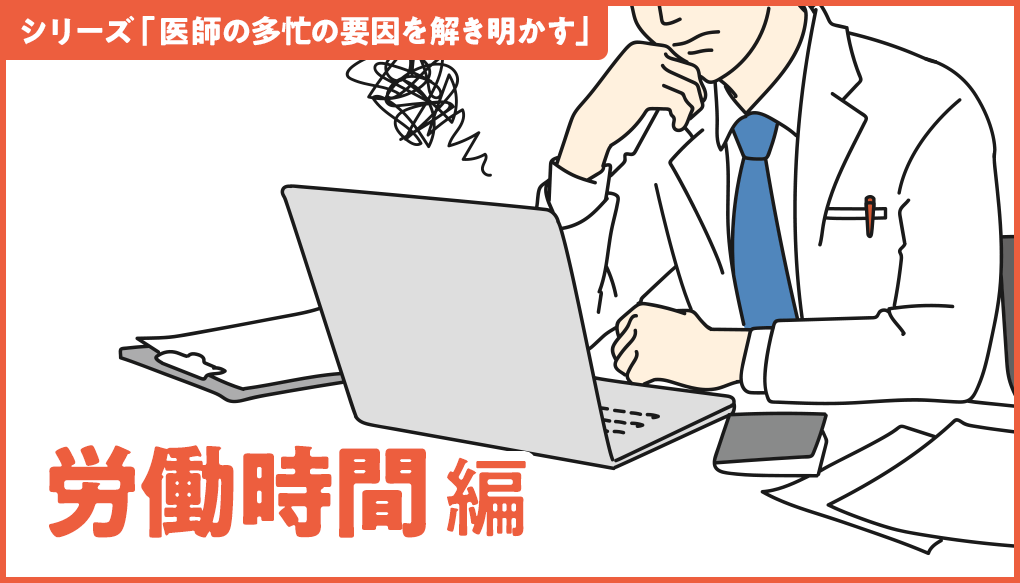複数回の転職を経験している先生の中には、「転職回数が多いと採用で不利になるのではないか」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
確かに、転職回数が多いと採用担当者に懸念を持たれるケースもありますが、一方で豊富な経験と高い適応力の証明として評価される場合もあります。重要なのは、転職回数の多さをネガティブに捉えるのではなく、それぞれの転職で得た経験や成長をいかにアピールできるかという点です。
本記事では、「採用担当者が転職回数の多い医師に対してどのような視点を持っているのか」について、実際に採用担当者の生の声を聞いている弊社のコンサルタントからの話も含めながら解説しています。「転職回数を強みに変える方法」や「効果的な履歴書・職務経歴書の書き方」も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
医師の転職回数は多くても不利にはなりにくい

医師の転職市場では、転職回数の多さが必ずしも不利な要素とは捉えられない傾向にあります。医師不足が深刻化している医療機関においては、転職回数よりも即戦力としての能力や人柄を重視する採用担当者が多いとされるためです。豊富な経験を持つ医師であれば、転職回数が多くても高く評価される可能性があります。
まずは転職回数について、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- 医師の転職回数が多いと見なされる目安
- 採用担当者が回数以上に注目しているポイント
医師の転職回数が多いと見なされる目安
転職回数に関する明確な基準は存在しませんが、常勤の場合一般的には4〜5回を超えると「やや多い」と見られる傾向があります。ただし、これはあくまで目安であり、回数そのものが不利に直結するわけではありません。むしろ、それぞれの転職に納得できる理由があり、一貫したキャリア形成につながっていれば、プラスに評価されるケースも少なくありません。
なお、厚生労働省「転職者実態調査(令和2年)」の結果から見ると、一般の会社員は生涯で2〜3回程度の転職を経験するケースが多いと考えられます。一方、医師は医局人事による異動や専門性を深めるための転職が比較的多く、30代の段階で複数回の転職経験を持つケースも珍しくありません。そのため、一般の会社員と同じ基準で判断されるわけではない点に留意が必要です。
採用担当者が回数以上に注目しているポイント
転職回数そのものよりも、採用担当者が注目しているのは以下のような点です。
- 経験や成長
- 適応力
- 転職理由の一貫性
中でも特に注目されるのは、経験や成長です。採用担当者は、「職場ごとにどのような役割を担い、何を学び、どう成長したか」を具体的に知りたいと考えています。「それぞれの職場で得た知見が今どう活きているか」を具体的に説明することで、評価につながる可能性があります。
次に重視されるのが適応力です。医療現場はスタッフや患者さまとの信頼関係が欠かせないため、新しい職場にスムーズに馴染めるかどうかは大きなポイントになります。こうした点から見ても、採用担当者の不安を解消するには適応力の高さをアピールすることが必要だと言えます。
そしてもう一つ大切なのが転職理由の一貫性です。転職のたびに理由がバラバラだと、場当たり的に動いている印象を与えてしまいます。「キャリアアップのために専門性を高めたい」「家庭の事情で働き方を見直したい」といった筋の通った理由であれば、理解を得やすくなります。つまり、転職歴をポジティブに見てもらうには、自分のキャリアプランとその時々の転職理由をつなげて説明できるかどうかが鍵となるのです。
転職回数が多い医師の強み・アピールポイント

明確なキャリアプランや考えに基づいて転職をしている場合、転職回数は必ずしもマイナス要素にはなりません。むしろ、その過程で得た経験や視野の広さが評価されることもあります。では、転職を重ねた先生がどのようにアピールが可能なのか、以下に分けて見ていきましょう。
- 医療に関する幅広い知識と経験がある
- 変化への高い適応能力がある
- 自身のキャリアに明確なビジョンを持っている
医療に関する幅広い知識と経験がある
異なる医療機関での勤務を通じて、多様な症例や治療方法に触れる機会を得られていると捉えられるのは、転職回数が多い先生の強みです。各施設の特色や得意分野での経験は、総合的な診療能力の向上につながっている可能性があります。特に地域医療や総合診療の現場では、このような幅広い知識と経験が強みとして重宝されるでしょう。
変化への高い適応能力がある
複数の医療機関での勤務経験は、多様な環境や文化に順応する力を培います。そのため、新しい職場にもスムーズに馴染みやすく、即戦力として評価される可能性が高いでしょう。組織の方針や運営体制の違いにも柔軟に対応できる経験があることは、転職の際に大きな強みになります。
また、診療システムの変更や新しい治療法の導入など、変化の多い医療現場でも柔軟に対応できる姿勢は、医療機関にとって大きな魅力となります。
自身のキャリアに明確なビジョンを持っている
転職回数の多い先生は、転職経験を通じて、自分にとって理想的な働き方や医療への取り組み方が明確になっているケースが多いとされています。目標に向けて積極的に行動する姿勢は、意欲的で前向きな人材として評価される可能性があります。過去の経験を踏まえた現実的なキャリアプランを持っている点も、採用担当者に安心感を与える要素となるでしょう。
また、自己分析や目標設定の能力が高いのも、転職経験豊富な医師の特徴と言えます。自分の強みと弱みを客観的に把握し、それに基づいた適切な職場選択ができることは、長期的な定着につながる要素として、採用担当者にアピールできる強みになります。
転職回数が多い医師が転職活動で意識したいポイント

転職回数の多さはマイナスではないものの、採用担当者へ適切にアピールしなければ、思い通りの転職活動ができない可能性があります。そのような事態に陥らないためにも、以下の点には気を付けましょう。
- 転職理由を明確にして正直に伝える
- 転職回数をアピールできる強みに変える
- 譲歩できる条件を整理しておく
転職理由を明確にして正直に伝える
転職理由については曖昧にせず、具体的で説得力のある説明を準備しておくことが重要です。キャリアアップや専門性向上など前向きな理由を中心に据えながら、自身にも反省すべき点があったことを率直に認める姿勢が好印象を与える可能性があります。他責的な表現は避け、自己の改善に取り組んできた経緯などを伝えることを意識しましょう。
転職に至った経緯を時系列で整理し、一貫したストーリーとして説明できるよう準備しておくと有用です。各転職がどのような学びや成長につながったかを具体的に示していくと、計画性のあるキャリア形成をしているとアピールできます。
転職回数をアピールできる強みに変える
豊富な転職経験を通じて得られた知識やスキルを具体的に整理し、転職先で活かせる価値として明確に伝えるのも重要です。多様な医療現場での経験を、問題解決能力や適応力の高さを示す証拠として活用できる可能性があります。異なる組織での成功事例や改善提案の実績があれば、積極的にアピールしてみましょう。
その他、転職経験を通じて培われたコミュニケーション能力や人間関係構築スキルも重要な強みになります。様々なタイプの同僚や患者さまとの関わりを通じて得られた経験は、どのような職場でも活かせる汎用性の高いスキルとして評価される可能性があります。
職歴は嘘をつけないからこそ、対応している症例数や件数など、職務経歴書に書く実績でカバーしていくと良いでしょう。
譲歩できる条件を整理しておく
時には、転職回数の多さを理由に条件面で妥協が必要になる場合があるかもしれません。そのような場合に備えて、事前に譲歩可能な条件を明確にしておくと良いでしょう。給与水準や勤務時間、業務内容など、どの部分であれば調整可能かを検討し、交渉の余地を残しておくと転職成功につながる可能性が高くなります。
その際、優先順位を明確にして、絶対に譲れない条件と調整可能な条件をわけて考えることが大切です。転職先の医療機関にとってもメリットのある提案ができれば、条件交渉も前向きに進められるかもしれません。
転職回数が多い医師でも評価される履歴書・職務経歴書の書き方

履歴書や職務経歴書の書き方次第で採用担当者に与える印象は大きく変わります。工夫次第で、むしろ「豊富な経験」として評価されることも可能です。ここからは、転職回数が多い先生でも評価される履歴書・職務経歴書の書き方について、以下のポイントに分けて解説します。
- 職務経歴書は成果に焦点を当てる
- スキル別に経験をまとめる
- 複数の経験から得た強みをアピールする
- 転職の経緯をポジティブに伝える
職務経歴書は成果に焦点を当てる
職務経歴書を書く際は、各職場での具体的な成果や実績を数値化して記載することが重要です。手術件数や診療患者数、専門外来の開設実績など、客観的に評価できる指標を用いて自身の貢献度を明確に示すようにしましょう。内視鏡検査の実施件数や訪問診療での担当患者数など、専門性を活かした具体的な業務実績も記載しておくと良い印象を与えられる可能性があります。
加えて、チーム医療での役割や改善提案の実績があれば、重要なアピールポイントとなります。医療安全への取り組みや患者満足度向上への貢献など、数値以外の成果についても具体的なエピソードとともに記載すると、より説得力のある経歴として活用できるでしょう。
【記載例】
<臨床実施の表現>
- OK例:年間約500件の内視鏡検査を実施し、早期胃癌の発見率向上に貢献
- NG例:内視鏡検査を日常的に担当し、幅広い症例を経験
<チーム医療への取り組み>
- OK例:週1回の多職種カンファレンスを主導し、情報共有体制を改善
- NG例:職種と連携しながら診療にあたり、コミュニケーションを意識
スキル別に経験をまとめる
転職経験の多さを活かし、診療科別や技術別に経験を整理して記載することで、専門性の幅広さをアピールできます。内科、外科、救急医療など、それぞれの分野での経験年数や主要な症例数を明記し、総合的な診療能力の高さを示していきましょう。
その他、特定の医療技術や検査手技についても、習得している技術を体系的に整理して記載する方法も効果的です。最新の医療機器や診療システムへの対応経験も、技術力の証明として有効なアピール材料となる可能性があります。
採用担当者が判断しやすいようにわかりやすく経験をまとめ、自己アピールとして活用しましょう。
【記載例】
<内科>
- OK例:複数の総合病院にて累計10年以上勤務し、生活習慣病外来を中心に担当。インスリン導入患者数は通算年間40名以上
- NG例:複数の病院で内科外来を担当し、生活習慣病診療に携わる
<外科>
- OK例:異なる外科チームで累計100件以上の腹腔鏡手術に従事。そのうち30件を執刀
- NG例:外科チームに所属し、腹腔鏡手術を含む各種手術に参加
<救急>
- OK例:地域基幹病院・地域病院での経験を通じ、延べ2,000件超の救急外来を担当。多発外傷や急性心筋梗塞など重症例も経験
- NG例:救急外来で幅広い症例に対応
<技術・検査(手技)>
- OK例:内視鏡(胃・大腸合わせて延べ2,500件以上)、エコー(腹部・心臓)を習得。電子カルテや遠隔診療システムの立ち上げにも対応
- NG例:内視鏡やエコーの経験があり、電子カルテも使用
複数の経験から得た強みをアピールする
異なる医療機関での経験を通じて身につけた問題解決能力や改善提案力を、具体的に記載するのも効果的です。組織運営の効率化や患者サービスの向上に貢献した事例があれば、転職先でも同様の価値を提供可能だとアピールできます。
さらに、多様な医療現場での経験により培われたコミュニケーション能力や適応力についても、具体的なエピソードとともに記載していくと良いでしょう。困難な状況での対応経験や、異なる組織文化への適応事例なども、強みとして訴求できる要素になり得ます。
【記載例】
<救急科勤務>
- OK例:受診患者数の増加に対応するため、トリアージ体制の見直しを提案・実施。待機時間を平均20分短縮し、患者満足度向上に貢献
- NG例:救急外来での患者増加に対応し、日々診療に従事
<外科病棟勤務時>
- OK例:術後感染対策のマニュアルを改善。チーム全体で共有し、感染率を前年度比で15%減少させた実績あり
- NG例:外科病棟において感染対策に参加し、患者ケアに努める
<クリニック勤務時>
- OK例:電子カルテの導入初期におけるスタッフ研修を主導。システム定着を早期に実現し、診療効率向上に寄与
- NG例:電子カルテの導入時にスタッフと協力しながら診療
<複数の病院での勤務経験>
- OK例:異なる診療スタイルや文化に柔軟に順応。どの現場でもチームメンバーと円滑に協力関係を築き、業務を遂行
- NG例:複数の病院で勤務し、それぞれの職場で求められる業務を経験
転職の経緯をポジティブに伝える
各転職の理由を前向きな表現で簡潔に記載することが、転職活動では重要です。スキルアップや専門性向上を目的とした転職であると明確に伝え、計画的なキャリア開発をしているのだとアピールしましょう。
そのためには、転職により得られた学びや成長についても具体的に記載し、各経験がどのように現在のスキルや価値観の形成に寄与したかを説明すると効果的です。失敗や反省点についても率直に認めつつ、それをどのように改善に活かしているかを示せれば、成長意欲と自己改善能力をアピールできます。
【記載例】
<急性期から慢性期への転職>
- OK例:前職では急性期医療に携わり、判断力とスピード感を培いました。その後、患者さまと長期的に関わる医療にも取り組みたいと考え、慢性期医療の現場へ転職。現在は一人ひとりを継続的に支えるスキルを身につけることができました。
- NG例:急性期医療は多忙で体力的にも厳しかったため、負担の少ない慢性期医療を選びました。
<短期在籍の経験>
- OK例:勤務環境が合わず短期間の在籍となってしまった職場もありましたが、その経験から職場選びの基準を明確にすることの大切さを学ぶことができました。その学びを活かし、以降は将来の目標に沿った職場を選択し、長期的に成果を出せるよう努めています。
- NG例:短期間で退職した職場もありますが、その後は長く働けるところを選んでいます。
<複数病院での経験>
- OK例:専門性を深める目的で複数の病院に勤務し、それぞれの現場で多様な診療に携わってきました。その経験を通じて幅広い疾患に対応できる総合診療力を培うことができ、今後のキャリアの大きな強みになっていると考えています。
- NG例:転職を繰り返す中で、一つの職場に長く勤めることが難しい時期もありました。
<人間関係での学び>
- OK例:一時的に人間関係で課題を抱えた経験もありましたが、その中で建設的なコミュニケーションの重要性を学びました。以降はこの経験を活かし、円滑な人間関係の構築に努めています。
- NG例:人間関係のトラブルが原因で退職したこともありました。
なお、さらに具体的な自己PRの書き方は以下の記事でも紹介していますので参考になさってください。
応募書類作成は転職コンサルタントに頼るのも有効
ここまでご紹介したように、履歴書や職務経歴書の工夫次第で転職回数の多さを強みに変えることができます。とはいえ、実際に自分で成果を整理したり、前向きに見える表現にまとめたりするのは大変な作業です。
そんなときは、転職コンサルタントにサポートを依頼するのも一つの方法です。第三者の視点から先生のご経歴を整理し、採用担当者に響く強みを見つけてくれるだけでなく、表現のブラッシュアップや伝え方の工夫まで一緒に行ってくれます。
「自分では気づかなかった経験をアピールポイントに変えてもらえた」という声も多く、安心して転職活動に臨める大きな助けになるでしょう。
採用担当者が最も気にする転職理由の質問への答え方

ここからは、実際にドクタービジョンのコンサルタントが採用担当者からよく聞かれる「気になる転職理由」を紹介します。以下のケース別にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
- キャリアプランの明確化を求める質問への回答
- 人間関係や適応力に関する懸念への回答
- スキルや専門の一貫性に関する質問への回答
キャリアプランの明確化を求める質問への回答
キャリアプランに関する質問としては、以下のようなものがあります。
- なぜ短期間で職場を変えられたのですか?
- 今回はどのようなキャリアを築きたいとお考えですか?
採用担当者としては、「転職が多いけど、医師としてどうなりたいの?」と聞いています。転職した結果、どんなキャリアを築きたいのかを知りたいと考えています。
このような場合は、まず自身にも改善すべき点があったことを率直に認める姿勢が大切です。そのうえで、一貫したキャリア目標に基づいた転職であることを強調できれば、説得力のある回答になります。
【回答例】
これまでの転職の中で、自分の準備不足や見通しの甘さがあったと反省しています。ただ、その経験を通じて医師として様々な現場を経験し、急性期から慢性期まで幅広い診療能力を磨くことができました。
結果として短期間での転職になってしまった職場もありますが、それぞれの経験が確実にキャリアの糧になっています。今後は、これまでに得た総合診療力を活かしつつ、在宅医療分野で長期的に患者さまを支えられるキャリアを築いていきたいと考えています。
人間関係や適応力に関する懸念への回答
人間関係や対応力に関する質問としては、以下のようなものがあります。
- 前の職場ではどのような人間関係でしたか?
- 周りのスタッフさんとの連携で意識していたことはありますか?
- 当院のような環境で問題無くやっていけますか?
このような質問を受けた場合、「各職種の専門性を尊重しながら建設的なコミュニケーションを心がけてきた」と伝えると良いでしょう。
【回答例】
看護師や薬剤師など、それぞれの専門職の皆さんの意見を尊重しながら、患者さまにとって最良の医療を提供するために積極的に話し合いをしてまいりました。
結果的に信頼関係が深まり、円滑に協力できるようになった経験があります。
様々な組織文化や診療スタイルを経験したことで、どのような環境でも円滑に業務を遂行できる自信があると、具体的な事例とともに説明していくと良いでしょう。
スキルや専門の一貫性に関する質問への回答
スキルや専門に関する質問としては、以下のようなものがあります。
- 様々な病院で勤務されていますが、専門性やスキルに一貫性はありますか?
このような質問を受けた場合、転職経験を通じて総合診療能力が向上していると強調すると良いでしょう。
【回答例】
異なる医療機関での勤務を通じて、診療科や背景は多様でしたが、一貫して患者さまをトータルで診る力を磨いてきたと考えています。
急性期で培った判断力と、慢性期での長期フォロー経験は、どちらも医師として欠かせない資質と考えています。
採用担当者にスキルアップやキャリアアップを目的とした前向きな決断をしてきたのだとアピールできれば、転職回数の多さによる懸念を払拭できる可能性があります。
採用担当者にスキルアップやキャリアアップを目的とした前向きな決断をしてきたのだとアピールできれば、転職回数の多さによる懸念を払拭できる可能性があります。
転職活動の回数が多いのにも関わらず高く評価された事例

ドクタービジョンにご相談いただいた先生の中には、「30代ですでに5回の転職」を経験している方がいらっしゃいました。
この先生は、もともとは医局に所属していたものの、その後は美容皮膚科へ複数回の転職を経験。さらに家庭の事情もあり、親族のヘルプ要請で内科へ戻られるなど、ご経歴は一見すると「離職しやすい」という印象を与えかねないものでした。
実際に、1年未満や数か月での退職歴もあり、応募段階で書類選考が通らないケースも少なくなかったそうです。それでも最終的には採用担当者に前向きに評価され、地方から都内の医療機関への転職が決まりました。その理由を詳しく見ていきましょう。
人柄重視で採用を勝ち取った
この先生の大きな強みは「柔らかな雰囲気」と「協調性の高さ」でした。どの職場でもチームで働く以上、採用側は人柄も重視します。とりわけ医師不足の現場では「すぐに溶け込み、長く働いてもらえるか」も評価ポイントの一つです。
先生ご自身では伝えきれない部分をコンサルタントが医療機関に対して「人柄の良さ」や「誠実さ」を丁寧にお伝えできたことも、前向きな評価につながりました。
基本を押さえた面接での対応
もう一つの成功要因は、面接での対応です。転職理由について他責的な表現を一切使わず、むしろ「自分の準備不足や見通しの甘さがあった」と率直に認めました。
例えば、当時の勤務先である親族が営む内科を離職する理由についても「親族の要請で戻ることを決めてしまったが、親族ゆえに人間関係が複雑で妻に大きな負担をかけてしまった」と説明。そのうえで「働き方を深く見直し、長期的に働ける職場を選びたい」と誠実に語ったことが、採用担当者に強い印象を与えました。
また、面接の際は転職支援を担当したコンサルタントとの事前対策も功を奏しています。面接での回答内容を事前に整理し、他責にならないよう細心の注意を払った準備が、当日の自然で誠実な受け答えにつながりました。
転職回数で悩んだ医師がまずやるべきこと3選

転職回数の多さが気になる場合、まずは冷静に現状を整理し、今後のキャリアを前向きに考える準備を進めることが大切です。ここからは、転職回数で悩んだときに最初に取り組むべきことを3つご紹介します。
- キャリアの棚卸しを行う
- 長期的なキャリアプランを描く
- 転職のプロに相談する
キャリアの棚卸しを行う
まずはこれまでの勤務経験を時系列で整理し、得られたスキルや知識、成果を明確にしましょう。短期間の勤務でも、そこで得た学びや成長をポジティブに捉え直すことが重要です。
また、キャリアの棚卸しをすることで、自分の強みや専門性がどこにあるのかを再確認できます。過去の転職理由や得られた経験を客観的に振り返ることで、今後の転職理由を一貫性のある形で説明しやすくなります。
長期的なキャリアプランを描く
次に、今後どのような医師としてのキャリアを築きたいのかを具体的に描きましょう。専門医資格の取得、地域医療への貢献、研究や教育への関わりなど、自分が目指す方向性を明確にしておくことが大切です。
長期的なキャリアプランを持つことで、転職の際にも「目標に沿った選択をしている」と採用担当者に伝えやすくなります。将来のビジョンを明確にすれば、転職回数の多さも「目的に沿った行動の結果」として前向きに評価されやすくなるでしょう。
転職のプロに相談する
一人で悩みを抱え込まず、転職エージェントやキャリアコンサルタントに相談することも有効です。第三者の視点から経歴を整理してもらえるだけでなく、採用担当者にどのように伝えるべきか具体的なアドバイスを受けられます。
また、非公開求人や希望条件に合致する職場の提案を受けられることもあり、自分一人で探すよりも選択肢を広げられるのが大きなメリットです。転職活動の不安を軽減し、前向きに進めるためにも、専門家のサポートを活用するのがおすすめです。
転職回数の多さで困ったら「ドクタービジョン」へご相談を
転職回数が多いことに不安を感じている先生は、まずは「ドクタービジョン」にご相談ください。私たちは医師専門の転職エージェントとして、多くの先生の転職をサポートしてきた実績があります。
転職回数の多さをネガティブに見せないための履歴書や職務経歴書の書き方、面接での伝え方についても丁寧にアドバイスいたします。また、先生のこれまでのご経験をどのように強みに変えていくかを一緒に整理し、最適な職場探しをお手伝いします。
非公開求人を含む豊富な求人情報の中から、先生のキャリアプランやご希望条件に合った医療機関をご紹介できる点も大きな強みです。
「転職回数が多くて不安」「次こそは長く働ける職場を見つけたい」と感じている先生は、ぜひお気軽にご相談ください。
医師の転職回数はハンデにならない場合もある。キャリアに沿った転職をしよう

医師の転職回数は、一見するとハンデのように思えるかもしれません。しかし、実際にはそれまでの経験をどう活かし、どのようにキャリアを築いていきたいのかを明確に示すことで、大きな強みに変えることができます。
重要なのは、転職の回数そのものではなく、そこから得た学びやスキル、そして今後のキャリアプランとの一貫性です。採用担当者は「この先生が自院で長く活躍してくれるかどうか」を重視しているため、誠実に自分の経験を伝える姿勢が何より大切です。
転職理由や経歴に不安がある場合でも、プロのサポートを受けることで安心して転職活動を進められます。キャリアの棚卸しや自己PRの整理、面接対策など、専門家の力を借りながら準備を整えていけば、転職回数の多さは必ずしも不利にはなりません。
これから転職を検討している先生は、ぜひキャリアの方向性を明確にし、自分に合った医療機関との出会いを見つけていきましょう。
1分で登録完了!コンサルタントへの転職相談
「転職について気になることがある」「周りの転職活動の動向を知りたい」など、
まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。